企業概要と最近の業績
株式会社データホライゾン
2025年6月期第3四半期(2024年7月1日~2025年3月31日)の連結業績は、売上高が33億6900万円となり、前年の同じ時期と比べて11.8%増加しました。
営業利益は5億2400万円で22.1%の増加、経常利益は5億4000万円で23.4%の増加、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億5500万円で22.8%の増加となり、2桁の増収増益を達成しました。
主力のデータヘルス関連事業では、国が推進する「データヘルス計画」を背景に、健康保険組合や自治体向けに健診情報などを分析し、健康づくりを支援するサービスの需要が拡大しました。
また、調剤薬局関連事業においても、医療DXの流れを受けてオンライン資格確認や電子処方箋に対応したシステムの導入が進み、業績に貢献しました。
国の医療制度改革が同社の事業にとって強力な追い風となっていることが、好調な業績につながっています。
価値提案
データホライゾンが提供する価値は、医療費の適正化と健康増進支援です。
レセプト分析によるコスト削減の提案から、地域住民の健康状態を踏まえた施策の立案支援まで幅広いサービスを展開しています。
医療費の増大は多くの自治体や健康保険組合にとって深刻な課題です。
特許取得済みの分析技術を活用し、膨大な医療データから無駄なコストを洗い出して提案できる点が差別化のポイントになっています。
【理由】
なぜこの価値を打ち出すに至ったかといえば、日本の社会保障費が増大し続けている現状に対応するためには、医療費をどう抑制し、同時に国民の健康レベルを高めるかが重要となるからです。
そのニーズを満たすソリューションとして、レセプト分析をコアとした同社の取り組みが大きな説得力を持ち、自治体や健康保険組合から継続的な需要を獲得しています。
主要活動
主要活動には、医療データの収集と分析、そして自社システムの開発や運用が含まれます。
あらゆる診療報酬明細書のデータを正確に取り扱い、統計学やAIなどの技術を組み合わせて高度な知見を引き出すプロセスが強みです。
こうした分析結果をクライアントにわかりやすく提示するために、ソフトウェアやダッシュボードの開発が行われています。
【理由】
なぜこれらの活動が必要かというと、データを収集するだけではなく、そのデータを理解しやすい形で提示し、施策につなげるまでのワンストップサービスが求められているからです。
データホライゾンは分析から運用サポートに至るまで手掛けることで、顧客との関係を強化し、継続的な契約につなげています。
リソース
最大のリソースは、医療ビッグデータそのものと、特許を取得した分析技術を活用できる専門人材です。
データはレセプトをはじめとする非常に機微な情報を含むため、扱いには厳格なセキュリティが必要です。
同社ではセキュリティ体制の整備に加えて、知見と経験を持つアナリストやエンジニアを確保することが競合優位性を維持する鍵となっています。
【理由】
なぜここに注力するかといえば、医療データ分析の分野は高度な専門知識と信頼性が求められ、簡単には他社が参入しにくい市場構造があるからです。
その独自性を守り続けるため、継続的に人材育成や技術開発へ投資を行い、医療業界に特化したノウハウを強化しています。
パートナー
パートナーシップとしては、自治体や健康保険組合に加え、DeNAグループとも連携しています。
特に自治体や健康保険組合は、同社の分析サービスを活用する主要なクライアントであると同時に、大量のレセプトデータを提供してくれる存在でもあります。
さらに、DeNAグループとの関係は、IT分野でのノウハウやネットワークを活かす上で重要な意味を持っています。
【理由】
なぜこうした連携が不可欠かといえば、医療データ分析だけではなく、システムの開発や新たなサービス展開を推進するために、多角的なリソースとネットワークが必要だからです。
こうしたパートナーシップによって、幅広い顧客基盤と革新的なサービスを同時に獲得できる仕組みを作っています。
チャンネル
営業チームや公式ウェブサイトが中心的なチャンネルとなり、自治体や健康保険組合へのコンサルティング提案が主な流通経路です。
【理由】
なぜこのチャンネル構造を採用しているかといえば、医療費適正化のニーズを直接ヒアリングしながら提案する手法が最も効果的であり、公式ウェブサイトを通じて企業の信頼度や実績をアピールできるからです。
医療関連のサービスは導入検討プロセスが慎重になる傾向があるため、オンラインとオフライン両面で丁寧なフォローが重要になっています。
こうして得た案件が新たな実績となり、評判が広がることで、より多くの自治体や保険組合から問い合わせが増える好循環を生んでいます。
顧客との関係
顧客との関係は、コンサルティング提案とサポート体制の二本柱で構築されています。
単なるデータ分析レポートの提供ではなく、分析結果に基づいた改善策や施策の実行支援まで踏み込むことで、強固な信頼関係を築いています。
【理由】
なぜこの形態を取るかといえば、医療費の抑制や健康増進施策は実行までが重要であり、データ分析の結果をどう活用するかによって成果が左右されるからです。
データホライゾンは、導入後のコンサルティングやフォローアップを通じて、顧客が実際にコスト削減や健康指標の改善といった成果を得られるように導くことを重視しています。
その結果、長期にわたるリピート契約や追加受注が期待できるのも強みです。
顧客セグメント
主な顧客セグメントは自治体と健康保険組合です。
これらの組織は医療費適正化と住民や加入者の健康増進に責任を負っており、ビッグデータ分析の活用意欲が高い特徴があります。
【理由】
なぜ自治体と健康保険組合が狙い目となるかというと、国全体で進む医療費増大の中で、予防医療や早期介入の重要性が年々高まっているからです。
これらの組織にとって、レセプト分析は無駄なコストを削減するだけでなく、住民サービス向上にも直結するため、積極的に導入しやすい領域となります。
データホライゾンはこのニーズを的確に捉え、確固たる市場ポジションを築いています。
収益の流れ
収益は、分析サービスの提供によるコンサルティングフィーやシステム導入費用、運用サポート費用から得ています。
カスタマイズされたレポートやアドバイスを行うことで付加価値を高め、高単価な案件につなげやすいのが特徴です。
【理由】
なぜこの収益形態を採用しているかといえば、医療ビッグデータ分析は高度な専門知識を要し、一般的なシステム開発とは異なる付加価値を提供できるため、顧客は価格よりも効果を重視する傾向があるからです。
さらに、自治体や健康保険組合が契約を継続しやすいように、運用サポート契約を組み合わせることで安定的な収入基盤を確保し、継続的な関係性を築いています。
コスト構造
同社のコストは大きく分けてシステム開発や運用にかかる開発コスト、そして専門人材の確保と育成にかかる人件費が中心です。
医療情報を扱う以上、データセキュリティやプライバシー保護のための設備投資も必要となります。
【理由】
なぜこれらのコストが大きなウェイトを占めるかといえば、分析技術を高度化し続けるためには常に最新のシステムやツールを導入し、データ管理体制を強化し続けなければならないからです。
さらに、医療制度や保険制度の知識を持つ専門家や分析エンジニアの確保が収益と直結するため、人件費が継続的に増加する傾向にあります。
これらのコスト構造は、同社のサービスの質を高めるために不可欠であり、競合他社との差別化要因にもなっています。
自己強化ループ
同社の自己強化ループは、医療ビッグデータの分析とその結果を自治体や健康保険組合へ還元することで生まれます。
より正確な分析を行えば、顧客は医療費削減や健康施策の改善を実感しやすくなり、その効果が周囲にも伝わることで、新たな受注やデータの収集機会が増える好循環に入ります。
データが増えるほど分析技術がさらに磨かれ、精度向上によって顧客満足度が高まり、口コミや実績を通じて更なる契約を獲得するという自己強化の仕組みが成り立っています。
このようなサイクルは、単なる一度きりの分析サービスではなく、長期的なパートナーシップを構築できる体制を持つ同社だからこそ可能になるものです。
今後も多くの自治体や健康保険組合が医療費負担の軽減や健康増進施策の重要性を認識する中で、このフィードバックループはさらに強化される見込みです。
採用情報
採用面では、初任給が月給21万5,000円から35万円まで幅広い設定となっています。
情報システムやデータ分析に関する高度なスキルを求めるポジションも多く、専門性に応じた給与体系を構築しているようです。
平均年間休日は125日(2023年度実績)と比較的多めで、オンとオフをしっかり切り替えたい人にとっては魅力といえます。
採用倍率は公表されていませんが、医療ビッグデータや分析技術に興味を持つ人材であれば、やりがいを感じられる環境が整っている可能性があります。
株式情報
同社の株式は、東証グロース市場に上場しており、銘柄コードは3628です。
2025年1月30日時点での1株当たり株価は498円となっています。
現在は配当金の情報が開示されておらず、投資家にとっては長期的なキャピタルゲインや今後の成長に期待する形となるでしょう。
赤字が続いている営業利益をいかに改善していくかが、株価上昇のカギになりそうです。
未来展望と注目ポイント
医療費の増大や少子高齢化といった社会的背景から、レセプト分析の需要は今後も高まっていく見通しです。
データホライゾンにとっては、自治体や健康保険組合を中心に多くの顧客と長期契約を結ぶことで、安定した収益基盤を築くチャンスがあります。
加えて、DeNAグループとの連携や新たなビッグデータ活用策を模索することで、より高度なサービス展開を図る可能性も十分に考えられます。
たとえば、AIによる予防医療の精度向上や、病気の早期発見に関するソリューションなど、ヘルスケア業界全体を変革するプロジェクトにつながる機会が広がるでしょう。
今は営業利益で赤字を計上している同社ですが、今後のIR資料や成長戦略を継続的にウォッチすることで、その投資がいつ実を結ぶのかを見極めることができます。
社会的意義の大きい事業を扱う企業だからこそ、さらなる技術革新とサービス強化により、一気に飛躍する可能性を秘めているといえます。

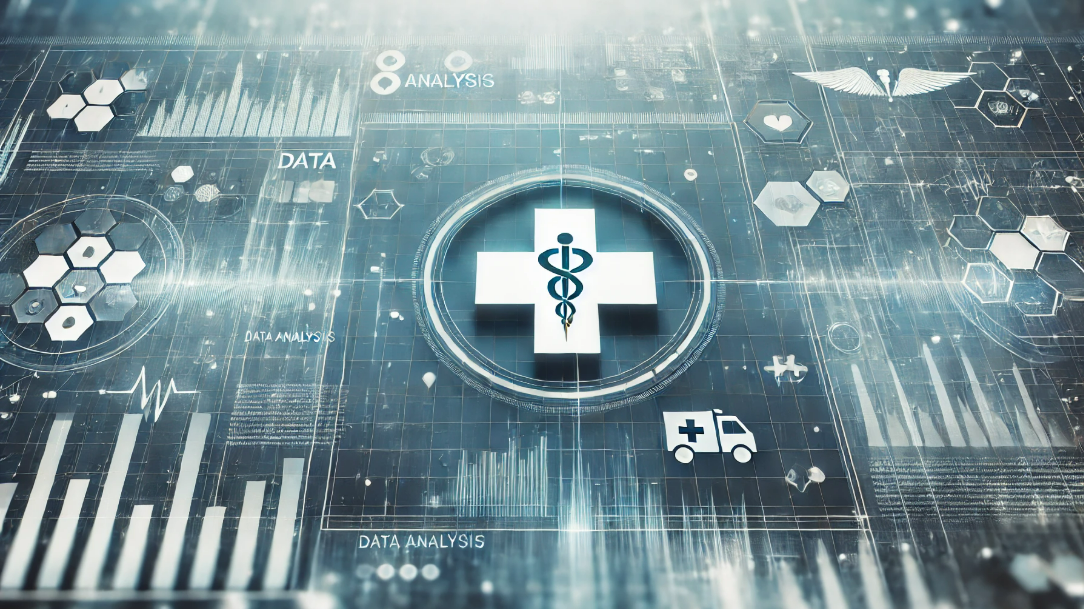


コメント