企業概要と最近の業績
株式会社デジタルプラス
2025年5月15日に発表された、2025年9月期の中間決算(第2四半期)についてお伝えしますね。
この期間の累計売上高は25億5,400万円で、前年の同じ時期と比べて4.1%の増加となりました。
しかし利益の面では、営業利益が1億8,300万円と、こちらは24.1%の減少となり、増収減益という結果です。
主力のデジタルギフト事業は好調で売上を牽引しました。
ただ、そのデジタルギフト事業で新規顧客を獲得するための広告宣伝費が増加したことが、全体の利益を押し下げる主な要因となったようです。
ビジネスモデルの9つの要素
価値提案
デジタルギフトとオンラインメディアを軸に、多様な選択肢と利便性をユーザーに提供していることが大きな特徴です。
たとえばデジタルギフトではポイントや電子マネー、人気のECサイトクーポンなどと交換できる幅広いサービスラインナップを用意し、ユーザーが自分の好みに合わせて自由に選択できる点が評価されています。
【理由】
キャッシュレス化やオンライン決済の普及が進む中で、利用者がより簡単かつお得にデジタルコンテンツやサービスを享受できる仕組みを求めているからです。
同社の価値提案は単なるギフト機能にとどまらず、オンラインメディアによって情報を収集できる場を同時に提供することで「お得×情報収集」という新しいユーザー体験を実現していることも強みといえます。
こうした総合的な価値設計が、業績好調の基盤になっていると考えられます。
主要活動
同社が最も注力しているのは、デジタルギフトやポイント交換サービスの開発と運用、そして集客力の高いメディアの運営です。
技術チームは常に新たな機能拡充やUI・UXの改善に取り組み、ユーザーが利用しやすいサービス環境を整えています。
さらにメディア運営チームでは、「漫画大陸」や「すーちゃんモバイル比較」など、ニーズに合致したコンテンツ企画とSEO対策を実施し、広告収入とトラフィックを獲得している点が特筆されます。
【理由】
なぜこうした活動に注力するに至ったかというと、フィンテック事業が利益を生み出す一方で、メディア事業が新規ユーザーとの接点や情報発信の場として大きな役割を果たすからです。
両者が相乗効果を生むことで、ユーザー基盤をさらに拡大できる戦略を組み立てています。
リソース
同社のリソースは、フィンテックやウェブメディアを運営するためのデジタルプラットフォーム、提携先企業や広告主とのネットワーク、そして高度な専門知識を有する人材に集約されます。
プラットフォームはユーザーが安全かつスムーズにポイント交換やギフト送付を行えるよう、セキュリティと操作性を重視して設計されているのが特徴です。
【理由】
なぜここを強化しているかといえば、信頼性の高い技術基盤があってこそ決済や交換サービスがスムーズに回り、利用者も安心してサービスを利用できるからです。
また、メディア運営においてはSEOやWebマーケティングの専門家を多く擁しており、コンテンツ制作からトラフィック分析まで一貫して行える体制が競合優位を生む大きな要素となっています。
パートナー
金融機関や電子決済サービス、さらにコンテンツプロバイダーなどとの多彩なパートナーシップを持つことが、事業拡大の鍵となっています。
フィンテック分野では、交換可能なポイントやクーポンの種類を増やすために、大手企業との連携を積極的に進めています。
メディア事業でも出版社や広告代理店、通信キャリアなどとの提携を行い、多様な情報やサービスを提供可能にする体制を強化しています。
【理由】
なぜこうしたパートナー戦略を重視しているのかといえば、ユーザーが求める選択肢を幅広く網羅するためには自社単独ではなく、専門領域を持つ企業との連携が不可欠だからです。
さらにパートナー各社にも、新たな顧客接点を得るメリットがあるため、双方にとってWin-Winの関係を築いています。
チャンネル
サービスの提供チャンネルは、自社ウェブサイトやモバイルアプリだけでなく、提携先のプラットフォームやSNSなど多岐にわたります。
デジタルギフトやポイントサービスは利用者が「いつでもどこでも」アクセスできることが重要であり、そのためにスマートフォンを主体としたUI設計を強化しています。
【理由】
なぜこのように複数のチャンネルを活用するかというと、現代のユーザーは検索サイトやSNSなどさまざまな経路を通じて情報収集やサービス利用をするためです。
また、メディア事業ではSEOに力を入れ、検索エンジン経由のトラフィック流入を大幅に増やしながらSNSでのシェアも促進していることが、多面的な集客へとつながっています。
顧客との関係
同社が重視するのはユーザーとの長期的な関係構築です。
オンラインサポート体制を整え、問い合わせやトラブルへの迅速な対応を行うと同時に、利用者の声を分析してサービス向上に生かしています。
さらに、メディアを活用しながらユーザーコミュニティを育成し、新商品の先行案内やアンケート調査などで双方向のコミュニケーションを図っています。
【理由】
なぜこうした取り組みを行うかといえば、フィンテックサービスは安心と信頼が鍵であり、広告収入を柱とするメディア運営でもファン層の拡大が収益向上に大きく影響するからです。
常にユーザーのニーズに耳を傾け、サービスをブラッシュアップする姿勢がリピーターや新規顧客の拡大につながっています。
顧客セグメント
デジタルギフトやポイント交換サービスを利用する個人ユーザーはもちろん、メディアコンテンツを閲覧する幅広い層が顧客セグメントとなります。
ポイントやクーポンを活用してお得に買い物をしたい若年層から、スマホ決済に慣れたビジネスパーソンまで多岐にわたります。
【理由】
なぜこれほど顧客セグメントが広いのかといえば、キャッシュレスやスマホシフトが進む現代において、誰もがオンライン上でギフトや情報を入手する可能性が高まっているからです。
また、法人向けのキャンペーンや福利厚生としてポイント交換を導入するケースも見られ、多様なセグメントへの訴求力が同社の強みを支えています。
収益の流れ
大きな柱は、ポイント交換などのフィンテックサービスから得られる利用手数料と、メディア事業による広告収入です。
さらに提携パートナーとの共同キャンペーンから発生する紹介手数料や、コラボ企画に伴うスポンサー収益など、複数の収益源を組み合わせています。
【理由】
なぜこれが重要かといえば、単一の収益モデルに頼ると市場変動や規制変化によるリスクが大きくなるためです。
同社は収益ポートフォリオを意図的に分散させ、安定性を高めながら、成長のチャンスを逃さないように設計しています。
コスト構造
プラットフォームの開発や運用に係るシステム関連費用が大きなウエイトを占めます。
また、マーケティング費用や広告費、人件費も重要なコスト要素です。
【理由】
なぜこうしたコスト構造になっているかといえば、オンラインサービスを拡張していくうえでの技術投資と、ユーザーを獲得するための広告・プロモーションが欠かせないからです。
さらにセキュリティ強化やサーバー運用などのインフラコストもあり、これらはフィンテック事業を安全に運営するための必要投資といえます。
同時にメディア事業では継続的なコンテンツ更新やライター費用、SEO対策費用などもかかるため、全体として投資回収を意識した運用が行われています。
自己強化ループについて
同社が展開するデジタルギフトやメディア事業では、それぞれの利用者が増えるほどサービス全体が活性化し、さらなる利用者や提携先を呼び込む自己強化ループが生まれています。
たとえばフィンテック事業では、交換先や提携先が増加するほどユーザーが利用したいと感じる機会が増え、さらにユーザー数が上昇することで新たなパートナー企業も参加しやすくなります。
一方、メディア事業はユーザーが多いほど広告主の注目度が高まり、広告収入が増えることでコンテンツの拡充が可能になり、より多くのユーザーを呼び込む好循環へとつながっています。
このように双方の事業が絡み合う形で、ユーザー拡大がさらなるサービス強化を促進し、その結果として利益が増加し、さらに事業開発に再投資できる流れを生み出している点が注目されます。
採用情報と株式情報
同社は人材育成にも積極的で、2025年4月から新卒初任給を大幅に引き上げる方針を打ち出しています。
さらに2026年度には初任給50万円の優待性枠を新設する予定があるとのことです。
平均休日や採用倍率などの詳細情報は公表されていませんが、こうした待遇改善によって優秀な人材を確保し、事業拡大のエンジンとする狙いがうかがえます。
株式情報としては、東証グロースに上場しており、銘柄コードは3691です。
2024年9月期は無配ですが、黒字転換を果たしたことが今後の配当方針にどのように反映されていくかも注目されています。
なお、2025年1月14日時点で株価は832円となっており、事業の拡大とともに今後の株価動向にも関心が寄せられています。
未来展望と注目ポイント
今後セレスがさらなる成長を遂げるためには、まずポイントサイト「モッピー」での会員増強と粗利率の向上が重要なテーマになります。
広告主との連携強化やユーザー満足度を高める施策に投資しつつ、オペレーション効率を上げることで利益率を改善する取り組みが進められるでしょう。
暗号資産事業においては、規制環境の変化や相場のボラティリティに左右されやすいものの、長期的にはデジタル資産市場の拡大によるメリットが見込まれます。
ここで安定的な運営体制とセキュリティを確立しつつ、新たなサービスを開発することでユーザー獲得を継続できるかが鍵を握るでしょう。
さらに暗号資産取引所とポイントサービスを連動させる仕組みを拡充することで、ユーザーの利便性を高めつつ、広告収益と手数料収入の両面で相乗効果を狙うことも期待されます。
こうした取り組みを通じて、安定的なキャッシュフローを生むモバイルサービス事業と大きな成長ポテンシャルを秘めたフィナンシャルサービス事業の二軸をバランスよく伸ばしながら、企業価値をさらに高めていくことが注目されるポイントです。

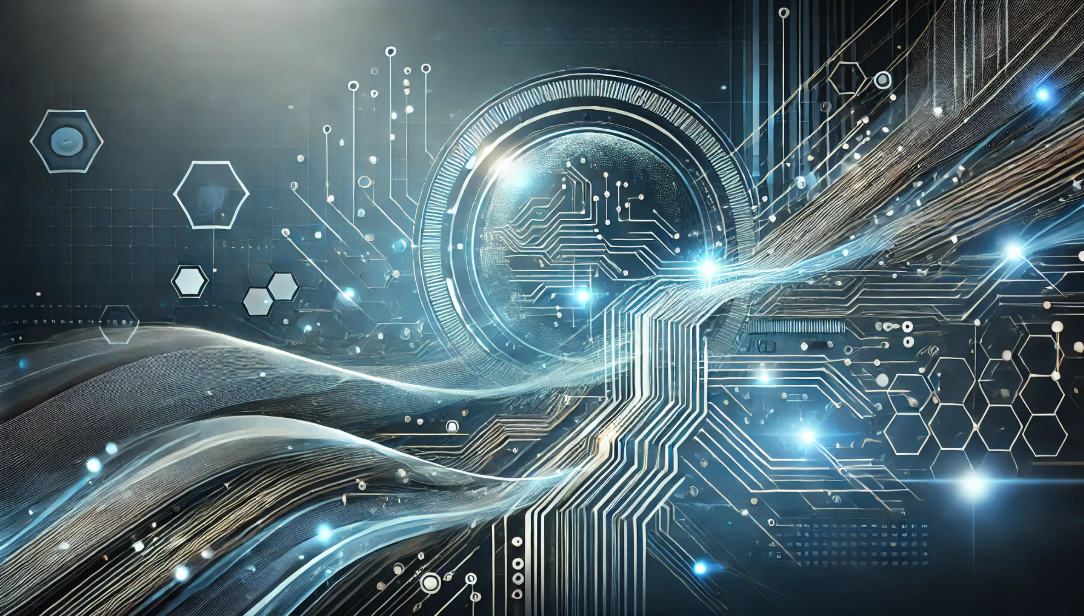


コメント