企業概要と最近の業績
株式会社トリプルアイズ
当社は、AI(人工知能)技術の研究開発と、システムの受託開発(SI)を二つの柱として事業を展開するテクノロジー企業です。
AI・DX事業では、独自のAI画像認識プラットフォーム「AIZE(アイズ)」を活用したソリューションを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。
SI事業では、長年培ってきたIT技術力と経験豊富なエンジニアにより、お客様の業務システムの設計から開発、運用までをサポートしています。
私たちは、AI技術とIT技術の融合により、社会の様々な課題を解決することを目指しています。
2025年7月11日に発表された2025年8月期第3四半期の決算短信によりますと、売上高は32億9,200万円となり、前の期の同じ期間に比べて15.0%の増加となりました。
営業利益は3億1,100万円で、前の期の同じ期間から3.3%の増加となりました。
この業績は、主力であるSI事業において、既存顧客との取引拡大や新規案件の獲得が順調に進んだことが主な要因です。
AI・DX事業も着実に成長しており、事業拡大のための人材投資などを吸収し、増収増益を確保しました。
【参考文献】https://www.3-ize.jp/
価値提案
トリプルアイズは、画像認識や機械学習を活用した高度なAI技術を提供しています。
特にAIZEは、多種多様な業界で役立つプラットフォームを目指して開発されており、企業が抱える課題を解決するためのカスタマイズ性に優れていることが特徴です。
こうした付加価値によって、自社のビジネスモデルにAIを導入したい企業や、業務フローを自動化したい企業にとって頼れる存在となっています。
【理由】
AI技術の進歩によって画像認識や自然言語処理といった分野が急速に市場を拡大しており、これらを実際の企業活動に落とし込むためには、専門的な知識と柔軟な開発体制が必要だからです。トリプルアイズは、早期からAI領域に注力していたこともあり、蓄積したノウハウを基に顧客企業が求める多様なソリューションを提供できるようになりました。
さらに、AIZE自体の汎用性を高めることで、さまざまな場面で使いやすいAI基盤を実現し、顧客満足度を向上させる戦略を取っています。
これが同社の価値提案の核となり、競合他社との差別化を図る大きなポイントにもなっています。
主要活動
AIプラットフォームAIZEの開発と運用、そして企業向けのシステムインテグレーションがメインの活動です。
AIZEは単にソフトウェアを提供するだけでなく、導入時のコンサルティングや、運用後のデータ分析サービスなども含めてサポートしているのが強みです。
その結果、単発の売り切りビジネスに終わらず、継続的な関係構築が可能になっています。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、AIを現場で活用するためには、機械学習のモデル構築だけでなく、実際の業務フローとの連携が不可欠だからです。同社がSI事業にも力を入れているのは、その総合的なニーズに応えるためといえます。
AIとシステム開発の両面で顧客に寄り添う姿勢を示すことで、企業のDX推進を支えるパートナーとしての地位を確立しようとしています。
このような戦略が功を奏し、売上高はもちろんのこと、AI分野の実務経験者が増えるなど社内リソースの充実にもつながっています。
リソース
AIエンジニアやデータサイエンティスト、システム開発エンジニアなど、高度な専門人材を多数抱えていることが大きな強みです。
さらに、自社で蓄積したAI開発のノウハウと、各業界の業務知識を融合することで、競合に負けないサービスを作り上げています。
【理由】
AIやDXという領域は依然として専門家が不足しがちであり、そのなかで一定の技術レベルを保つ人材を確保し続けることが差別化の要となるからです。トリプルアイズは比較的早い段階からAI人材の育成と採用に注力していたため、他社が追随しにくい開発力を確立できました。
また、研究開発費を積極的にかけていることもあり、AIZEの精度向上や新技術の実装にスピード感を持って対応できる点が評価されています。
長期的にAIを活用したビジネスモデルを実現するには、最新技術をキャッチアップする専門家の存在が不可欠であり、同社がリソースの面で優位性を発揮できる理由はここにあります。
パートナー
技術提携先や販売代理店など、多角的なパートナーシップを築いています。
特に画像認識やクラウド基盤などで提携を強化することで、AIZEをより多機能かつ安定的に提供できる体制を整えています。
【理由】
自社だけで全ての技術領域を網羅するのは難しいため、協力関係を結ぶことが事業拡大の近道だからです。AIだけでなく、データ解析プラットフォームやネットワーク、ハードウェアとの連携など、専門外の領域は積極的に外部パートナーの力を借りるほうが効率的です。
こうしたアライアンスの構築によって、顧客に対しワンストップでのソリューション提供が可能になり、導入ハードルを下げることに成功しています。
結果として、トリプルアイズはエンドユーザー企業に対して「何でも相談できる頼もしさ」をアピールでき、案件獲得の幅を広げることができています。
チャンネル
自社営業チームとパートナー企業の両輪でサービスを広めています。
自社営業チームは特に大手企業への提案活動を重点的に行い、パートナー企業は中堅や地域企業へのアプローチを担うなど、役割分担を明確にして市場を網羅しています。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、新規のAI導入は顧客企業にとってハードルが高いケースが多いため、丁寧な導入支援や実績ベースの説得が重要だからです。大手企業はスケールの大きな案件に結びつきやすい反面、複雑な要件に対応する必要があります。
一方、中堅企業や地方の事業者は導入コストやサポート体制を慎重に見極めます。
自社営業チームとパートナー企業が連携することで、多様なニーズに細かく応えられるようになり、その結果、顧客満足度と契約数の両方を伸ばすことができるのです。
顧客との関係
システム開発やAI導入は、プロジェクトベースで契約が結ばれるケースが多いです。
ただしトリプルアイズの場合、プロジェクト完了後も継続的なサポートを提供しているため、長期的な関係を築く顧客が増えています。
運用や保守に加えて、新機能の提案や追加開発を積極的に実施し、顧客のDX促進を後押ししています。
【理由】
AIシステムは一度導入したら終わりではなく、常に改善やバージョンアップが必要だからです。実運用を開始した後に見えてくる課題や、新たに発見されるデータの特徴を踏まえてチューニングを行うことで、顧客の生産性やサービス品質を継続的に高められます。
この取り組みが顧客ロイヤルティを高め、追加の契約や他の事業部門への横展開などにつながり、結果的にトリプルアイズの安定的な収益基盤の拡大に寄与しています。
顧客セグメント
AIソリューションやシステム開発を必要とする企業全般が対象ですが、特に製造業や小売業、医療分野など、画像認識技術が活躍しやすい領域からの引き合いが多いです。
さらに、インフラや物流領域でも需要が高まっているのが現状です。
【理由】
これらの業界は多くの画像データやセンサー情報を扱うため、AIによる効率化や品質向上が期待できるからです。たとえば製造業では外観検査や仕分け作業を自動化することで人為的ミスを削減し、小売業では在庫管理や顧客動線の把握にAIを活用できます。
医療分野でも画像診断の補助などで高い需要が見込まれます。
こうした具体的メリットがわかりやすい業界ほど導入が進みやすく、トリプルアイズとしてはAIZEの導入事例を増やすことで他業種への波及を目指している状況です。
結果的に、幅広い顧客セグメントにアプローチしているものの、まずは画像認識の有用性が特に際立つ業種でのシェア拡大を図っているといえます。
収益の流れ
大きく分けて、システム開発の受注収益と、AIZEのライセンス収入の2本柱になっています。
システム開発案件では、案件ごとの契約金と追加の開発費、保守運用費用が発生し、AIZEでは月額ライセンスや機能追加のオプションフィーなどで安定的なストック収益を形成しています。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、ソフトウェアビジネスで安定した収益を確保するためには、ライセンスモデルの拡充が不可欠だからです。受託開発だけではプロジェクト単位の収益に限られるため、波が大きくなりがちです。
一方、AIZEのようなプラットフォームをサービスとして提供する形にすることで、月額や年額の利用料金を得られ、長期的に会社の基盤が安定しやすくなります。
こうした収益モデルの組み合わせによって、まずは受注開発で顧客との接点を増やし、その後にAIZEへ誘導するというクロスセル戦略も可能になります。
コスト構造
人件費と研究開発費が大きなウェイトを占めています。
優秀なAIエンジニアやデータサイエンティストを採用・育成するためのコスト、そしてAIZEの精度向上に向けた開発投資が欠かせません。
また、営業活動やマーケティングにも一定のコストをかけています。
【理由】
AI関連の事業で勝ち抜くには、高度な専門知識と実務経験を持つ人材の確保が避けては通れないからです。最新技術のリサーチやモデル改善には継続的な投資が必要で、それが利益を圧迫する面もあります。
ただし、こうしたコストを惜しんでしまうと、競合他社との差別化が難しくなり、かえって成長が鈍化するリスクがあります。
そのため同社は、短期的な利益率よりも長期的な成長を見据え、研究開発費を積極的に投下する姿勢を選んでいます。
結果的に売上高は急拡大していますが、営業利益がまだ大きくない要因の一つはこのコスト構造にあるといえます。
自己強化ループ
トリプルアイズの自己強化ループは、AIZEのユーザー数が増加することで収集データが増え、AIモデルの精度が向上し、さらに新規導入が促進されるという好循環にあります。
具体的には、新規の企業がAIZEを導入すると、その企業が持つ独自の画像や業務データが学習素材として蓄積されます。
すると、これまでになかったパターンのデータ解析が可能になり、AIZEの認識性能や予測精度が高まります。
そして、その成果がすでに導入済みの企業にも反映されるため、利用企業は継続的に価値を享受することができ、満足度と導入効果がさらにアップします。
この高精度化が市場での評価を高め、新たな顧客を呼び込み、プラットフォームがより強固になるという循環を生み出すのです。
システムインテグレーション事業の面でも、豊富なプロジェクト実績がノウハウとして蓄積され、新しい開発案件での提案力や問題解決能力が向上します。
結果として、企業からの信頼が厚くなり、追加の案件やリピート受注が発生しやすくなります。
このようにAIプラットフォームとSI事業の両面で、トリプルアイズならではの自己強化サイクルが機能していると考えられます。
採用情報
現時点で初任給や平均休日、採用倍率といった具体的な数値は公表されていません。
ただし、AIエンジニアやシステム開発者の需要が高まるなか、トリプルアイズは積極的に専門人材を募集しているようです。
AI分野は競争が激しく、技術者不足が続く業界といわれているため、自分のスキルを活かしたいエンジニアにとっては魅力的な環境といえます。
また、同社の強みは研究開発にも力を入れている点なので、最新技術に触れながらキャリアを積めることが期待できます。
将来的に上場企業としての安定性も見込まれますので、就職活動の候補として検討する人も増えています。
株式情報
銘柄は証券コード5026で、トリプルアイズとして上場しています。
2024年8月期の配当は実施されておらず、利益を成長分野への投資に充てている姿勢がうかがえます。
1株当たりの株価は2025年2月3日時点で1,155円となっており、AI分野への期待感なども相まって変動が激しい可能性があるため、投資を検討する場合は最新のIR資料や株価情報を確認することが大切です。
配当を重視する投資家というよりも、成長性やAI関連銘柄としての将来性を評価して購入する投資家が多い印象があります。
未来展望と注目ポイント
今後はAIZEのさらなる性能向上と市場認知度アップが、トリプルアイズの成長を左右しそうです。
まず、競合が増えているAIプラットフォーム市場では、単なる画像認識能力の高さだけでなく、カスタマイズ性や導入後のサポート体制が重要視されます。
同社はシステムインテグレーション事業と連携しながら、顧客ごとの要望に柔軟に対応できる点を強みにしていますが、それをより多くの企業に知ってもらうためのマーケティング活動が欠かせません。
また、AIZEで蓄積される学習データが増えるほど、業務フロー全体の自動化や新しいサービス開発も期待できるでしょう。
たとえば、店舗の棚卸を自動化する機能や、防犯カメラの映像をリアルタイムで解析して異常を検知する仕組みなど、実用的なソリューションが増えてくると見られます。
それによって、さらなる業界横断的な導入事例が増え、企業間の口コミや成功事例の拡散によるシナジー効果が高まるのではないでしょうか。
株式市場の視点からすれば、売上が急成長しているものの利益面がまだ控えめな状況がどう変化していくかが注目ポイントですし、研究開発や人材投資から生み出される成果が今後の収益をどれだけ底上げしていくのか、その成長ストーリーが順調に進むかどうかを注視している投資家は多いはずです。
したがって、トリプルアイズは今後もビジネスモデルを磨きながら、AI領域で独自の地位を確立していく可能性が十分にあると考えられます。

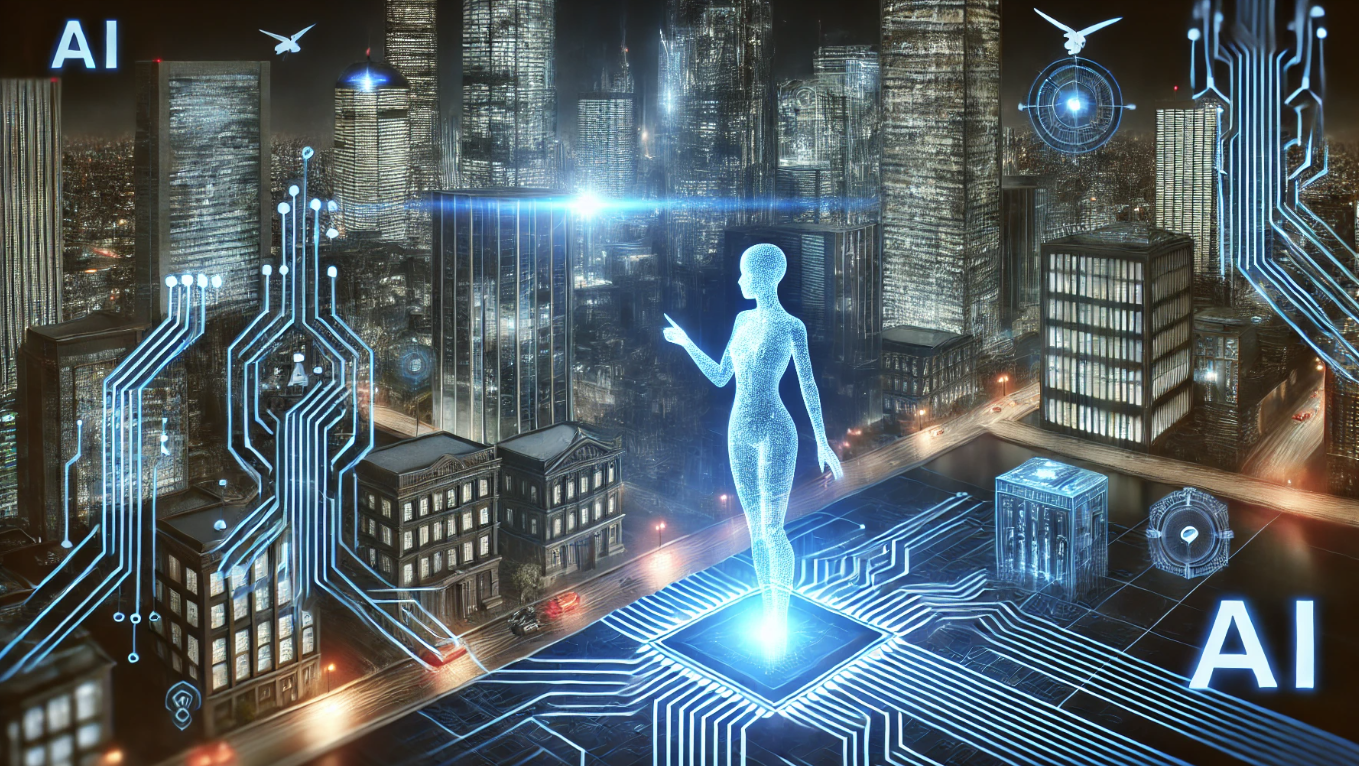


コメント