企業概要と最近の業績
加賀電子株式会社
当社は、電子部品や半導体などを扱う独立系のエレクトロニクス商社です。
国内外の幅広いメーカーの電子デバイスを顧客に販売する「電子部品事業」を中核としています。
その他にも、顧客の要望に応じて電子機器の設計から製造までを請け負うEMS事業や、パソコン・周辺機器などを販売する情報機器事業、アミューズメント機器の企画開発など、多角的な事業を展開しています。
最新の2026年3月期第1四半期決算によりますと、売上高は前年の同じ時期と比較して2.8%減の1,440億40百万円でした。
営業利益は31.8%減の71億26百万円、経常利益は28.5%減の77億62百万円となっています。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、25.9%減の63億10百万円となり、減収減益での着地となりました。
車載向けや産業機器向けの半導体・電子部品の需要が減少したことが主な要因です。
【参考文献】https://www.taxan.co.jp/
価値提案
加賀電子株式会社の価値提案は、多様な電子部品を必要とする企業や教育機関に対し、幅広い商材をワンストップで提供できる点にあります。
さらに受託製造サービス(EMS)も行うことで、単なる部品調達にとどまらず、製品設計や品質管理などの付加価値をプラスしています。
【理由】
こうした形態はなぜ生まれたかというと、産業機器や車載市場が急速に高度化し、複雑な電子部品を安定して供給できるパートナーが求められるようになったからです。
また、教育機関向けにはパソコンや周辺機器をまとめて導入するニーズが高まっており、IT化やセキュリティ面のサポートを含めたトータル提案を実現することが差別化要因として評価されています。
その結果、多角的なサービスが「安心して頼れる企業」というイメージを確立し、長期的な取引を生み出す仕組みになっています。
主要活動
この企業の主要活動は、部品の調達・販売から受託製造、そして情報機器の販売に至るまで多岐にわたります。
電子部品事業では、グローバルで調達した半導体やコンデンサといった製品を産業機器・車載関連メーカーへ供給します。
EMS事業では、設計から製造・検査・出荷まで一括で行うため、顧客企業の負担を減らすことが可能です。
さらに情報機器事業では、教育機関向けパソコンの販売網を維持しながら、セキュリティソフトや周辺機器も含めたトータルソリューションを提供しています。
【理由】
なぜこうなったかというと、顧客のニーズが「製品の調達だけでなく、ものづくりの一連の流れを任せられるパートナー」「教育現場に最適化したIT導入サポート」を求めていたからです。
あらゆるステップでサポートできるように事業領域を拡大することで、安定的に付加価値を創出できるビジネスモデルを築いています。
リソース
同社のリソースとして挙げられるのが、グローバルに展開された調達ネットワーク、高い技術を持つ製造拠点、そして専門知識を持つ技術者の存在です。
世界各地にある部品メーカーや現地生産拠点と結びつくことで、価格交渉力と安定供給力を兼ね備えています。
また、EMS事業においては高度な品質管理や量産設計技術が求められるため、経験豊富なエンジニアが大きな武器となっています。
【理由】
なぜこのようにリソースを集められたかというと、同社が長年にわたり電子部品流通に携わってきたことで培われたネットワークと、国内外にわたる顧客企業からの信頼が背景にあるからです。
こうしたリソースは競合他社が簡単には真似できないため、大きな強みとしてビジネスを支えています。
パートナー
加賀電子株式会社が連携しているパートナーには、電子部品メーカー、物流企業、さらに教育機関などが含まれます。
電子部品メーカーとの強固な関係によって、最新の半導体やコンポーネントをいち早く確保できるのがメリットです。
物流企業との連携は、国内外へのスムーズな配送や在庫管理を実現し、顧客企業への納期を遵守するために欠かせません。
教育機関とのパートナーシップは、現場のニーズに合わせたパソコンやソフトウェアを最適に導入するノウハウを得るきっかけにもなっています。
【理由】
なぜこうした多彩なパートナーが必要かというと、同社がカバーする事業領域は幅広く、それぞれの分野で専門性やネットワークを活用しなければ競争力を保てないからです。
結果的に、豊富なパートナーとの協業が、付加価値の高いサービスとビジネス拡大を可能にしています。
チャンネル
加賀電子株式会社は顧客への販売チャンネルとして、直販、代理店、オンラインの3つを中心に展開しています。
大手企業や教育機関など規模の大きい取引先には直販ルートを活用し、きめ細かいサポートやカスタマイズを提供しています。
一方で、代理店網を活用することで中小規模の企業にも製品やサービスを届けやすくしており、多様な業界からの需要を獲得する仕組みを作っています。
また、オンラインチャネルは地域や時間に縛られない販路として活用され、特に教育機関向けではオンライン学習製品やサポートサービスの案内にも役立っています。
【理由】
なぜこれらの複数チャンネルを使い分けるかというと、顧客が求めるサービスレベルや予算がそれぞれ異なるからです。
複数の販売ルートを整備することで取りこぼしなく需要を取り込み、安定的な収益を得られるようになっています。
顧客との関係
この企業では、長期的な取引やカスタマーサポートを重視する姿勢が顕著です。
特に産業機器や車載向けの顧客は、長期にわたって部品供給を必要とするため、信頼関係を構築することが売上維持に直結します。
教育機関向けでも、パソコンやセキュリティ対策など継続的なサポートが必要となる場面が多く、導入後もアフターサービスをしっかり提供しています。
【理由】
なぜここまで丁寧な顧客関係を築くかというと、一度契約した顧客がリピーターとなる確率が高く、定期的な更新や追加購入が発生しやすいためです。
さらに、IR資料などで公表される安定的な取引実績は投資家からの信頼にもつながります。
こうした長期的視点の顧客対応が、ビジネス全体を支える大きな柱です。
顧客セグメント
同社の顧客セグメントとして代表的なのは、産業機器メーカーや車載機器メーカー、そして教育機関です。
産業・車載分野は高付加価値の部品やEMSサービスが求められるため、同社の技術力や調達力が評価されています。
教育機関では、パソコンやソフトウェアだけでなく、ICT化を総合的に支援するサービスが重宝されています。
【理由】
なぜこれらの顧客セグメントに注力しているかというと、少子化が進む中でも教育現場のデジタル化は国策として進められ、安定した需要が期待できるからです。
また、産業用・車載用の電子部品は景気に左右されにくい長期的プロジェクトが多く、継続的な売上を見込むことができます。
このように選定した顧客セグメントが、多様な事業展開を支える大きな要因となっています。
収益の流れ
収益の流れは大きく分けて、電子部品の販売収入とEMS事業による受託製造サービスの収入に加え、情報機器事業からの収入があります。
産業機器や車載向けの部品販売は、長期契約や安定納入によって定常的な売上を生み出します。
EMS事業では顧客企業の製品を大量に生産するため、受注が増えれば比例して収益が拡大しやすい特長があります。
情報機器事業でも、パソコンやソフトウェア販売に加え、保守サービスや追加ライセンスで安定的な収入を得られます。
【理由】
なぜ複数の収益源を持つかというと、市場の需要変動や為替リスクを一つの事業に頼らず分散するためです。
こうした収益構造は景気が変動する局面でも柔軟に対応できる仕組みとなっており、成長戦略を描きやすい体制を整えています。
コスト構造
コスト構造は主に製品調達コスト、製造コスト、物流コストで構成されています。
製品調達コストは、電子部品を仕入れる際の原価が大きく、為替レートの影響も受けやすいため、グローバルに最適な調達先を選ぶ必要があります。
EMS事業では生産ラインの維持費や品質管理に関連するコストが大きいものの、効率化に成功すれば大きな利益を生み出す余地があります。
物流コストは在庫管理と輸送経路の最適化が課題となり、需要予測や顧客への納期対応力が鍵を握ります。
【理由】
なぜこれらのコストを適切に管理するのが重要かというと、競合他社も価格競争を強めている中で、コスト削減と付加価値の提供を両立させないと利益が確保しにくいからです。
このように、多方面からコストを管理する仕組みが、安定した経営に結びついています。
自己強化ループ
加賀電子株式会社が強みを発揮できるのは、多様な事業展開と顧客との長期的な関係が相互に良い影響を及ぼす自己強化ループを構築しているからです。
電子部品の販売で得た実績が信用を高め、EMSや情報機器事業への追加発注につながるケースが少なくありません。
さらに、教育機関向けの実績が拡大すると、学校や自治体からの信頼が厚くなり、関連するセキュリティソフトや周辺機器の需要も高まります。
こうした事業間のシナジーによって売上が増加し、さらに調達ネットワークが強化されることでコスト競争力も高まり、顧客の満足度が上がってリピート受注へとつながります。
このサイクルが回るほど業績や知名度が向上し、新たな成長戦略を打ち出すための資金や技術への投資も拡充できます。
結果として、次の段階のイノベーションやさらなる市場拡大を可能にする好循環が形成されているのです。
採用情報
現在は初任給や平均休日、採用倍率などの具体的な情報は公表されていませんが、電子部品の専門知識やEMSの技術力を活かした総合力が求められる企業として、技術職・営業職ともにやりがいのある環境が整っていると考えられます。
特に教育機関への導入支援や最先端の産業機器分野への部品供給など、多彩な業種とのやり取りができる点は、働く上での魅力と言えるでしょう。
就職情報サイトや同社の採用ページを確認すると、詳細な業務内容や求める人材像について理解が深まるはずです。
株式情報
証券コードは8154で、1株当たりの株価は2025年2月21日時点で2654円です。
配当金に関しては公開されていませんが、今後の成長戦略やIR資料をチェックすることで、投資家がどの程度のリターンを期待できるかを見極めることができます。
複数の事業ドメインを持ち、リスク分散が図られている点が投資家からも評価されるポイントかもしれません。
市場環境や業績次第で変動が予想されますので、株価の動向を継続的にウォッチしていくと良いでしょう。
未来展望と注目ポイント
加賀電子株式会社は、産業機器や車載関連のみならず、教育現場のICT化にも力を入れており、今後も継続的な需要が見込める分野での成長が期待されています。
さらに、幅広い顧客基盤を通じて蓄積されたノウハウを活かし、新たなビジネスモデルの開発や海外市場へのさらなる展開も視野に入れていると考えられます。
特にEMS事業では、高度化する技術とコスト競争の両立が鍵となるため、グローバル規模での効率的な生産体制づくりが進むでしょう。
教育機関向けソリューションも引き続き拡張が見込まれ、周辺機器やセキュリティ領域などでの付加価値提供が重要な役割を果たしそうです。
こうした多角的な事業展開を着実に支える収益構造があれば、景気変動や市場競争にも柔軟に対応できるはずです。
今後のIR資料や決算発表を通じて、どのような方針で投資や戦略を進めていくのか、一層注目が集まっています。

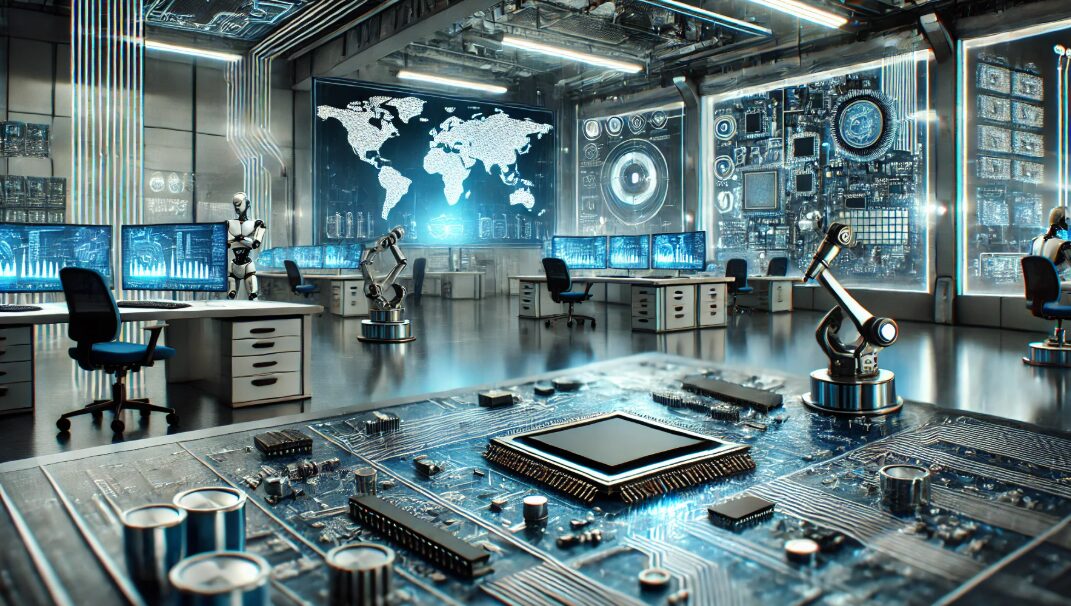


コメント