企業概要と最近の業績
株式会社学研ホールディングス
「教育」と「医療福祉」を事業の二本柱とする持株会社です。
教育分野では、学習参考書や図鑑の出版、学習塾「学研教室」や進学塾の運営、オンライン学習サービスの提供などを手掛けています。
医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅や認知症グループホームの運営、保育園などの子育て支援施設の運営などを行っています。
2025年8月13日に発表された2025年9月期第3四半期の連結決算によりますと、売上高は1,205億3,000万円で、前年の同じ時期に比べて5.8%増加しました。
営業利益は50億8,000万円で、前年の同じ時期から10.2%の増加となりました。
経常利益は51億2,000万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は30億1,000万円となり、増収増益を達成しています。
医療福祉分野において、主力の高齢者向け住宅事業で既存施設の入居率が高水準で推移したことに加え、教育分野でも学習塾の生徒数が順調に増加したことが業績を牽引しました。
価値提案
学研ホールディングスが提供する最大の価値は、質の高い学びや知識、さらに安心して暮らせる福祉サービスを幅広い世代に届けることです。
子ども向けの教材開発や学習塾運営から、高齢者向けの介護・福祉サービスまで、人生の異なるステージをサポートしています。
【理由】
なぜそうなったのかという背景としては、長い歴史のなかで教育分野に強みを築き、そこから派生して出版や福祉へと事業領域を拡大してきた経緯があります。
教育の専門知識をベースにしながら、少子高齢化という社会変化に合わせて事業を展開したことで、学研ホールディングスならではの総合的な価値提案が実現しました。
事業間で得られる知見やリソースを活かして、顧客に新たな価値を継続的に提供できる体制を整えています。
主要活動
同社の主要活動には、教材や書籍などのコンテンツ企画・編集、学習塾運営、介護施設の運営などが含まれます。
出版物の制作から現場のサービス提供まで手がけることで、多様なノウハウと実行力を蓄積しています。
【理由】
なぜそうなったのかという理由としては、紙媒体やデジタル教材など多角的なコンテンツを扱ってきた歴史と、介護施設への進出に代表されるような事業拡大の柔軟性が挙げられます。
社会のニーズに応えながら主要活動を幅広く展開することで、事業リスクを分散しつつ成長の機会を増やしているのです。
リソース
学研ホールディングスのリソースとしては、豊富な教育・出版関連のコンテンツ、高度な専門性を有する人材、長年のブランド力などが挙げられます。
さらに、全国に展開している学習塾や福祉施設のインフラも大きな強みです。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、学校教育の現場や家庭向け教材などを長く手がけてきたことがリソースの蓄積につながったと言えます。
出版事業で得た編集力やノウハウが、教育コンテンツの開発や福祉分野のマニュアル整備などにも活かされ、結果として総合力を高めているのです。
パートナー
同社は教育機関や自治体、他の出版社やIT企業などと連携しながら事業を進めています。
特に学校や自治体との協力で学習プログラムを共同開発したり、地域の福祉施設と協力して介護サービスを拡充したりするケースも多いです。
【理由】
なぜそうなったのかは、社会の多様なニーズに応えるには単独では難しく、協業が効果的だからです。
学研ホールディングスは長年の信頼と実績をもとに、パートナーと相互にメリットをもたらす関係を築き、事業の幅を広げています。
チャンネル
主なチャンネルとしては、書店やオンライン書店、学習塾の教室、介護施設などが挙げられます。
さらに、自社サイトやデジタルコンテンツのプラットフォームを通じて情報発信やサービス提供を行っています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、紙媒体だけでなくデジタル化が進む現代において、多様な接点を持つことが必要とされているからです。
学研ホールディングスは従来のリアルな販売網に加え、オンラインでも信頼できるチャンネルを強化することで、より多くの顧客にアプローチしていると考えられます。
顧客との関係
同社は教育や福祉の領域で、利用者と長期的な関係を築くことが特徴です。
学習塾に通う生徒やその保護者、介護サービスを受ける高齢者とのコミュニケーションを密に行い、ライフステージに応じた継続的なサポートを提供しています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、教育や介護の現場では安心感や信頼感が重視されるからです。
長期的な付き合いが求められる分野だけに、学研ホールディングスは質の高いサービスと細やかなフォローで顧客満足度を高めています。
顧客セグメント
学研ホールディングスの顧客セグメントは、未就学児から学生、保護者、教育者、高齢者まで幅広くなっています。
また、一般の書籍や雑誌を楽しむ読者層も重要な顧客として位置づけられます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、教育事業の長年の蓄積によって子どもや保護者に強いアプローチができ、さらに高齢化に伴う介護ニーズにも対応することで、人生のどのステージでもサービスを提供できる企業へと進化してきたためです。
収益の流れ
収益の主な流れは、学習塾や福祉施設利用者からのサービス利用料、出版物の販売やデジタルコンテンツの販売収益などが中心です。
教材のライセンスや法人向けの契約から得られる収入も含まれます。
【理由】
なぜそうなったのかは、出版と教育というコアの収益源に加え、高齢化社会への対応として福祉事業が拡大し、収益の柱が増えたためです。
複数の収益源を持つことで、景気変動や時代の変化に強い体制が築かれています。
コスト構造
コストとしては、人件費や開発費、施設の維持管理費が大きな割合を占めます。
また、書籍や教材の制作には編集・印刷などの費用、福祉施設の運営には介護人材の教育コストなどが必要です。
【理由】
なぜそうなったのかを振り返ると、教育や福祉は人手が欠かせない分野であり、専門性を持ったスタッフの確保が不可欠だからです。
紙媒体からデジタルへシフトする流れもあり、システムやITへの投資コストもかさむ一方で、効率的な運営で利益を確保しています。
自己強化ループのポイント
学研ホールディングスは教育、出版、福祉という3つの分野がお互いに影響し合うことで、自己強化ループを生み出しています。
まず、出版事業で培った編集力やコンテンツの制作技術が、学習塾や福祉現場で活きることがあります。
教育事業で得た顧客のフィードバックが、新しい教材開発に役立つことも多いです。
また、福祉分野においては介護の専門知識や施設の運営ノウハウが確立されると、それが教育分野の健康や福祉に関する教材作成に転用でき、より多角的な内容を提供できるようになります。
こうして、各事業の成功が別の事業にプラスの影響を与え、結果的に全体のブランド力や収益性を高める循環が生まれていることが大きな特徴です。
採用情報
学研ホールディングスでは幅広い職種で人材を募集しています。
初任給については公表されていませんが、業界水準に照らして検討されることが一般的です。
休日数は年間120日程度で、ワークライフバランスにも配慮されています。
採用倍率は非公表ですが、多様な大学や学部出身者の採用実績があるため、多角的に活躍できるフィールドがあると考えられます。
株式情報
銘柄コードは9470で、2025年2月28日時点の株価は1,082円となっています。
配当金は1株あたり22円が予定されており、安定した配当を行う企業としても注目されることが多いです。
投資家からは今後の事業拡大や成長戦略の進捗が注目され、IR資料などが公開されるタイミングで株価に影響が出る場合があります。
未来展望と注目ポイント
学研ホールディングスは少子高齢化が加速する中で、教育事業と福祉事業を両輪とした展開をますます強化していくと考えられます。
教育分野ではデジタル教材やオンライン学習の需要拡大が見込まれ、出版事業とのシナジーを活かした新たなサービス開発が期待されています。
福祉分野では、高齢者向け住宅や介護施設を地域と連携させることで、よりきめ細かなケアの提供が可能になるでしょう。
さらに、デジタルコンテンツの開発力を高めることで、出版市場の変化に対応しながら新しい収益機会を創出できると予想されます。
こうした領域の拡張やサービスの質の向上は、自己強化ループを通じてさらに学研ホールディングスの競争力を高めると考えられます。
教育や福祉の現場と密接にかかわる企業だからこそ、今後も社会的なニーズに合わせて柔軟に成長していく可能性が高いといえます。
ビジネスモデルの多角化やIR資料で示される方向性に注目していくことで、これからの展開がますます楽しみになるでしょう。

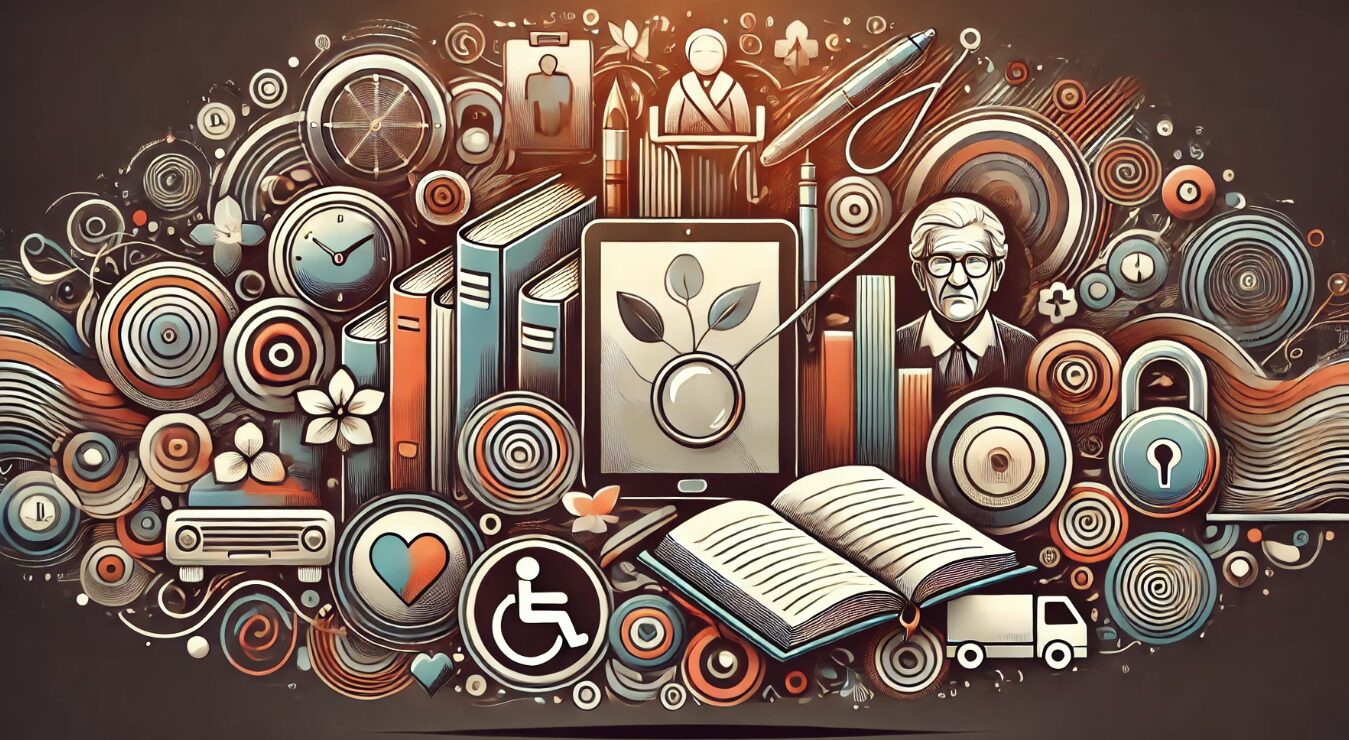


コメント