企業概要と最近の業績
株式会社いよぎんホールディングス
いよぎんホールディングスは、愛媛県に本店を置く伊予銀行を中核とした金融持株会社です。
2022年10月に設立され、グループ全体の経営管理やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、新規事業開発などを担っています。
グループ傘下には、伊予銀行のほか、証券、リース、クレジットカード、コンサルティングなどの専門機能を持つ会社を有しています。
これらのグループ会社が一体となり、預金や融資といった伝統的な銀行業務にとどまらない、総合的な金融サービスを地域社会に提供しています。
2026年3月期第1四半期の連結業績は、経常収益が455億25百万円(前年同期比14.5%増)、経常利益が131億47百万円(同14.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は92億48百万円(同15.3%増)となり、増収増益でした。
これは、貸出金利息収入や有価証券の利息配当金が順調に増加したことに加え、法人向けコンサルティングやビジネスマッチングの手数料収入が好調だったことによるものです。
中核である伊予銀行の預金残高は8兆5,248億円、貸出金残高も6兆9,114億円と、ともに順調に増加しています。
価値提案
いよぎんホールディングスは地域経済を支える金融インフラとして、四国を中心に総合的なサービスを提供しています。
個人から法人まで幅広い顧客に対して預金や融資だけでなく、証券業務やリース業務なども含めた多角的なサポートを行う点が大きな特徴です。
地域に根ざすことで、顧客のライフステージやビジネスフェーズに合わせた金融ソリューションを提案する柔軟性に長けています。
こうした価値提案が生まれた背景には、地元に密着しなければお客さまのニーズを逃さず的確に捉えることは難しいという考えがあるためです。
また、外貨債券運用の実績を活かし、資産運用に強みを持つ地域の銀行グループとしてブランド力を高めることを目指しています。
これによって、より多くの投資や融資機会を地元に提供し、地域経済の発展を後押ししようとする姿勢が確立されました。
【理由】
なぜそうなったのかといえば、都市部の大手銀行に対抗するには地元への強いコミットメントと差別化が必要だったからです。
その結果、地域の企業や個人から「頼れる銀行グループ」という評価を得ることに成功し、継続的に業績を伸ばしています。
主要活動
銀行業務をはじめ、リース業務や保証業務、証券業務など、多岐にわたる金融サービスを展開していることが特長です。
たとえば企業向けには融資サービスだけでなく、事業拡大に伴う設備投資や資金繰りの提案、経営支援サービスを行います。
個人向けには住宅ローンや預金、資産運用など、ライフサイクルに応じた細やかな商品を取りそろえています。
さらに、オンラインバンキングやモバイルアプリの機能強化にも積極的で、地域の住民がより便利に銀行サービスを利用できる環境を整えています。
こうした多彩な活動の背景には、地域における金融ニーズを一手に引き受けることで、銀行グループとしての存在感と顧客満足度を高めたいという戦略があります。
【理由】
なぜそうなったのかといえば、単純に預金と融資だけでは競合他行との違いを出しにくいため、幅広い金融業務を提供することで、顧客のさまざまなニーズに応えられる体制を整えてきた結果です。
リソース
最大のリソースは伊予銀行を中心とする専門知識とネットワークです。
長年の営業活動を通じて培われた地域密着のノウハウや、外貨債券運用で培われた投資判断力が強みとして挙げられます。
また、地元企業や自治体との人脈を築き上げてきたことで、地域内の経済動向やビジネスチャンスを的確に把握することが可能です。
さらに、店舗網の広さやオンラインプラットフォームの活用もリソースの一部として重要視されており、多様な顧客にアクセスできるチャネルを保有しています。
【理由】
なぜこうしたリソースを充実させるに至ったのかというと、地域銀行としての責務を果たしながら収益を確保するには、地元市場の情報をどれだけ正確かつ迅速に掴めるかが勝負になるからです。
投資運用や融資判断でも地域の動向を理解しているからこそ的確にリスクをコントロールでき、それが安定した業績と信頼獲得につながっています。
パートナー
地元企業や自治体との連携を大切にしている点が大きな特徴です。
伊予銀行が地元の企業活動を支援してきた歴史があるため、取引先とのつながりが強固です。
また、他の金融機関との協働によって商品開発やサービス向上に取り組む場面も増えています。
たとえば地域の産業活性化に向けた共同プロジェクトに参画したり、ベンチャー企業との業務提携を進めたりして、新たなビジネス機会を創出しています。
こうしたパートナー関係が重要視されるのは、単独では難しい顧客ニーズに応えるために外部のリソースを活用する必要があるからです。
【理由】
なぜそのような協力体制が生まれたのかといえば、地域に根ざした銀行として「地域全体を盛り上げること」こそが自社の持続的な成長に直結すると考えているからです。
そのため、オープンイノベーションの推進や共創の場を積極的に広げ、地域社会と共に成長していく姿勢を貫いています。
チャンネル
店舗網とオンラインバンキング、モバイルアプリの三つを大きな柱として展開しています。
店舗ではきめ細かい対面サービスを提供し、高齢者やインターネットに不慣れな方にも安心して利用できる環境を整えています。
一方で、若年層やビジネスパーソンにはオンラインバンキングやモバイルアプリを通じて24時間いつでも手軽に取引できる利便性を提供しています。
このように、顧客の属性やライフスタイルに合わせて複数のチャンネルを整備し、幅広い層をカバーする戦略を取っているのです。
【理由】
なぜこれが必要なのかというと、地域銀行であってもデジタル化の潮流は避けられず、対面だけに頼っていては顧客満足度を維持しづらいという課題があるからです。
そのため、伝統的な店舗サービスと先進的なデジタルツールを組み合わせることで、多様な顧客ニーズに柔軟に対応しています。
顧客との関係
いよぎんホールディングスは地元密着の姿勢を重視しており、長期的な信頼関係を育むことを目指しています。
店舗に足を運びやすい雰囲気づくりや、担当者が直接足を運んで細かい相談に乗るスタイルなど、「顔が見える銀行」としてのブランドを大切にしています。
また、オンラインチャネルでも顧客対応の迅速化やスムーズなUX設計に力を入れており、時代に合ったコミュニケーションを提供しています。
こうした方針を採用しているのは、金融サービスが人々の生活や企業活動に深く根ざしているからこそ、安心感や信頼感が非常に重要になるからです。
【理由】
なぜそうした姿勢を保ってきたのかといえば、地元での長い歴史の中で培われた評判を守り、顧客に「選ばれ続ける」銀行グループとなるためには、継続的に誠実な対応を積み重ねる必要があると考えているからです。
顧客セグメント
主に四国地方を中心とした個人と法人がメイン顧客です。
個人の中には、年配の方から若い世代まで幅広く含まれており、住宅ローンや教育資金、老後の資産運用などライフステージ別のニーズに応える商品を提供しています。
また、法人では中小企業から大手企業まで、地域の産業を支える幅広いセクターをカバーしています。
農業や観光業など、その地域特有の産業を支援する取り組みも重視されています。
こうした顧客セグメントの形成には、四国という地域の特性が大きく関係しています。
【理由】
なぜそうなったかといえば、東京や大阪といった大都市圏に比べて企業規模が小さいケースが多いため、地元の銀行が広くサポートしなければ地域経済全体が成長しづらいという現実があるからです。
結果として、個人も法人も含めた地域のあらゆる層に密着することが必須となり、多彩な商品・サービス展開が進みました。
収益の流れ
金融グループとしての基本は利息収入と手数料収入ですが、いよぎんホールディングスの場合は外貨債券の投資運用も主要な収益源の一つです。
海外の市場金利や為替相場を見極め、円ヘッジなしで投資する運用スタイルが功を奏しており、比較的高いリターンを得やすい構造になっています。
一方、地域企業への融資においては、保証料やリース料といった形でも収益を確保しつつ、地域経済を下支えする役割を担っています。
【理由】
なぜこうした収益構造になったのかといえば、低金利時代が長期化する中、従来の国内融資や預金金利だけでは銀行グループとしての収益を伸ばしにくかったという事情があります。
そのため、積極的な外債投資や多角的な金融サービスへの拡張を図ることで、利息依存度を下げつつ安定した収益基盤を築き上げています。
コスト構造
大きなウエイトを占めるのは人件費や店舗運営費、システム維持費などです。
地域密着の銀行として、ある程度の店舗数や人員を確保しておかないと顧客満足度を保てないので、固定費がかさみやすい面があります。
一方、デジタル化の推進によって取引のオンライン化を進めることで、将来的には店舗コストや人員コストを最適化しようという動きも見られます。
【理由】
なぜ固定費負担が大きい構造になっているのかというと、地方銀行は地元の利用者が対面での相談を好む傾向が強いという要因や、地域全体の利便性向上のために店舗網を維持する必要があるからです。
それでも、オンラインバンキングの活用や事務手続きを効率化するテクノロジーの導入により、一定のコスト削減効果を期待しており、今後はデジタル面への投資が一層進むと考えられています。
自己強化ループ
いよぎんホールディングスが注目されている理由の一つに、外貨債券運用で得た収益を再投資し、さらに収益を拡大させる自己強化ループがあります。
外債運用によって高いリターンを確保すると、それがグループの資本力や投資余力を強化し、新しいプロジェクトや地域連携への投資を可能にします。
たとえば地元企業への融資枠拡大やデジタルシステムの更新などに充てることで、さらに競争力が高まり、収益基盤が安定していくのです。
こうして生まれた余裕資金をまた海外投資に回すことで、うまくタイミングを掴めばさらなるリターンが期待でき、収益の好循環が続きやすくなります。
この一連の流れが「好業績→投資余力拡大→さらに有利な投資→再び好業績」という形で繰り返されるので、持続的な成長が見込まれるのです。
地域密着型の銀行グループは国内需要に依存しがちという課題を抱えていますが、外貨投資というグローバルな視点を取り入れることで、リスク分散と収益拡大を同時に実現している点が大きな強みです。
採用情報
現時点で初任給や平均休日、採用倍率などは公式に公表されていません。
ただし、四国地方の銀行グループとしては比較的人員が充実しており、新卒採用では地域に根ざして働きたい学生から人気を集める傾向があります。
金融知識を身につけたい人や、地元企業を盛り上げたいという熱意のある方には、有力な就職先の一つとして検討されやすい存在です。
最新の情報に関しては公式の採用ページを確認し、自分が興味のある業務内容をチェックすると良いでしょう。
株式情報
銘柄コードは5830で、配当金は2024年3月期が年間30円、2025年3月期は年間40円(中間20円、期末20円)になる予定です。
1株当たり株価は2025年2月21日時点で1,631円となっており、地方銀行の中でも安定した配当利回りが魅力の一つとされています。
投資家から見れば、低金利の時代に配当が期待できる銘柄として注目されやすい存在です。
投資を検討する際には、外貨運用の成果や地域経済の動向なども合わせて考慮すると、より戦略的な判断ができるでしょう。
未来展望と注目ポイント
今後、いよぎんホールディングスは、四国という地域にとどまらず、さらなる成長戦略を描こうとしています。
地域を超えた投資機会の探索や、オンラインサービスの拡充によって新規顧客を獲得する可能性があります。
また、外貨債券運用のノウハウを活かし、金利が変動しやすい国際マーケットでも収益を確保し続けられるかが今後のカギになりそうです。
加えて、地域企業や自治体との連携プロジェクトにより、地方創生の担い手としての役割を果たすことで地元からの信頼をさらに強固にする狙いもあります。
銀行業界はデジタル化や異業種参入が進む中、金融ビジネスの多様化が加速していますが、いよぎんホールディングスはこの変化をポジティブに捉え、自社のビジネスモデルと地域密着の強みを掛け合わせながら新たなサービスを展開していくと考えられます。
高い収益力と地域への貢献を両立し続けることで、地元経済をけん引する存在としての地位をより一層確立していくことが期待されます。

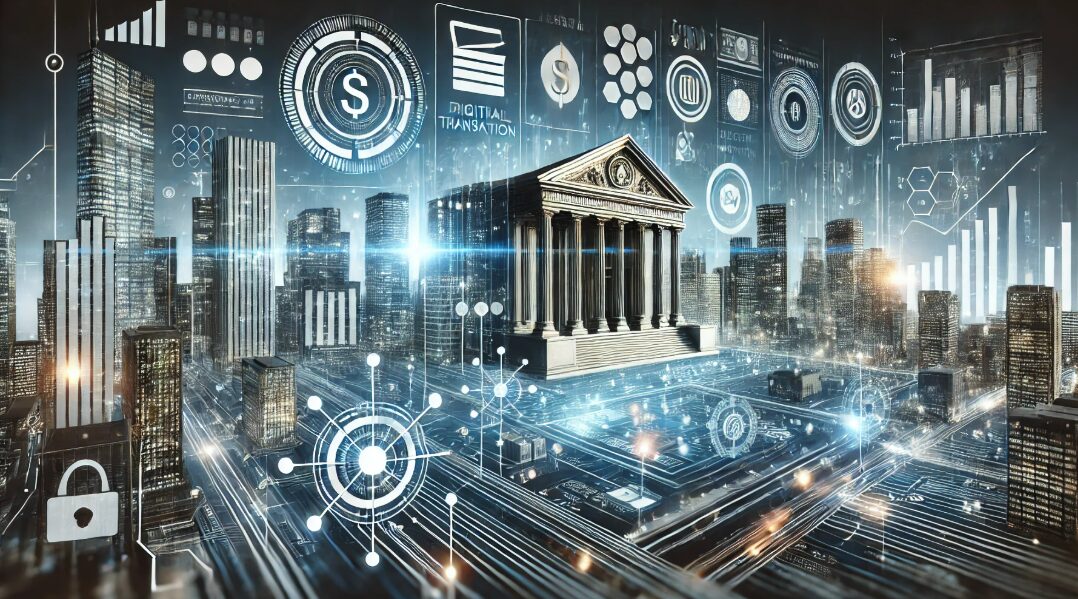


コメント