企業概要と最近の業績
曙ブレーキ工業株式会社
曙ブレーキ工業は、自動車や鉄道車両など、様々な乗りものの「止まる」を支えるブレーキ専門のメーカーです。
乗用車やオートバイはもちろん、日本の新幹線にも同社のブレーキが採用されていることで知られています。
ブレーキパッドやディスクブレーキといった基幹部品の開発から製造・販売までを一貫して手がけています。
現在は事業再生計画のもと、収益性の改善に取り組んでいるグローバル企業です。
2025年8月8日に発表された2026年3月期第1四半期の連結決算によりますと、売上高は434億7,100万円となり、前年の同じ時期と比較して7.0%増加しました。
これは、自動車メーカーの生産回復や円安などが主な要因です。
利益面では、事業再生計画に沿った価格の適正化や経費削減の効果が大きく現れました。
その結果、営業利益は16億700万円となり、前年の同じ時期の7億700万円の赤字から黒字へと大きく転換しました。
経常利益、および親会社の株主に帰属する四半期純利益も、それぞれ黒字に転換しています。
価値提案
曙ブレーキ工業は高品質で信頼性の高いブレーキシステムを提供することを大切にしています。
ブレーキは乗員の安全や快適性に直接関わる部品なので、たとえ価格が多少高くなっても、確かな性能を求める自動車メーカーが多いです。
高い耐久性や熱への強さなど、厳しい環境下でも安定して動作する技術力が価値の核となっています。
これにより、自動車メーカー側は顧客満足度向上やリコールリスクの低減が期待できるため、信頼できるパートナーを求める傾向が続いています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、車の安全機能がますます重視される現代において、ブレーキの品質や信頼性が車種選びの基準になるケースが増えているからです。
また、独立系であることから複数メーカーへ対応しやすく、多様なニーズを満たすための高性能商品が求められてきました。
そうした顧客の期待に応えることで同社は信頼を積み上げ、価値提案の軸を確立しているのです。
主要活動
同社の主要活動には、ブレーキ技術の研究開発、生産、販売、アフターサービスが含まれます。
研究開発では摩擦素材の改良や軽量化技術に力を入れ、環境規制や安全基準の強化への対応を進めています。
生産面では国内外に複数の拠点を構え、需要変動や為替リスクに対応しながら効率的なオペレーションを行っています。
販売面では、自動車メーカー向けの安定供給に加え、補修部品市場への対応も欠かせません。
【理由】
なぜそうなったのかというと、ブレーキという重要部品は車両が走っている間ずっと使用されるため、摩耗や交換需要が一定数見込まれます。
アフターサービスを含めたサポートまで手掛けることで顧客との長い取引関係を築き、売上の安定化を図っているのです。
リソース
曙ブレーキ工業の大きなリソースは、長年培ってきた高度なブレーキ技術と生産ノウハウ、そして世界各地に構える拠点と人材です。
ブレーキ開発には摩擦素材の調整や温度管理といった専門知識が欠かせませんが、独自の研究チームが蓄積したデータを活かすことで、高品質な製品を継続的に生み出せる体制を築いています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、安全部品であるブレーキは性能や信頼性に妥協できないことから、長い年月をかけて蓄積される研究成果や熟練したエンジニアが不可欠だったからです。
その結果、国内外で厳しい品質基準をクリアするブレーキを生み出し、多様な車種やメーカーに対応できる豊富なバリエーションも確保しています。
パートナー
同社のパートナーにはトヨタ、日産、ホンダなどの国内大手メーカーをはじめ、欧米の自動車メーカーや部品サプライヤーが含まれます。
協力関係を築くことで、ブレーキシステム開発の段階から情報共有が可能になり、車両特性に最適化された部品を供給できるのが強みです。
【理由】
なぜそうなったのかというと、ブレーキシステムは車両の設計段階で安全基準や性能要件を細かく検討する必要があるため、メーカーと密に協力することが非常に重要だからです。
さらに研究機関とも連携して新技術の開発を進めることで、環境性能や安全性能を向上させるノウハウを蓄積してきました。
チャンネル
曙ブレーキ工業が製品を届けるルートには、自動車メーカーへの直接販売、代理店ネットワークを通じた販売、そして近年ではオンラインでの情報提供やアフターサービスの受付なども含まれます。
多様なチャンネルを持つことで、グローバルに展開される自動車産業の動向や需要変化にも柔軟に対応可能です。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーごとに求める供給体制や納入条件が異なるため、直接取引を重視しつつ市場全体の変化に合わせて幅広い販売網を整備する必要があったからです。
また、補修部品市場では代理店や整備工場を通じた販路が重要なため、地域によって最適なチャンネルを構築する戦略が求められています。
顧客との関係
同社は長期的な取引関係を大切にしており、技術サポートやカスタマーサービスを通じて信頼度を高めています。
自動車メーカーは新車開発の際、コストだけでなく安全面や信頼性を重視するため、供給先のブレーキメーカーとの関係は長期化する傾向にあります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、一度大規模なテストを経て採用が決まるブレーキ部品は、モデルチェンジまで基本的に使い続けられることが多く、入れ替えには多大な費用や期間がかかるからです。
曙ブレーキ工業は積極的な技術支援と品質保証で顧客企業との結びつきを強化し、長く使い続けてもらう関係を構築しています。
顧客セグメント
主に自動車メーカー、商用車メーカー、そして補修部品市場が大きな顧客セグメントです。
幅広い市場に対応できるのは、独立系として特定のグループに縛られない立場と、乗用車からトラック、バスなど多彩な車両向けに製品を開発してきた実績があるからです。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車産業は世界規模で供給網が広がっており、地域や車種によって求められるブレーキの仕様が異なります。
そのため特定メーカーの系列に属さず、多様な仕様に対応できる開発力と生産体制を整えることで、幅広い顧客セグメントを獲得しているのです。
収益の流れ
曙ブレーキ工業の収益は、新車向けのブレーキ供給からの売上、そして補修部品市場での販売による収益に大きく依存しています。
新車向けの受注が堅調であれば出荷台数増に伴って売上が増え、補修部品市場では継続的なブレーキ交換需要が期待できます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、ブレーキ部品は安全上重要であり、定期的な交換が義務付けられるケースも多いからです。
さらに長い目で見ると、アフターサービスや補修用パーツの安定需要が企業のキャッシュフローを下支えし、研究開発などに再投資できる好循環が生まれやすくなります。
コスト構造
コストの大部分を占めるのは原材料費や製造コストですが、研究開発費や販売管理費も重要です。
特にブレーキの性能を左右する摩擦材や金属部品は素材価格に左右されやすく、世界的な資源価格の上昇が利益を圧迫する可能性があります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、軽量化や耐久性向上など高機能な素材が求められる一方、環境規制や為替変動によって調達コストが増えやすいからです。
これらのコストを適切に管理しながら、研究開発や品質管理に投資を続けることが、他社との競争で優位に立つカギとなっています。
自己強化ループ
同社では自動車需要が回復すると新車生産が増え、それに伴ってブレーキの受注数が拡大し、売上や利益が上がりやすくなります。
その利益の一部を研究開発に再投資することで、新素材の活用や生産工程の自動化など、さらなる技術革新が進みます。
技術力が高まると自動車メーカーからの信頼度が向上し、新たな契約やモデルへの採用につながります。
こうして需要拡大と技術投資の好循環が生まれることで、同社は長期的な業績の成長を目指しています。
一方で、原材料高や為替リスクなど外部要因が働く可能性もあるため、その影響を抑えられる体制整備も同時に進め、安定的な好循環を維持する取り組みが続けられています。
採用情報
曙ブレーキ工業の初任給や平均休日、採用倍率など具体的なデータは公表されていません。
ただし、製造業の中でも技術開発に注力している企業のため、専門知識を生かせる環境やグローバルな生産拠点で働けるチャンスがあるとされています。
興味がある方は最新の企業情報や採用ページを確認すると良いでしょう。
株式情報
銘柄は曙ブレーキ工業で、証券コードは7238です。
2024年3月期の年間配当は0円となっています。
株価は2025年2月20日時点で118円程度で推移しており、為替レートや自動車市場の動向などが影響する可能性があります。
今後、さらなる研究開発や事業拡大に力を入れるのであれば、利益の内部留保を優先する状況が続くのかもしれません。
未来展望と注目ポイント
曙ブレーキ工業は既存の乗用車向けブレーキ市場だけでなく、商用車やEV、さらには自動運転関連など新しい分野での需要が期待できる状況です。
特にEVの軽量化や自動運転システムとの連動性を高めるには、専用のブレーキ技術や制御システムが必要となるため、高い技術力を持つ企業には新たな商機が生まれやすいです。
また、海外拠点の活用により、北米やアジアなど成長市場での生産を強化する戦略が進められれば、さらなる業績拡大が見込まれます。
一方で、原材料費やエネルギーコストの上昇は引き続き収益を圧迫する可能性がありますが、そこを上回る付加価値を製品に与えられるかどうかが重要になりそうです。
今後も業績の推移とあわせて、環境対応技術や新しい安全機能への投資動向に注目が集まっています。

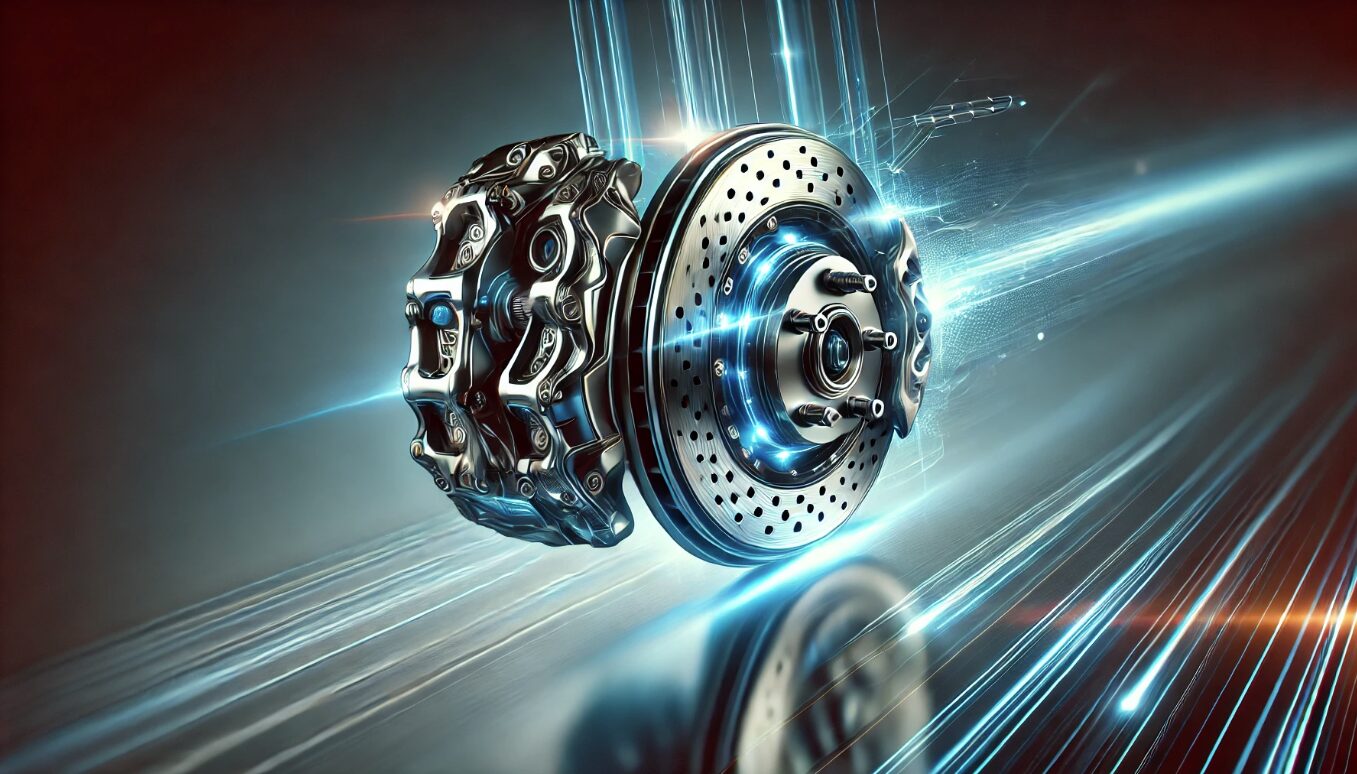


コメント