企業概要と最近の業績
株式会社きもと
きもとは、フィルムに様々な機能を加える加工技術を核とした、高機能性フィルムの開発・製造・販売会社です。
事業は、ディスプレイの部材やデータ保存用テープの基材などに使われる「高機能フィルム」が中心です。
また、地図情報の収集・加工や、文化財のデジタルアーカイブなどを手掛ける「CG・GISデータ」事業も展開しています。
長年培ってきたコーティングや表面処理などの独自技術を応用し、エレクトロニクスから自動車、建築まで幅広い産業分野に製品を供給しています。
2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が41億11百万円となり、前年同期比で6.1%の減収となりました。
営業利益は34百万円で前年同期比61.8%減、経常利益は55百万円で同64.5%減、親会社株主に帰属する四半期純利益は42百万円で同67.7%減となり、減収減益でした。
主力の高機能フィルム事業において、一部の顧客で生産調整があったことなどから、電子部品関連のフィルム販売が伸び悩みました。
CG・GISデータ事業は堅調に推移したものの、全体の減収を補うには至りませんでした。
利益面では、原材料価格の高止まりなども影響しました。
価値提案
株式会社きもとは、高機能フィルムとデジタルツイン技術という2つの領域で明確な価値を提供しています。
まず、フィルム事業においては、極めて薄い素材に遮光や粘着、拡散といった複数の機能を持たせられる技術力が強みです。
自動車の内装やディスプレイ、通信機器の高度化に対応できる品質は、他社が参入しにくい分野として大きく差別化を生んでいます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、IoTや車載ディスプレイの普及により機器の軽量化と高機能化が同時に求められた背景があり、同社が長年培ってきた薄膜技術と開発力が最適なソリューションになっているからです。
一方、デジタルツインでは実際の空間とデータを融合させるサービスに注力し、河川や公共インフラなどの管理を効率化する仕組みを構築しています。
これにより、行政や大手建設会社が抱える課題を解決する手立てを提示できるようになり、従来のフィルムとは別の分野でも高い付加価値をもたらすようになりました。
主要活動
同社の主要活動は、大きく分けてフィルムの製造・販売とデジタルデータの加工・提供に集約されます。
フィルム製造においては、研究開発から生産、品質管理までを一貫して行い、スピーディーかつ安定的に高機能フィルムを生み出せる体制を構築しています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーや通信機器メーカーの要求水準が高まり続ける中で、外部に委託していては開発スピードや品質保証で不利になりやすいからです。
デジタルツイン関連では、河川管理システムなどのビッグデータを取り扱い、クラウド上での分析やコンテンツ化を行っています。
こうした解析とシステム化をセットで提供する活動が、自治体や公共事業に深く結び付く要因になっています。
フィルムの製造技術とデジタル分野のノウハウを同時に伸ばすことで、事業間のシナジーを狙う姿勢が同社の活動の柱になっています。
リソース
きもとのリソースとしてまず挙げられるのは、高い専門性を持つ人材と最先端の生産設備です。
フィルムのコーティングや薄膜形成技術を支える研究者や技術者が在籍していることで、新製品の開発スピードを維持できています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、競合との差別化を図るためには、知的財産や独自のノウハウが最重要とされてきたからです。
さらに、公共分野のデータを扱うデジタルツイン事業では、セキュリティ面を含めたITインフラが不可欠であり、サーバーやクラウド環境の整備も重要なリソースとして挙げられます。
これらの設備や人的リソースを活かせる基盤があるからこそ、複雑な顧客ニーズに応えられる柔軟性と信頼性が保たれているのです。
パートナー
パートナーとしては、自動車メーカーや通信機器メーカーなどの民間企業だけでなく、公共機関や研究機関も含まれます。
同社のフィルムは車載や通信機器に欠かせない部材として認知が進んでいるため、大手メーカーが開発段階から共同で検討を行い、新しい機能のフィルムを試作することもあります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、ユーザーが求める性能を実現するためには、互いの技術を早い段階で擦り合わせる必要があるからです。
また、デジタルツイン事業においては自治体や政府系の組織との共同研究やシステム導入も進んでおり、公共インフラの維持管理を高度化するプロジェクトに参加するケースが増えています。
こうした幅広いパートナーシップが同社の事業領域を一層拡大させる要因となっています。
チャンネル
チャンネルとしては、直接営業やオンラインによる引き合い、さらにパートナー企業を通じた共同提案などが挙げられます。
フィルム事業は技術的な打ち合わせを要することが多いため、顧客の開発担当者と協力しながら調整を進める直接営業がとても重要ですし、
【理由】
なぜそうなったのかというと、高機能フィルムの仕様は機器や車両の設計に深く関わるため、専門家同士で詳細を詰めなければ正確な製品化が難しいからです。
一方、デジタルツインの案件では公共機関や法人向けのセミナーなどもチャンネルの一つとなっており、現場が抱える課題を直接ヒアリングする機会を通じて導入が進む傾向があります。
これら複数のチャンネルを活かして顧客層を拡大しているのが、同社の特徴です。
顧客との関係
同社はカスタマイズ対応と長期的な技術サポートを重視しています。
自動車産業であれば車両モデルチェンジの際に新しい部材を求められることが多く、通信機器でも新製品ごとに求められる性能が異なります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、顧客の技術革新スピードが速い現代において、カタログ製品だけでは満足してもらえないシーンが増えたからです。
また、デジタルツインの分野では導入後のデータ管理や追加要望への対応が不可欠であり、一度契約して終わりではなく継続的なアップデートやサポートが発生します。
こうした顧客との深い関係構築がリピート受注や追加受注の機会を増やし、経営の安定につながっています。
顧客セグメント
主に自動車産業と通信機器産業、そして公共インフラ関連の企業・機関が顧客セグメントに位置付けられます。
自動車産業では内装やディスプレイ分野の軽量化と高耐久化、通信機器では小型化と多機能化のニーズが強く、同社の高機能フィルムが役立つ場面が多いです。
【理由】
なぜそうなったのかというと、これらの産業はIoTや5Gなどの進化に伴い、より繊細で高機能な素材を求めるトレンドが続いているからです。
また、デジタルツインを活かした公共インフラ関連では、河川や道路、ダムなどの保守管理を効率化する仕組みを提供しています。
これにより、自治体や国が抱える老朽化インフラの課題を解決しやすくなるため、長期的なニーズが見込まれています。
収益の流れ
収益はフィルム製品の販売収入と、デジタルサービスの提供からの収入に大きく分かれています。
フィルム製品はBtoB取引が主であり、試作品から量産品までの受注が安定収益を生み出しています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーや通信機器メーカーが継続的に製品化を行っており、量産契約にこぎつければ長期にわたって安定的に供給する体制を築きやすいからです。
一方、デジタルツイン関連ではシステム導入費用と保守・運用サポートの契約が収益源となります。
公共案件のため契約金額が大きいだけでなく、データ更新や追加要望に対応するサブスクリプション型のサービス提供で継続収益を得られる点も魅力になっています。
コスト構造
コストは主に製造コストと研究開発費、販売・マーケティング費用で構成されています。
高機能フィルムの原材料やエネルギー費は、国際的な原材料価格の変動に影響を受けやすく、コスト管理が経営上の課題の一つです。
【理由】
なぜそうなったのかというと、同社が提供するフィルムには特殊な素材や高度な加工が必要であり、単純な代替品が少ないからです。
デジタルツイン側ではデータ解析やシステム保守に必要な人件費とITインフラの維持費が大きく、この部分のコスト最適化が利益率向上の鍵になります。
研究開発費は中長期的に見て新技術の確立や他社との差別化を保つために欠かせない要素であり、同社が持続的に投資を行うポイントです。
自己強化ループ
きもとが生み出す自己強化ループは、高付加価値の製品やサービスを開発し、その売上や利益を再投資してさらに強力な技術を確立する好循環から成り立っています。
まず、自動車や通信機器向けの高機能フィルムは、性能が高いほど収益性が上がりやすい特徴があります。
その結果、得られた利益を新しい研究開発に充てることで、より画期的なフィルムやソリューションを生み出す土壌が整うのです。
同時に、デジタルツインの事業でも公共インフラや民間の大規模プロジェクトを受注するほど、システムの開発力やデータ解析の精度が蓄積され、次の案件でさらに進んだサービスを提供できます。
こうした循環がブランド力を高め、顧客からの信頼につながり、追加注文や継続的な契約を呼び込む要因にもなっています。
このようにフィルム事業とデジタル事業が同時に発展することで、企業としての基盤がより強固になり、新たなマーケットにも柔軟に進出できるサイクルが生まれているのです。
採用情報
きもとでは技術研究職や営業職、事務職など幅広い分野で人材を募集しています。
初任給は大学院卒で21万円、大学卒が20万2千円、短大や高専、専門卒は17万4千円となっています。
休日は土日と祝日を中心に週休2日制で、年末年始や慶弔休暇など各種休暇制度も充実しており、ワークライフバランスを重視しながら働きたい方にとって魅力的です。
採用人数は若干名ですが、技術系の高度な開発業務やデジタル分野のシステム企画に携われる可能性があるため、専門性を活かしたい人にはやりがいを感じられる環境だといえます。
実際に応募したい方はこまめに選考情報をチェックすることをおすすめします。
株式情報
銘柄は株式会社きもとで、証券コードは7908です。
配当金については、2025年3月期の年間予想が6円(中間3円と期末3円)とアナウンスされています。
株価の最新情報は証券取引所や各種金融情報サイトで随時更新されていますので、投資を検討する方は時期や市況に合わせて確認すると良いでしょう。
配当金が一定額見込める点は、安定的な利益体質への期待を示す材料になっています。
長期的に事業展開をチェックすることで、さらなる成長の波に乗るチャンスを見極める投資判断ができるかもしれません。
未来展望と注目ポイント
今後、株式会社きもとがさらに注目される理由は、IoT社会の深化と公共インフラのデジタル化にあります。
自動車向けの高機能フィルムは、電気自動車や自動運転車の普及に伴い、軽量化や安全性向上のための素材ニーズが拡大すると見られます。
これによって、同社の独自技術がますます重宝される可能性が高まるでしょう。
また、通信機器においても5Gや6Gなどの次世代通信規格が進展するにつれ、高周波対応や放熱機能の向上を狙ったフィルムの需要が一段と高まると予測されます。
さらに、デジタルツインの分野では、社会インフラの老朽化や自然災害への備えが重要視される中、データ解析や遠隔監視を活用した効率的な運用管理のニーズは減るどころか増える一方です。
この流れを的確に捉えられるかどうかが、きもとの今後の大きな分かれ道になるでしょう。
技術への再投資で競争力を保ち、顧客とのコラボレーションを深めて新しいソリューションを創造できれば、さらなる成長が期待できると考えられています。
売上や利益の拡大に加えて、事業の多角化による安定経営が実現すれば、市場からの評価も一層高まる可能性があります。
中期的な経営戦略と研究開発の動向に引き続き注目していきたいところです。

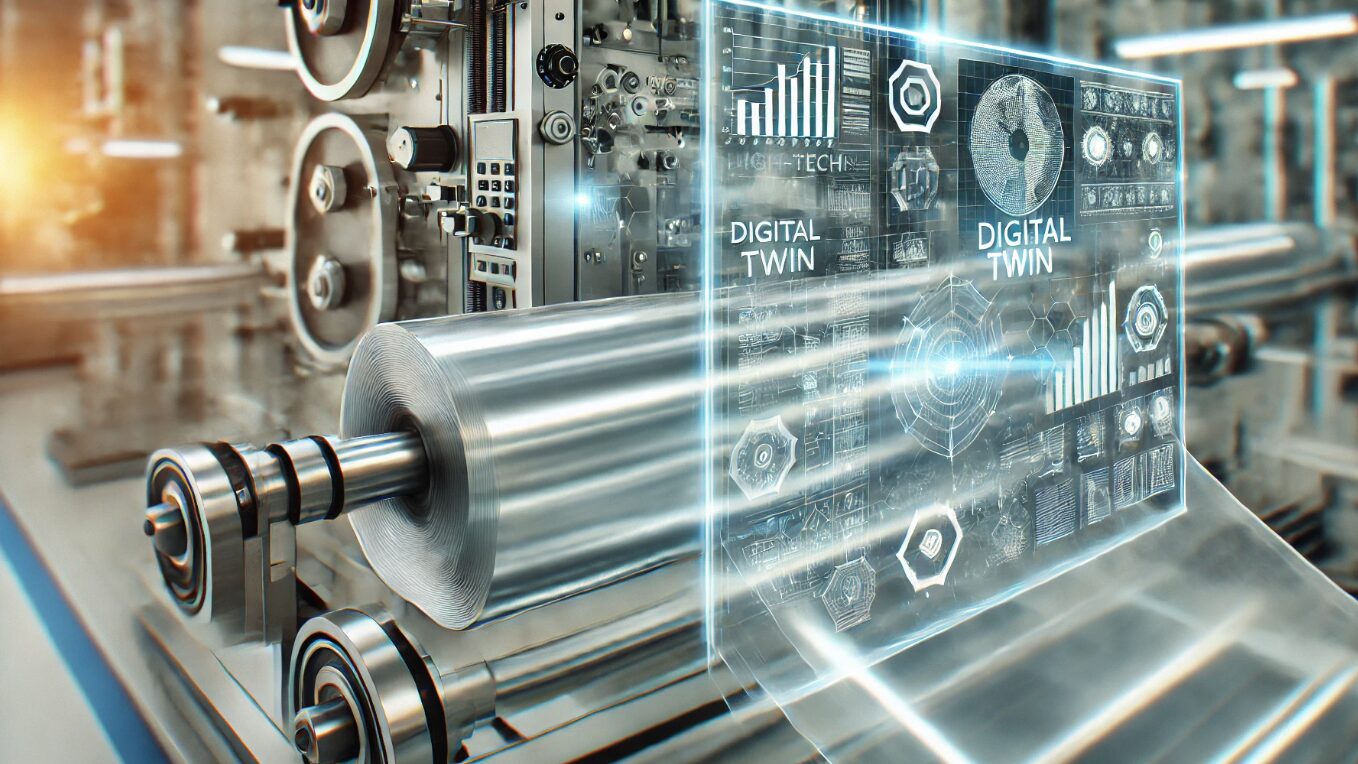


コメント