企業概要と最近の業績
株式会社スクロール
通信販売事業を中核とし、ソリューション事業やeコマース事業などを展開する企業です。
静岡県浜松市に本社を置き、カタログやインターネットを通じてアパレル、生活雑貨、化粧品などを販売しています。
長年の通販事業で培ったノウハウを活かし、他の通販事業者へのフルフィルメントサービス(EC支援)も提供しています。
2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が166億43百万円(前年同期比4.1%減)、営業利益は4億9百万円(同47.6%減)となりました。
経常利益は4億85百万円(同42.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億60百万円(同53.3%減)と、減収減益でした。
主力の通信販売事業において、暖冬の影響で冬物衣料の販売が苦戦したことや、化粧品関連で一部ブランドの販売が終了したことなどが響きました。
ソリューション事業は、既存取引先の業務拡大や新規取引先の獲得により増収となりました。
eコマース事業は、円安の影響を受けたものの、新規顧客の獲得が順調に進み、前年同期並みの売上を確保しました。
【参考文献】https://www.scroll.jp/
価値提案
全国一律のカタログ配布を活用し、忙しい方でも自宅で手軽に買い物ができる利便性を提供している。
物流代行や決済代行などをまとめて行うソリューションを展開し、EC事業者が抱えるコストや人手不足を解消している。
【理由】
なぜそうなったのかの背景としては、まず長年培ってきた通販ノウハウを生協組合員向けのカタログビジネスに活かすことで、安定した収益を得られる仕組みが整ったことが挙げられます。
その一方で、自社で培ったノウハウやインフラを他のEC事業者にも提供する形をとることで、さらなる売上拡大を狙った結果、BPOサービスなど総合的な支援体制を整えました。
これによって消費者には便利な購買環境を、EC事業者にはコスト削減と業務効率化をもたらすという双方にとって魅力的な提案ができるようになっています。
主要活動
カタログの企画と制作を通じて、生協組合員などの広い顧客層に商品情報を定期的に届ける。
物流拠点を活用し、受注から配送までを一貫して行うBPOサービスを提供している。
【理由】
なぜそうなったのかに関しては、まず自社の通販事業での運営効率を高めるために、商品企画から受注、配送まで一連のプロセスを最適化してきたことが大きいです。
その結果、ノウハウを活かして他社EC支援を行うソリューション事業を強化しやすくなりました。
さらに、全国一律でカタログを配布する仕組みは、多くの潜在顧客へのリーチ力を高め、定期的に商品を提案できるため、リピーターを生みやすいことにつながっています。
リソース
生協組織とのつながりにより確保された約800万世帯の安定した顧客基盤。
物流拠点やコールセンターなど、通販に必要なインフラと専門スタッフがそろっている。
【理由】
なぜそうなったのかの背景としては、生協との協力関係を長年築き上げてきた歴史が大きく関わっています。
これによって、他社にはない大規模な顧客リストと販売チャネルを持つようになりました。
同時に、商品を確実に届けるための物流設備や、顧客対応を担うコールセンターを自社で整備してきたことが、通販事業とソリューション事業の成長を下支えしている要因です。
これらのリソースがあるからこそ、新規のEC事業者が参入してきても、差別化を図れる強みになっています。
パートナー
生協組織との協力による全国的な配布網。
物流会社や決済プロバイダーとの連携によるスムーズなBPOサービス。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、まず生協という巨大なネットワークと結びつくことで、全国規模の顧客に一斉にアプローチできる強みを手に入れました。
また、物流や決済といった専門的な領域については、外部の専門企業と組むことでコストと品質の両面を安定化してきました。
こうしたパートナー関係を上手に活用することで、自社はコアとなる企画やマーケティングにリソースを集中し、スピード感あるサービス提供を実現してきたのです。
チャンネル
紙のカタログとオンラインショップを併用するハイブリッド戦略。
電話やウェブを通じた受注体制で、年代や地域を問わず商品を届ける。
【理由】
なぜそうなったのかは、まず生協組合員の世代層が幅広く、デジタルだけに頼るのではなく紙媒体も欠かせないと判断したことが大きいです。
一方で、EC市場が拡大する中、オンラインショップやアプリへの移行も避けては通れない課題です。
両方を上手に組み合わせることにより、特にネットに不慣れな層にもアピールしつつ、デジタル対応を強化している段階にあります。
このような多面的なチャンネルを展開していることが、安定成長を支える原動力になっています。
顧客との関係
定期的なカタログ配布と電話窓口による、身近なコミュニケーション。
BPOサービスでは顧客企業との長期的な契約関係を重視。
【理由】
なぜそうなったのかを探ると、まず生協の組合員向けカタログは、長い歴史の中で「いつでも注文しやすい仕組み」として定着してきました。
そのおかげで利用者にとっては信頼感のある接点が保たれています。
また、ソリューション事業では、単発の代行ではなく継続的なサポートを提供することで顧客企業との関係を深めやすくなりました。
これにより安定的な収益を確保しつつ、新たなサービス追加や改善提案もしやすい循環が生まれています。
顧客セグメント
生協組合員や一般消費者といったB2C領域。
EC事業者や通販企業を含むB2B領域。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、歴史的にはカタログ通販のB2Cビジネスが強みでしたが、EC市場の成長に伴い自社ノウハウを他社にも提供するチャンスが見えてきました。
そこでB2Bのソリューション事業を拡充し、物流やコールセンター機能を外部向けにも展開したのです。
これによって、消費者向けの売上に加えて企業との取引でも手数料収入が得られるようになり、顧客セグメントが拡大しているのが大きな特徴です。
収益の流れ
通販事業では商品販売による収入。
ソリューション事業ではBPOサービスの利用料や手数料。
【理由】
なぜそうなったのかに関しては、まず通販ビジネスで生協組合員という巨大な顧客基盤を得ていたので、そこで得られる安定売上がベースにあります。
一方で、EC化の波に乗るために培ってきた物流やコールセンター運営のノウハウを他社にも提供すれば、BPOサービスの手数料という新たな収益源を獲得できると考えたわけです。
こうした多角的な収益モデルによって、景気や市場の変動にも柔軟に対応できる仕組みを作り上げました。
コスト構造
商品仕入れに伴う原価やカタログ制作費。
物流やコールセンター運営などの人件費や設備維持費。
【理由】
なぜそうなったのかを見てみると、カタログを全国に配布するには印刷費用や発送費など相応のコストがかかります。
また、自社で物流設備を持つことで初期投資や維持費は高くなりますが、その分サービス品質をコントロールしやすく、他社へのBPO提供の際にも自社拠点を利用できるメリットがあります。
コストは高めに見えますが、安定供給と品質保持によるリピート客の獲得、さらにB2Bサービスの手数料収入拡充がコストをカバーしやすい構造を支えています。
自己強化ループについて
株式会社スクロールの自己強化ループは、通販事業とソリューション事業が相乗的に成長を促す仕組みとして機能しています。
自社通販で培ったノウハウをソリューション事業に転用し、他企業の物流代行やコールセンター業務を行うことで多種多様な経験値が蓄積されます。
そこから得られた知見を再び自社通販にフィードバックすることで、商品選定や顧客対応の精度が上がり、販売機会を拡大しやすくなるのです。
この循環が加速すると、ますます高品質なサービス提供が可能となり、他社からの受注も増えることにつながります。
結果的に通販事業の売上増とBPOサービスの拡大が同時進行で進み、全体的なスケールメリットを享受できる点が大きな強みと言えます。
採用情報
株式会社スクロールでは大卒初任給として月額22万円を提示しています。
年間休日は120日ほどで、オンとオフのメリハリがつけやすい環境です。
採用倍率は約10倍であり、安定した事業基盤や多角的な成長戦略に魅力を感じる人が多いと考えられます。
通販やBPOに関する業務は幅広いため、入社後にさまざまな職種で活躍できる機会が見込めるのが特徴です。
株式情報
同社の銘柄コードは8005で、株価は1株あたり2025年2月25日時点で2500円となっています。
配当金は年間50円を予定しており、投資家にとっては安定した配当収入を期待できる企業の一つです。
今後の株価や配当方針は経営環境や業績によって変動する可能性があるため、定期的にIR資料をチェックすることでより正確な情報を得ることができます。
未来展望と注目ポイント
株式会社スクロールは従来の通販事業だけでなく、EC全盛時代に対応するためのBPO事業を強化している点が大きな注目ポイントです。
特に生協を中心に築き上げた安定的な販売ネットワークがあるため、デジタルシフトが進んでも紙とオンラインを組み合わせた柔軟な手法を展開できます。
これにより購買層を広げつつ、競合他社との差別化を図ることが可能です。
今後はオンラインサービスの拡充と同時に物流を含むインフラ強化が求められ、これらに投資することで一段上の成長を目指す見通しです。
また、多様なデータや顧客ニーズを活かし、商品開発や新規サービス創出にも積極的に取り組むことで、さらなるシェア拡大が期待されています。
通販とソリューションを両立させるビジネスモデルを軸に据えているため、継続的な売上増や収益力の安定が見込まれ、投資家や就職希望者が注目する企業としての地位を今後も維持しそうです。


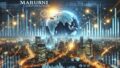

コメント