企業概要と最近の業績
株式会社スリー・ディー・マトリックス
スリー・ディー・マトリックスは、自己組織化ペプチド技術という独自の技術を基盤とする医療機器・医薬品開発企業です。
この技術を応用した、手術時に出血を止めるための医療機器(吸収性局所止血材)の開発・製造・販売を主な事業としています。
透明で使いやすいといった特徴を持ち、国内外の医療現場で採用されています。
将来的には、この基盤技術を再生医療や創薬の分野に応用することを目指して研究開発を進めています。
2026年3月期第1四半期の決算短信によりますと、売上収益は8億9百万円となり、前年の同じ時期と比較して35.1%の大幅な増収となりました。
一方、営業損失は5億13百万円(前年同期は5億55百万円の営業損失)となり、赤字幅は縮小しました。
親会社の所有者に帰属する四半期損失は5億74百万円で、前年同期から損失額が改善しています。
主力の止血材が国内外で販売を伸ばし増収に繋がりましたが、将来の成長に向けた研究開発費や、販売体制強化のための費用が先行し、営業損失が継続したと報告されています。
価値提案
株式会社スリー・ディー・マトリックスの価値提案は、生体適合性に優れた自己組織化ペプチド技術を通じ、患者さんや医療従事者に安心かつ効率的な治療手段を提供することにあります。
従来の止血材や組織再生素材では、体内吸収や組織との相性などで課題が多くありました。
同社の技術は手術中の使いやすさや安全性に配慮した設計が施されており、世界各地の医療機関から高い評価を受けやすくなっています。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、研究開発初期から大学や専門機関と連携し、生体内環境に適合しやすいペプチド構造を緻密に検証してきた経緯があります。
このように学術的根拠に基づいた製品開発を続けてきたことで、患者さんへの負担を減らしつつ効果を最大化するソリューションを提案できるようになりました。
主要活動
同社が最も力を注いでいるのは、医療用バイオマテリアルの研究開発と販売です。
特に止血材「PuraStat」を中心とした外科領域での応用実績が高く、さらに組織再生やDDS領域へも幅広く展開しようとしています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自己組織化ペプチド技術は多様な治療シーンに応用できる汎用性の高さを持ち、ひとつの成功事例が別の医療分野への発展を促す側面があるためです。
加えて、米国など海外市場で実際に売上拡大を実現したことで、各地域での販売や治験を継続的に行う体制を整えやすくなりました。
こうした積極的な臨床・販売活動が同社の主要活動を力強く支えているのです。
リソース
同社のリソースは自己組織化ペプチド技術に関わる特許やノウハウ、そしてこれを実現する高い専門知識を持った研究開発チームに集約されます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、医療バイオ産業では製品化までのプロセスが長期にわたるため、特許や独自技術、そしてそれを扱う人材がないと競合他社との差別化が難しいからです。
長年にわたり蓄積された化学・生物学的な知識を活かし、自社で研究開発を主導できる点が強みといえます。
この技術基盤があるからこそ、多角的な医療応用や新たな治療手段の開発がスムーズに進められており、競争優位を確立しやすい土台を整えているのです。
パートナー
株式会社スリー・ディー・マトリックスは大学や医療機関、製薬企業との共同研究や連携を積極的に進めています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、医療分野で新たな技術を普及させるためには、製品の有効性や安全性を学術的に証明する必要があるためです。
大学との共同研究により基礎データをしっかり蓄え、医療機関を通じて臨床応用の実績を重ねる流れが、製品の信頼性を向上させています。
また、製薬企業と組むことで販売経路の拡大や大規模な治験プロセスを進めやすくなり、世界市場での承認や導入が加速するメリットを得ています。
チャンネル
同社の製品は自社販売と医療機器ディストリビューターによる流通を組み合わせる形を取っています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、専門性の高い医療機器を扱うには医師や医療スタッフへの研修とサポートが欠かせず、自社でカバーしにくい地域や販売ルートを拡充するにはディストリビューターの存在が重要だからです。
自社による直接販売では製品特性の正確な伝達とアフターサポートを行いやすく、一方で販売ネットワークの広さを補完するのがディストリビューターの役割となっています。
この二つのルートを使い分けることで、より多くの医療機関に製品を届けることが可能になっています。
顧客との関係
顧客は主に外科医や内科医などの医療従事者です。
同社は学術セミナーや学会発表、トレーニングプログラムなどで積極的に情報提供を行い、導入時の疑問や使い方のポイントをしっかりサポートしています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、医療現場では製品の安全性と使い勝手が非常に重視されるため、初期導入時のサポート体制が信頼獲得の鍵を握るからです。
専門家同士のコミュニティである学会にて製品の有効性データを共有することで、新規ユーザーにも安心感を持ってもらいやすいというメリットがあります。
このようなサポートと情報発信の継続が顧客との良好な関係を築く大きな要因になっています。
顧客セグメント
同社の顧客セグメントは幅広く、外科医や消化器内科医、耳鼻咽喉科医など、止血材や組織補填材を使用する可能性がある領域が主です。
【理由】
なぜそうなったのかというと、自己組織化ペプチド技術は切開手術のみならず、内視鏡下での止血や修復にも有用とされているためです。
さらに将来的には整形外科や再生医療、美容医療などの領域でも応用が期待されており、実際に放射線性直腸炎や炎症性腸疾患など新しい適応への研究も進んでいます。
このように多領域に顧客を広げられるのが、独自技術のもつ大きな強みとなっています。
収益の流れ
収益源は医療機器としての製品売上が中心となります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、同社の技術は実際の医療現場で使用される物理的な製品に結実しているからです。
止血材や組織補填材などは消耗品としての需要があり、手術や治療が行われる限り継続的な買い替えや補充が発生します。
加えて、DDS関連や再生医療分野など新規プロジェクトが実用化すれば、ライセンス収入や共同開発契約からの収益も見込まれます。
このように多角的な製品ラインと技術シーズを持つことで、長期的な安定収益を形成する土台づくりを目指しているのです。
コスト構造
研究開発費が大きな比重を占め、次いで製造コストや販売・マーケティング費用が続きます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、バイオベンチャーとして製品の信頼性や新しい適応症の開拓には継続的な研究が不可欠だからです。
医療分野は安全性と有効性の証明が重要であり、それに伴う試験や臨床データの取得には莫大な費用と時間がかかります。
しかし研究開発を怠ると競合に追い抜かれてしまうため、ベンチャーであっても積極的に投資を継続する必要があります。
このコスト構造を理解しながらも、海外展開や既存製品の売上増などで収益を高め、研究開発を回していく流れが同社の長期戦略となっています。
自己強化ループ
株式会社スリー・ディー・マトリックスが成長を加速させる大きな要因は、海外事業の成功がさらなる投資と開発力強化につながる自己強化ループにあります。
例えば米国子会社が黒字化したことで、研究開発や新製品の臨床試験に再投資できる余力が生まれます。
その結果、組織再生やDDS分野など次の有望領域で革新的な製品開発を進めやすくなるのです。
また、実際に米国で成果を上げているという実績が医療従事者や投資家からの信頼度を高め、新規市場への参入や認知度拡大も後押しします。
こうしたプラスの循環が加速すると、研究開発で生まれた新技術を製品化し、さらに海外へ広げるための資金やネットワークが確保しやすくなるでしょう。
結果として、売上増加→研究開発強化→新製品投入→海外展開の成功→さらなる売上増加という好循環が形成され、企業全体が安定的かつ継続的に成長していく見込みがあります。
採用情報
同社の公式サイトでは、初任給や平均休日、採用倍率などの詳細な数値は公開されていません。
新卒や中途の募集分野では研究開発職が中心と思われますが、営業やマーケティングなども募集されるケースがあります。
先端医療に関わる企業だけに、生命科学や化学、薬学の知識を活かしたい方や、グローバル展開を視野に入れたキャリアを希望する方にとっては魅力的な環境といえるでしょう。
最新情報は同社公式サイトで更新されているので、検討している方は定期的に確認するとチャンスをつかみやすくなります。
株式情報
銘柄コードは7777で、2025年2月21日時点の株価は183円となっています。
時価総額は約198億8,100万円で、発行済株式数は108,640,181株です。
現状では配当予想が0円となっており、バイオベンチャーとして内部留保を研究開発に回す姿勢が見られます。
成長を重視する投資家にとっては、将来的に新製品や海外市場の開拓による株価上昇を期待する向きが強いようです。
未来展望と注目ポイント
今後は既存の止血材市場に加え、組織再生やDDS分野など成長余地の大きい領域への本格進出が予想されます。
特に米国での実績を踏まえたグローバル展開が加速することで、売上拡大と収益性改善に拍車がかかる可能性があります。
研究開発が順調に進めば、放射線性直腸炎や炎症性腸疾患など、新たな適応領域での臨床結果を武器に市場を拡大できるでしょう。
また、国際的な医療ニーズに対応したライセンス契約を結ぶことで、収益の多角化が進むことも期待できます。
投資の観点では、医療バイオセクター特有のリスクとリターンを理解しつつ、IR資料のチェックや学会発表などの情報収集が重要になりそうです。
研究成果の進捗や海外規制当局の承認動向によって、企業価値が大きく変動する可能性があるため、常に最新情報を追いかけることをおすすめします。
長期的には自己強化ループを回し続け、研究開発型のバイオベンチャーから世界的な医療テクノロジー企業への飛躍が期待されています。

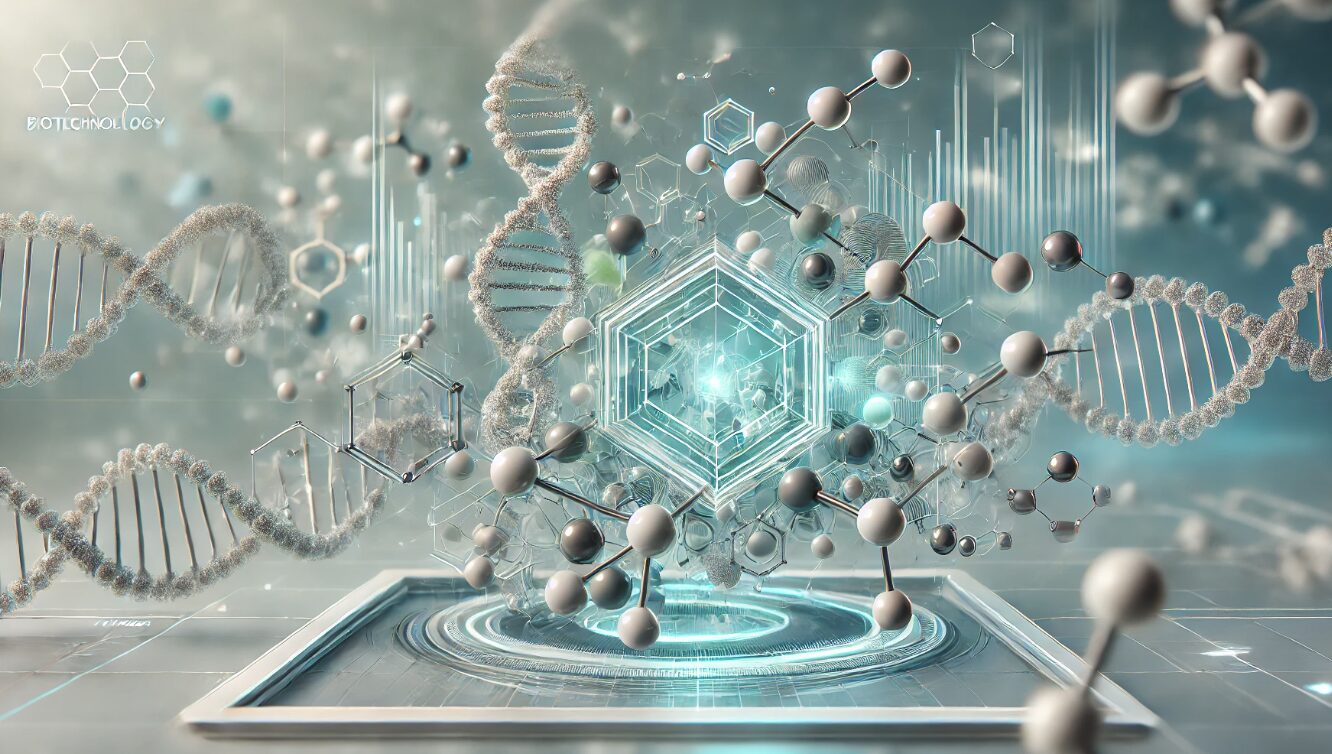


コメント