企業概要と最近の業績
株式会社セカンドサイトアナリティカ
当社は、AI(人工知能)とデータ分析を活用して、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するテクノロジー企業です。
「データサイエンティスト」と呼ばれる専門家集団が、お客様の持つ様々なデータを分析し、ビジネス上の課題を解決するためのAIソリューションを提供しています。
主な事業は、製造業における不良品の検知や需要予測、サプライチェーンの最適化などを行うためのAI開発・コンサルティングです。
私たちは、データとAIの力で、企業の競争力強化と生産性向上に貢献することを目指しています。
2025年5月14日に発表された2025年6月期第3四半期の決算短信によりますと、売上高は13億8,700万円となり、前の期の同じ期間に比べて17.4%の増加となりました。
営業利益は2億6,100万円で、前の期の同じ期間から3.9%の増加となりました。
この業績は、企業のDX投資意欲が旺盛な中、主力である製造業向けのAIソリューション提供やコンサルティング案件が順調に拡大したことが主な要因です。
利益面では、事業拡大のための人材採用や研究開発への先行投資があったものの、売上の増加により吸収し、増収増益を確保しました。
【参考文献】https://secondsight.ai/
価値提案
- データ分析とAI技術を活用して企業の課題を解決するコンサルティングを提供
- 汎用的なAIプロダクトを開発し、幅広い業種で使えるソリューションを提案
【理由】
企業にはビッグデータを活用しきれていない現場が多く存在し、AIによる効率化や精度向上のニーズが拡大している背景があります。
そこで、株式会社セカンドサイトアナリティカはコンサルティングを通じて現場の課題を的確に把握し、最適なAIモデルを構築することで「こうすれば実際に成果が出る」という価値を届けようとしています。
また、ソフトウェアとして提供されるAIプロダクトも、導入企業が自社データを簡単に活用できるように設計されているため、専門知識の少ない担当者でも使いやすい点が評価されており、これらの取り組みが同社の価値提案を支えています。
主要活動
- アナリティクスコンサルティング事業での課題抽出とAIモデル構築
- AIプロダクトの継続的なアップデートと保守サポート
【理由】
単にAI技術を導入するだけでは成果が出にくい企業が多いためです。
顧客ごとの業務内容やデータ特性を丁寧に分析し、必要なアルゴリズムを開発・導入できるコンサルティングが重要と考えられています。
また、導入後もAIモデルは定期的なチューニングやバージョンアップが欠かせません。
そのため、株式会社セカンドサイトアナリティカではAIプロダクトの保守体制を整え、継続的に顧客をサポートする活動を主要な業務として位置づけています。
この両輪がそろうことで、顧客満足度を高め、リピーターや追加案件を確保しやすくなるのです。
リソース
- 高度な専門知識を持つデータサイエンティスト
- 自社開発の機械学習アルゴリズムやAIプロダクト
- 技術顧問や研究機関との連携
【理由】
AIやデータ分析は専門知識が必要な領域であり、優秀な人材の採用と育成が成長の要となるからです。
機械学習アルゴリズムの精度を上げるには、データ前処理からモデル選定、実装まで一貫したスキルが求められます。
そこで、同社はデータサイエンティストなど専門家を充実させることで、顧客ごとに最適なソリューションを提案できる体制を構築しています。
さらに、研究機関などと連携することで、最先端のAI技術を取り入れながらプロダクトを改良し続けています。
このようなリソースを確保することで、コンサルティングの品質向上と独自プロダクトの高度化を実現しているのです。
パートナー
- 大学や研究機関との共同研究
- 事業会社との業務提携
【理由】
AI技術は日進月歩で進化するため、社内の知見だけではカバーしきれない領域が出てくることがあります。
そこで、大学や研究機関と共同研究を行うことで、最新の理論や技術を実務に応用しやすい環境を整えています。
また、事業会社との業務提携は、同社のAIプロダクトをより広い範囲に展開する上で効果的です。
販売チャネルを拡大するだけでなく、具体的な業務課題を共有することで、さらに実践的な製品改善ができるようになります。
こうしたパートナーとの協力が、同社の競争力を押し上げる大きな要素になっています。
チャンネル
- 自社営業チームによる直接提案
- パートナー企業を通じた販売や紹介
【理由】
大手企業を中心にAI導入への関心は高まっていますが、まだ社内に専門家がいないケースも多いからです。
そのため、コンサルティング力を強みにした直接営業で顧客課題を詳細にヒアリングし、最適なソリューションを提案する方法が効果的とされています。
一方で、パートナー企業からの紹介や販売網を活用することで、新たな顧客層へもリーチできます。
異なる業種や規模の企業に対して広くアプローチするために、複数のチャンネルを整えていることが同社の営業戦略の特徴です。
顧客との関係
- コンサルティングを中心とした継続的なサポート体制
- AIプロダクトの導入後の運用サポートやアフターケア
【理由】
AIは導入後もモデルのメンテナンスや効果検証が重要だからです。
初期導入だけでは最適な成果が維持できないため、株式会社セカンドサイトアナリティカはコンサルティングを通じて顧客との長期的な関係を築き、運用状況を随時確認しながらサポートを行います。
モデルの再学習や改善提案など、導入企業の課題に応じて柔軟に対応することで高い満足度を維持しています。
これがリピーターの増加や新たな案件獲得につながり、同社の安定した事業運営を支える要素となっています。
顧客セグメント
- 金融業界や製造業界などデータ活用のニーズが高い分野
- 小売りやサービス業など幅広い業種
【理由】
金融や製造などの分野は大量のデータを扱う上に、予測精度や分析スピードの向上によるコスト削減やリスク管理が重要視されているからです。
また、小売りやサービス業界でも、顧客行動データや在庫管理の効率化が課題となることが多く、AIの導入意欲が高まっています。
そのため、同社はそれぞれの業界の特徴やニーズに合わせてコンサルティング手法やプロダクトを調整できる体制を整え、幅広い顧客層をカバーしています。
この対応力の高さが、多種多様な企業からの相談を受けられる理由といえます。
収益の流れ
- コンサルティングフィー(フロー収入)
- AIプロダクトの販売や保守契約による継続収入(ストック収入)
【理由】コンサルティングは契約期間のプロジェクト型が中心で、導入設計やモデル開発などにかかる費用を一度に受け取るケースが多いからです。
一方で、AIプロダクトはライセンス費用や保守費用といった形で継続的な収入が見込めます。これら両方の収益源を持つことでキャッシュフローが安定し、研究開発への投資も進めやすくなります。
また、コンサルティングでの成功体験がプロダクトの販路拡大にもつながり、プロダクト導入後は追加のコンサルティング需要が生まれるという好循環が起きやすくなっています。
コスト構造
- データサイエンティストやエンジニアなどの人件費
- 研究開発費と販売費
【理由】
AI関連事業は高度な人材や技術が求められるため、優秀なデータサイエンティストを確保するための人件費が大きくなりがちです。
また、常に新たなアルゴリズムや機能を開発する必要があるため、研究開発費をかけることは不可欠です。
さらに、導入を検討する顧客が増える中、営業やマーケティングなどの販売費用も継続的に発生します。
これらのコストをどう最適化しながら、品質の高いサービスとプロダクトを提供し続けるかが、同社の収益力と競争力を左右するポイントになっています。
自己強化ループ
自己強化ループとは、ある取り組みが成果を生み、それが次の活動をより強力にするという好循環のことです。
株式会社セカンドサイトアナリティカでは、コンサルティングを通じて得られた業務知識やデータの特徴を、新しいAIプロダクト開発に反映させています。
これにより、プロダクトの精度や使いやすさが高まり、導入を検討する企業が増えるというプラスの連鎖が生まれます。
また、AIプロダクトを導入した企業の課題がより効率的に解決されると、「他にもこういった分析が必要だ」という次のニーズが見つかり、追加のコンサルティング案件へとつながるのです。
こうしたフィードバックループが同社の成長を後押しし、売上と利益の両面でプラスの影響をもたらしています。
採用情報
採用に関しては、初任給や平均休日、採用倍率などの具体的な情報は公表されていないようです。
高度な専門知識が求められる領域だけに、データサイエンティストやエンジニアの採用は厳選して行われる可能性があります。
働き方や報酬制度など、興味がある方は募集要項をこまめにチェックすることをおすすめします。
株式情報
株式市場では、セカンドサイトアナリティカ(証券コード 5028)として上場しています。
配当金は2024年12月期予想で0円となっており、利益の再投資に力を入れている姿勢がうかがえます。
2025年2月5日時点での株価は1株当たり373円となっており、AI分野への期待感や今後の業績拡大次第で変動が予想されます。
未来展望と注目ポイント
今後は、AI技術がさらに進化するにつれて、より多くの企業がデータ分析と自動化を求めるようになると考えられます。
株式会社セカンドサイトアナリティカは、コンサルティングで培ったノウハウをAIプロダクトに反映する独自のビジネスモデルを確立しており、この点が差別化要因として光ります。
人材確保や研究開発投資を継続して行うことで、汎用性の高いAIソリューションをさらに拡充できれば、多業種への導入も広がり、一層の市場シェア拡大が期待されます。
また、AIモデルの精度が向上すれば、コンサルティングを受けた企業の成果も高まり、リピーターや追加導入の案件が増える好循環が起きやすくなるでしょう。
こうした展開により、収益安定とさらなる成長の両立を目指せる企業として注目されます。
ビジネスモデルやIR資料を通じて同社の取り組みを知ることで、AI時代における最先端の活躍をリアルに感じられるのではないでしょうか。
これからも業績動向や新製品リリースに目を向けることで、同社がどのように市場をリードしていくのかを知る良いきっかけになると考えられます。

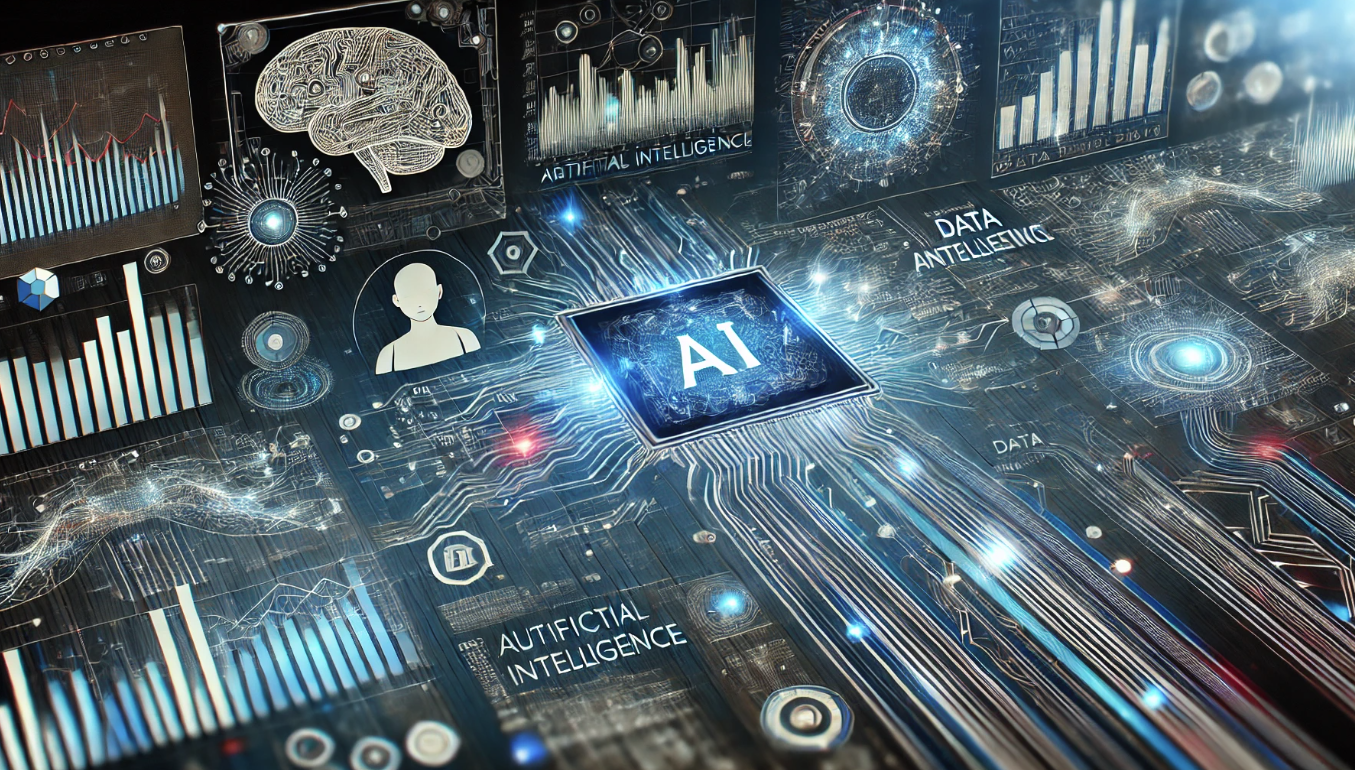


コメント