企業概要と最近の業績
株式会社テラプローブ
当社は、半導体の品質や信頼性を保証するための「テスト」を専門に行っている会社です。
自社で半導体の設計や製造は行わず、国内外の半導体メーカーから依頼を受け、製造工程の最終段階で製品が正常に作動するかを検査する事業に特化しています。
具体的には、シリコンウェーハの状態で電気的特性を調べる「ウェーハテスト」と、完成品となった半導体の品質を保証する「ファイナルテスト」のサービスを提供しています。
最新の2025年12月期第2四半期の決算によりますと、半年間の累計売上高は203億7,300万円となり、前年の同じ時期と比べて13.5%の減収となりました。
これは、スマートフォンやパソコン市場の在庫調整が長引いたことにより、関連する半導体のテスト需要が減少したことが主な要因です。
データセンター向けや車載向けの半導体テストは堅調に推移したものの、全体の落ち込みをカバーするには至りませんでした。
売上の減少に伴い、利益面でも固定費の負担が重くなったことなどから、営業利益は23億7,800万円と、前年の同じ時期から45.4%の大幅な減益となっています。
価値提案
テラプローブの価値提案は、高い品質と迅速な対応を同時に実現する半導体テストサービスにあります。
特にDRAM分野での豊富な経験を活かし、顧客が求める低不良率やスピードアップを提供できることが大きな利点です。
【理由】
同社は創業当初からエルピーダメモリ(現マイクロン)のテスト部門を母体としてノウハウを積み上げており、大量生産時の歩留まり改善やレイテンシ削減など実践的な課題を解決する力を養ってきました。
さらにグローバルに展開するPTIグループの一員となったことで、新設備への投資や最新技術の取り込みがスムーズに行える体制が整い、高品質とスピードを両立する独自の価値が生まれています。
主要活動
同社が中心的に取り組んでいる活動は、ウエハテストとファイナルテスト、そしてテスト技術の研究開発です。
ウエハテストでは主に製造後すぐの半導体を検査し、歩留まり向上と不良品の早期排除に努めています。
ファイナルテストではパッケージ化後の動作確認を行い、製品として市場に出る最終段階での品質保証を担います。
【理由】
高い信頼性を求める車載やサーバー向けに対応するためには、前工程と後工程の両テストが不可欠となるからです。
また顧客ニーズに合わせたテスト技術の開発も重要であり、複雑化・高速化する半導体に合わせて常に新たな検査手法を研究する姿勢が企業価値を高める大きな柱となっています。
リソース
テラプローブのリソースとしては、最新鋭のテスト装置や高度な半導体知識を持つエンジニアが挙げられます。
ウエハテスト装置やハンドラーなどの設備を多く導入しているため、多様な半導体製品に対応できるキャパシティを保持しています。
【理由】
大口顧客からの要望や市場で急速に進む高集積化に対応するため、継続的な設備投資が必須だったからです。
また専門技術者の育成や採用にも力を入れ、現場で蓄積される知見を体系化することで、より効率的かつ高精度なテストが可能になっています。
結果として、設備と人材という両面のリソースが強みとなり、他社では簡単に模倣しにくい独自のテスト体制を築き上げています。
パートナー
テラプローブはPTIグループをはじめ、製造装置メーカーや材料メーカーなどとの連携を大切にしています。
特にPTIグループ各社との連携により、前工程から後工程までシームレスにつなげる体制を構築している点が特徴です。
【理由】
半導体テストは後工程だけでなく前工程の知識や情報と連動することで、検査精度を高めたり不具合の原因を迅速に特定したりすることができるためです。
こうしたパートナーシップによって調達や新技術導入のスピードが上がり、市場の変化にも柔軟に対応できるようになっています。
チャンネル
同社のチャンネルには、直接営業やPTIグループ経由の受注が含まれます。
大口顧客との取引が多いため、専任の営業担当がテスト仕様のヒアリングやスケジュール管理を行い、安定した取引関係を築いています。
【理由】
半導体テストは製造工程と密接に結びついており、仕様のすり合わせや納期調整が非常に重要だからです。
グループ企業との連携を活かし、迅速かつきめ細かな対応を可能にすることで、大手メーカーからの信頼を獲得しているといえます。
顧客との関係
テラプローブは顧客との長期的なパートナーシップを目指す関係構築を重視しています。
【理由】
半導体テストは一度受注すると継続的に利用されるケースが多く、顧客にとってテストの信頼性や歩留まり改善のノウハウが非常に重要な競争力となるためです。
その結果、同社は顧客企業の研究開発段階から共同でテスト手法を検討するなど、単なる受託以上の付加価値提供を行える強みを持っています。
こうした連携が進むことで、中長期的な継続受注や技術力の向上につながっています。
顧客セグメント
同社の顧客セグメントは車載、5G、サーバー向けなどの半導体メーカーが中心です。
高速通信や大容量メモリを必要とする分野は、今後も市場拡大が予想されるため、成長余地が大きい領域でもあります。
【理由】
半導体市場はスマートフォンやパソコンだけでなく自動車やクラウドインフラといった新たな分野に広がっており、特に車載やサーバー用は信頼性や高性能が求められます。
こうした需要に対応できる技術力を持つことが、テラプローブの顧客層を広げる要因になっています。
収益の流れ
同社の収益の流れは基本的にテスト受託によるサービス収入です。
ウエハテストとファイナルテストの双方から安定的に売上が発生し、車載やサーバー用の大口案件が増えると利益率が高まる構造となっています。
【理由】
高度な検査が必要な顧客ほど単価が上昇しやすく、不良率低減のメリットを実感しやすい分野ほど付加価値を認めてもらえるためです。
また、円安など為替の影響で連結換算額が上振れすることもあり、市場動向に合わせて売上が変動しやすい面もあります。
コスト構造
コスト構造は設備投資費や人件費が大きな割合を占めます。
テスト装置の定期的な更新やメンテナンスは不可欠であり、電力費などの固定費も無視できません。
【理由】
半導体テストは高い精度とスピードを同時に満たすために最新装置の導入が必要であり、それが競争力の源泉でもあるからです。
ただし大規模投資を行えば設備が高性能化し、より高付加価値の案件が取れる好循環につながりやすい側面もあります。
自己強化ループ
テラプローブは最新設備への投資と技術開発により高いテスト精度を確保し、顧客満足度を高め、それがさらなる受注拡大を呼び込む自己強化ループを持っています。
この流れが成り立つ背景には、大口顧客を中心に品質や信頼性への要求が高まっていることが挙げられます。
例えば車載向けでは安全性確保のために厳密な検査が求められ、テラプローブのように専門性と設備力を備えた企業がより多くの案件を受注しやすくなります。
そこで得た収益を再度研究開発や設備投資に回すことで、さらにテスト精度やスピードが上がり、顧客の製品競争力も高まります。
これが顧客との長期的パートナーシップを強化し、会社全体の事業基盤を固める好循環となっています。
採用情報
同社の初任給は公式な具体金額の公表は見当たりませんが、半導体業界の平均水準と同程度と考えられます。
休日休暇については年次有給休暇のほか特別休暇なども整備されており、技術者が働きやすい環境が整っています。
採用倍率の公表はありませんが、半導体テストの専門知識や装置オペレーションの経験が必要とされるため、エンジニア系人材の需要が高い傾向です。
株式情報
株式会社テラプローブは証券コード6627で上場しており、配当金は2023年12月期で1株当たり110円となっています。
株価は変動があるため、最新の株価は証券会社や金融情報サイトなどで確認が必要です。
半導体業界は市況の変動が大きいため、DRAMやサーバー用半導体の需給バランスによって株価も影響を受けやすい点が注意点といえます。
未来展望と注目ポイント
テラプローブは車載向け半導体の需要増や5G基地局・データセンターの拡大を背景に、今後も受託案件の増加が期待されます。
電気自動車の普及や自動運転技術の進化により、車載半導体は安全性と高性能を両立させる必要があり、それに伴いテスト精度もますます重要度を増します。
サーバー向けでもクラウドサービスやAI演算などの処理能力が求められ、高品質のDRAMやロジックICのテストニーズが高まると予想されています。
こうした環境下で同社は成長戦略として設備投資と研究開発を続け、顧客の多様なテスト要求をトータルでサポートする体制を強化する方針です。
またPTIグループとの連携によって、製造工程から後工程までの一貫受託が強化される可能性も高いでしょう。
市場拡大が続く分野を主力とする同社にとって、これからの技術革新や新規顧客の獲得がさらなる飛躍への鍵となるため、今後のIR資料や業績発表には注目が集まります。

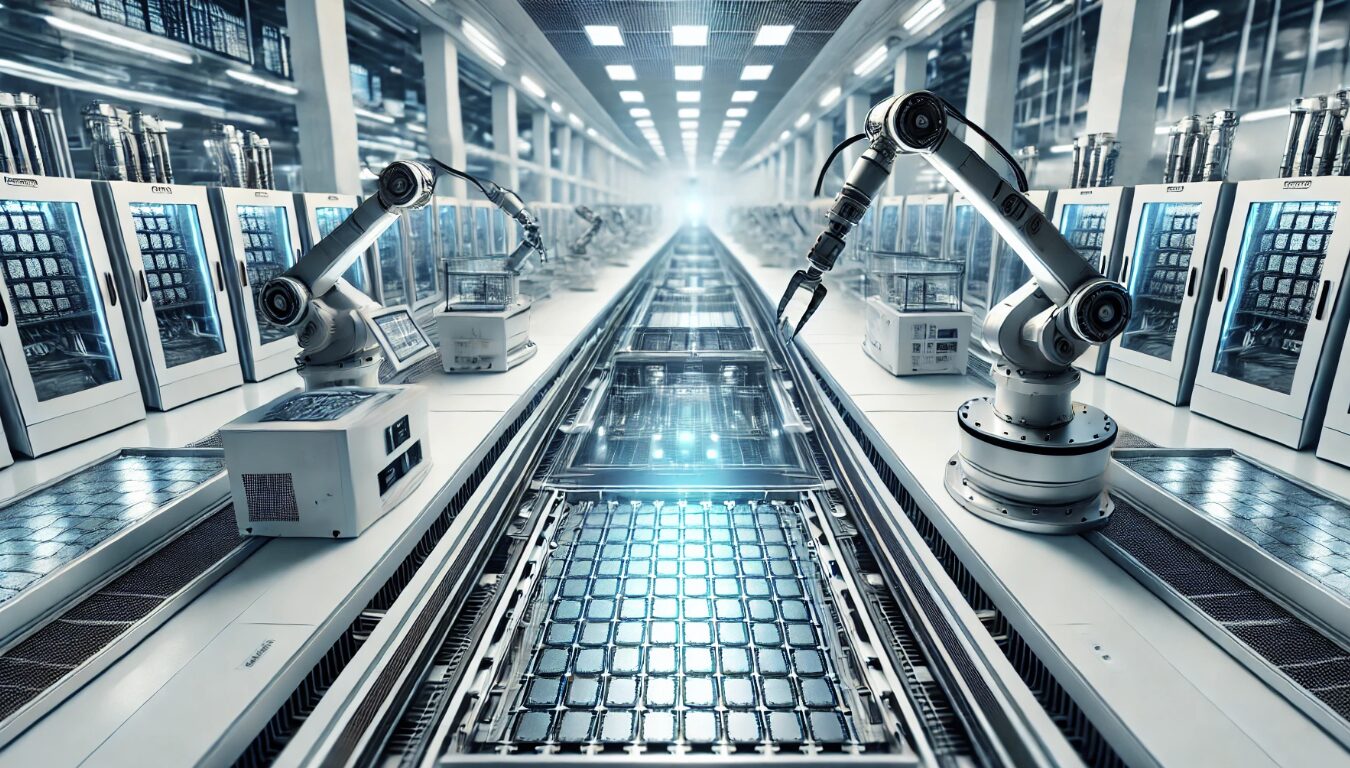


コメント