企業概要と最近の業績
株式会社トーホー
飲食店やホテル、病院などに食材を供給する、神戸市に本社を置く業務用食品卸の大手企業です。
「食」に関わる多様な事業を展開しており、全国に配送網を持つ業務用食品卸売の「ディストリビューター事業」が中核です。
また、プロ向けの食品スーパー「A-プライス」を運営する「キャッシュアンドキャリー事業」なども手掛けています。
2025年6月12日に発表された2026年1月期第1四半期の連結決算によりますと、売上高は600億5,000万円で、前年の同じ時期に比べて6.8%増加しました。
営業利益は10億円で、前年の同じ時期から19.5%の大幅な増加となりました。
経常利益は11億2,000万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は7億円となり、増収増益を達成しています。
主力のディストリビューター事業において、人流の回復やインバウンド需要の増加を背景に、主要顧客である外食産業向けの販売が好調に推移したことが業績を牽引しました。
【参考文献】https://www.to-ho.co.jp/
価値提案
外食産業を支援する幅広いサービスと多様な商品ラインナップ
全国の事業所ネットワークによる安定供給や品質管理
業務用調理機器や店舗内装に関するコンサルティングサポート
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食市場では食品だけを仕入れて終わりではなく、店舗設計や機器導入など、さまざまな工程が成功のカギとなります。
株式会社トーホーは卸売に限らず、その周辺領域にまで事業範囲を拡大することで、顧客企業に対する付加価値を高めたいという狙いがありました。
幅広いニーズを一括してサポートできるようになると、取引先との関係が深まり、長期的かつ安定的な契約につながることが期待できます。
また多角的なサービスをまとめて提供することで、単一サービスのみを提供する競合他社との差別化が可能になり、外食企業が必要とする多岐にわたる業務をワンストップで解決できる点が大きな魅力となっています。
主要活動
食品の調達と卸売および店舗での現金販売
物流網の運営と最適化
フードソリューションとしての調理機器や店舗設計支援
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食産業は商品開発や人材育成など多くの課題を抱えがちで、その一つひとつをサポートするサービスが求められます。
株式会社トーホーはまず食品卸売で事業基盤を確立した後、顧客の困りごとに合わせて関連サービスを拡充してきました。
これにより、食材の供給から運営支援までを一手に担うことができるようになり、他社では代替しづらい独自のポジションを確立しています。
業務用食品のディストリビューターとして長年蓄積したノウハウを生かし、物流コストの削減や商品提案力の向上など、顧客との関係を強固にする活動が中心となっています。
リソース
全国84事業所と海外拠点による広範なネットワーク
専門知識を持った人材と物流システム
多種類の業務用食材およびPB商品の企画開発力
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食産業向けの卸売を大規模に行うには、全国規模の物流網と多数の取り扱い商品が不可欠です。
外食企業は店舗の場所や業態によって異なる食材や設備を必要とするため、多彩な商品を常時そろえておく必要があります。
また、顧客企業が安心して取引できるよう、衛生面や品質管理に詳しい人材を揃えることが信頼向上につながります。
さらに独自開発のPB商品を扱うことで、仕入れコストを抑えると同時に差別化が図れるため、この開発力も重要なリソースとなっています。
パートナー
食品メーカーや加工業者との連携
配送や倉庫保管を請け負う物流企業との協力
外食産業の共同開発プロジェクトへの参加
【理由】
なぜそうなったのかというと、業務用食品には季節や地域によるバリエーションが多く、品質や価格帯もさまざまです。
株式会社トーホーは幅広いメーカーや業者と提携し、常に安定した品質と供給体制を確保するためのパートナーシップを築いてきました。
また店舗内装や調理機器の設計・導入にも専門企業とのコラボレーションが欠かせず、各種プロジェクトや商品開発の段階から外部パートナーと協力することで、総合的なサービスを提供できる体制を作り上げています。
チャンネル
ディストリビューターとしての直接取引と店舗販売(キャッシュアンドキャリー)
オンラインによる受発注システム
展示商談会や試食会などのリアルイベント
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食産業の顧客は大手チェーンから個人経営の小規模店まで幅広く、調達方法のニーズも多様です。
オンライン注文が便利なケースもあれば、実際に店舗で食材を手に取りたいと考えるオーナーもいます。
そこで株式会社トーホーは、ディストリビューターとして大口注文に対応しつつ、キャッシュアンドキャリー店舗やオンラインシステムを活用することで、あらゆる規模の飲食事業者にとって利用しやすいチャンネルを築いてきました。
さらに展示商談会を開き、新商品や調理機器を実際に見てもらう機会を作り出すことも、販路拡大に大きく貢献しています。
顧客との関係
展示商談会や料理講習会を通じたコミュニケーション
オンラインシステムや電話対応による丁寧なフォローアップ
新メニュー開発や店舗設計での共同作業
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食企業との信頼関係を築くためには、ただ食材を届けるだけでは十分ではありません。
メニュー開発や調理機器の利用方法など、より深いレベルの情報交換が求められます。
株式会社トーホーは定期的に展示商談会や講習会を行い、調理のノウハウや新商品情報を共有することで、顧客との接点を増やしています。
こうした場は新たな商談や長期的な関係強化にもつながるため、お互いにメリットを得られる関係性が築かれやすくなります。
顧客セグメント
全国チェーン店やホテル、居酒屋や給食業態など幅広い層
個人経営の飲食店や地域密着型の小規模店舗
テーマパークなど独自のニーズを持つ業態
【理由】
なぜそうなったのかというと、外食産業には多岐にわたる形態があります。
ファミリーレストランのチェーン店だけでも大量の食材が必要ですし、ホテルやテーマパーク向けには高品質な食材や多様な調理機器が求められます。
一方で個人経営や地域密着型の飲食店では、コストや店舗運営の効率が大きな課題となります。
株式会社トーホーは多様な商品とサービスを扱い、それぞれのセグメントに応じた提案ができるようになりました。
こうした幅広い顧客基盤により、一つの業態が不調でも他のセグメントで業績を補えることが、企業の安定性にもつながっています。
収益の流れ
食品や関連商品の販売収益
店舗設計や調理機器、情報システムの導入支援に伴うサービス収益
PB商品の開発と販売による差別化収益
【理由】
なぜそうなったのかというと、業務用食品卸売だけでは価格競争の影響を受けやすく、収益が不安定になりがちです。
そこで株式会社トーホーはフードソリューション事業やPB商品の販売を組み合わせ、多角的な収益源を持つ体制を確立しました。
特にPB商品はコストをコントロールしやすく、顧客企業に独自の価値を提案できるため、価格だけに縛られない強みがあります。
また店舗設計や調理機器の導入支援など、コンサルティング要素のあるサービスを提供することで、食品卸売とは異なる付加価値を生み出し、収益の安定と拡大を同時に実現しているのです。
コスト構造
仕入れコストや物流費
人件費と店舗運営に関する経費
PB商品の開発費用や品質管理のための投資
【理由】
なぜそうなったのかというと、全国規模で事業を展開する以上、物流網や人材確保にかかるコストは避けられません。
特に外食産業は季節変動やトレンドの影響を受けやすいため、タイムリーな供給体制と高品質を両立するには、それなりのコスト投下が不可欠です。
またPB商品の開発や品質管理の体制を強化することは、将来の競争力を高めるうえでの重要な投資となります。
こうしたコストをどう最適化しながら収益を伸ばすかが、株式会社トーホーの大きな経営課題といえます。
自己強化ループ(フィードバックループ)について
株式会社トーホーが成長を続ける背景には、事業を回すうちに得た利益を再投資し、さらにビジネスを拡大していく好循環があります。
たとえばPB商品の開発に力を入れることで、外食企業にとって独自性の高い商品を提供できるようになり、結果として販売数が伸びます。
この売上増加がさらに開発資金となるため、商品の改良や新商品投入を続けられます。
同時に展示商談会を活用することで、実際に商品を手にしたり試食したりする機会を増やし、顧客企業との信頼関係を深めながら新規開拓も推進します。
こうした取り組みが繰り返されることで収益が安定し、さらなる投資余力が生まれ、より幅広いサービスを提供できるようになります。
このような自己強化ループは、コロナ禍からの回復をいち早く実感できた今だからこそ、次の成長に向けて大きな武器となるでしょう。
採用情報
初任給や年間休日数、採用倍率などの具体的な数字は公表していないようです。
ただし外食産業向けの総合支援を行う企業として、物流や営業、商品企画、店舗設計など多方面の職種で幅広く人材を募集しています。
食ビジネスに興味がある方や、地域社会に密着した活動に関心のある方にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
株式情報
銘柄は株式会社トーホーで証券コードは8142です。
2024年1月期の配当金は年間90円を実施し、2025年1月期は110円を予定しています。
1株当たり株価は2023年9月6日時点で3,080円となっており、外食産業の需要回復やインバウンド需要の拡大に伴い、株主への還元意識も高めていることがうかがえます。
未来展望と注目ポイント
今後は観光再開と外食業界のさらなる需要拡大が期待されるなか、株式会社トーホーのビジネスモデルはより強みを発揮すると考えられます。
特に物流費や人件費の上昇をいかに抑制しながら、高品質かつ多様な食材やサービスを提供できるかが大きな焦点になります。
同時に内装工事や調理機器導入など、外食企業にとって欠かせないソリューションをトータルでサポートできる体制は、競争力を強化する重要な要素となります。
またPB商品の開発や展示商談会の拡充によって、取引先との信頼関係と売上の両面でさらに強固な基盤を築く可能性があります。
外食市場は世界的にも回復基調にあるため、海外拠点を活用したグローバル展開も十分に見込めるでしょう。
こうした多角的な取り組みがどのように結実するか、そしてそれを支える経営の舵取りが、これからの同社の成長を左右する大きな鍵となりそうです。
今後のIR資料や決算情報にも注目が集まっています。

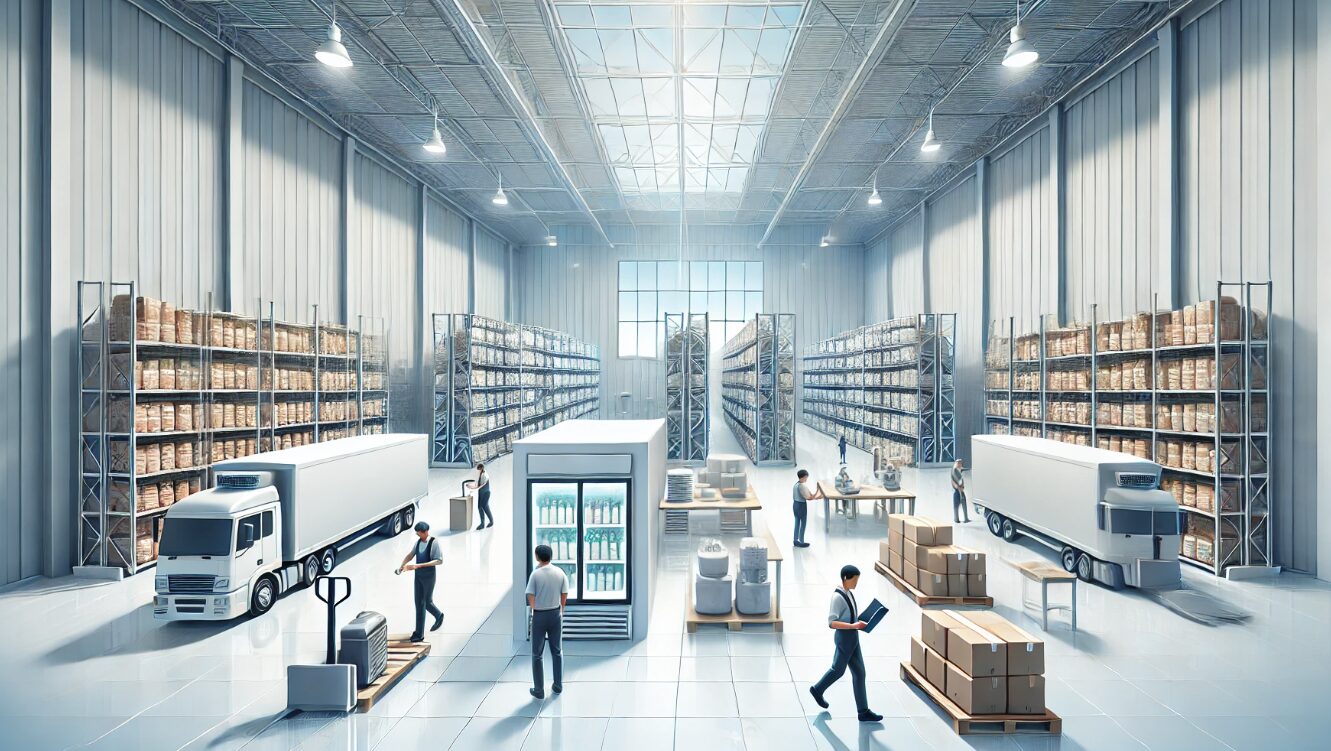


コメント