企業概要と最近の業績
株式会社ヨロズ
当社は、自動車の乗り心地や走行安定性を支えるサスペンション部品を専門に開発・製造しているメーカーです。
サスペンションを構成するサブフレームやサスペンションアームといった骨格部品を主力としており、プレス加工や溶接、塗装までを一貫して手がける高い技術力が強みです。
日本国内をはじめ、米州、中国、タイ、インドネシアなど世界各地に開発・生産拠点を持ち、グローバルに自動車メーカーへ製品を供給しています。
2026年3月期の第1四半期(2025年4月1日~6月30日)の連結業績は、売上収益が458億100万円(前年同期比10.7%増)、営業利益が27億6100万円(同149.9%増)となりました。
税引前四半期利益は23億1600万円(同281.4%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は13億8800万円(同289.1%増)となり、大幅な増収増益を達成しました。
決算短信によると、主要な市場である米州や日本で自動車生産台数が回復したことに加え、為替相場が円安に推移したことが増収に貢献しました。
利益面では、増収効果に加え、世界各地域での合理化活動やコスト改善が進んだ結果、大幅な増益に繋がったと報告されています。
価値提案
サスペンション部品の高品質とコスト競争力を両立させ、メーカーが求める軽量化や安全性にも応えています
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーとの長年の協力体制や、トヨタ生産方式の導入による無駄の削減が背景にあります
高い品質基準をクリアする技術力に加え、効率的な生産プロセスを確立していることで、ユーザーにとってコストパフォーマンスのよい部品を提供できるようになりました
とくに、サスペンション周辺は安全面での規制が厳格化しているため、高い信頼性を担保することが差別化につながっています
これによりメーカー側からの信頼を獲得し、安定した受注体制とブランド力を手にすることになりました
主要活動
・製品設計や生産工程の最適化をはじめ、新車モデルへの部品提案も行っています
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーとの協同開発のなかで、車種ごとの特性に合わせた設計が重要となるからです
メーカーは燃費向上や安全性強化に取り組んでおり、それに連動してヨロズが早期段階から設計に関わることで、より効果的な部品を提供できます
また、生産工程の最適化によって利益率を高め、新たな開発投資や設備更新に資金を回しやすくなりました
特にサスペンション分野は車体剛性に直結し、乗り心地や安全性に大きく影響するため、細かな部品調整が必要とされます
こうしたノウハウをいち早く反映できる組織体制が競争優位の源泉となっています
リソース
・高度な生産技術と熟練した人材、そして国内外に整備された生産設備
【理由】
なぜそうなったのかというと、サスペンション部品は高い精度と耐久性が求められるため、熟練者の経験と最新技術の両方が欠かせません
これまでに培った製造ノウハウを継承しながら、自動化設備やデジタル管理システムを導入することで作業効率を上げています
さらに、生産拠点の拡充や改修に投資を行うことで、グローバルな自動車市場の需要変動に柔軟に対応できる体制をつくっています
こうしたリソースの蓄積が、生産コストの低減やリードタイムの短縮といった面で大きな強みとなり、メーカーからの継続的な発注を支える背景にもなっています
パートナー
・国内外の自動車メーカーや原材料サプライヤーとの緊密な連携
【理由】
なぜそうなったのかというと、日産系列から独立した後、多方面の自動車メーカーとの取引拡大を図る過程で、長期的に協力できるパートナーシップの重要性が増しました
とくにトヨタ自動車など、規模が大きく品質要求の厳しいメーカーと協力することが、ヨロズの技術力向上にもつながっています
また、鉄鋼やアルミなど原材料を扱うサプライヤーとの連携を強化し、安定した供給と価格競争力を得ることで、部品の品質とコスト面を両立させることができました
このようにパートナー関係を幅広く築くことで、企業規模を超えたノウハウの共有も進んでいます
チャンネル
・主にOEMという形で、自動車メーカーに直接部品を納入
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車部品業界では車種ごとのカスタマイズが大きいため、メーカーとの直接的なやりとりが不可欠です
サスペンション部品は車両設計の早期段階から検討されるので、ヨロズが直接コミュニケーションを取ることで開発効率を上げることができます
これにより、メーカー側の細やかな要望や最新仕様をスピーディーに反映できる利点があります
さらに、メーカーの生産スケジュールに合わせた納品が必要となるため、ダイレクトなチャンネルがサプライチェーン全体の安定にも寄与しているのです
顧客との関係
・技術サポートと長期的な信頼関係を重視
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカーは、車の安全性と性能に直結する部品に対して厳しい品質基準を設けています
ヨロズはこれをクリアするために、設計段階から共同開発のような形で関わり、必要に応じて技術サポートや改善提案を行います
このように密接な連携体制を築くことで、長期にわたる取引が実現しやすくなります
部品不良やリコール対応などで連携が強化される場合も多く、トラブルシューティングの際に素早く対応できることでメーカーからの評価も高まります
結果として安定的な受注につながり、業績を下支えしています
顧客セグメント
・国内外の自動車メーカー全般
【理由】
なぜそうなったのかというと、日産系列から独立したことにより、特定メーカーへの依存度を下げる必要が高まりました
その結果、トヨタや海外メーカーへのアプローチが進み、多様な顧客セグメントを獲得することで安定した売上を得られるようになりました
さらに、電動化やハイブリッド化などの技術動向に合わせて、新興のEVメーカーにも対応ができる柔軟性が求められています
こうした分散化した顧客構造は、市場の変化や特定メーカーの不調時でもリスクを減らすことができる点で重要です
幅広い顧客セグメントを獲得し続ける力が、ヨロズの成長を後押ししています
収益の流れ
・サスペンション部品の販売収益
【理由】
なぜそうなったのかというと、自動車メーカー向けに部品を出荷し、その対価として安定的な収益が生まれる構造です
一般消費者向けに直接販売するわけではなく、OEM部品という形でメーカーに納品するため、大口取引で利益を計上しやすくなっています
一方で、車両の販売台数やモデルチェンジのタイミングなど、メーカーの都合に収益が左右されることもあるため、複数のメーカーを取り込むことが戦略上大切になります
生産コストの削減と品質管理を徹底することで、利益率の改善に成功し、一定のキャッシュフローを確保できる体制を築き上げました
コスト構造
・原材料費や人件費、生産設備の維持費が中心
【理由】
なぜそうなったのかというと、サスペンション部品の製造には鉄鋼やアルミなどの素材が必要で、これらの価格変動がコストに大きく影響します
また、熟練した技術者の育成や現場での作業にも人件費がかかります
ヨロズはトヨタ生産方式に学び、不要な在庫やムダを削減することで生産効率を向上
設備投資も必要最低限で抑えつつ、必要に応じてラインを増強するなど柔軟な対応を行っています
こうした徹底したコスト管理により、利益を確保しながらも品質基準を落とさない手法が評価され、着実な成長の土台を作っています
自己強化ループ
自動車メーカーからの信頼が高まることで、ヨロズが得られる受注は増え、それに伴って設備投資や人材育成などのリソース強化が進みます
生産効率が上がればコストが下がり、品質も向上しやすくなり、メーカー側の満足度がさらに高まります
すると新規車種や新規顧客からの依頼が増え、会社全体の業績が良くなってさらなる拡充投資につながるのです
特にトヨタ生産方式は、現場での継続的な改善活動を促す仕組みが整っているため、フィードバックによる改良が繰り返し行われます
この自己強化ループによって、企業全体としての競争力がさらに高まる構造になっています
こうしたプラスの循環を絶やさないためには、人材のモチベーション維持や技術継承が欠かせない重要課題となります
採用情報
株式会社ヨロズでは、初任給の具体的な金額は公表されていませんが、業界水準と大きく離れていないと推測されています
休日は年間120日程度が見込まれ、ワークライフバランスにも配慮した体制を整えています
採用倍率は公表されておらず詳細は不明ですが、自動車部品に関する技術職を中心に募集していると考えられます
生産技術や品質管理など専門知識を活かせる領域で、ヨロズ独自の生産ノウハウを学べることも魅力といえます
株式情報
銘柄は株式会社ヨロズで証券コードは7294です
2024年3月期の年間配当金は1株当たり50円が予定されています
自動車部品業界の市場動向や各メーカーの生産計画の影響を受けやすい面はありますが、高配当であることは投資家にとっての魅力につながる部分です
株価については時期や市況によって変動が大きいため、定期的に確認することが大切と考えられます
未来展望と注目ポイント
自動車業界は電動化や自動運転などの新技術が加速しており、サスペンション部品にも軽量化や複合素材の活用が一段と求められています
ヨロズはこれまでに培った技術力とトヨタ生産方式の効率性を活かし、こうした新しい需要にも対応を進めています
特に海外市場では電気自動車の普及が急速に進んでいるため、グローバルな視点で開発リソースを投じる意義が増しているのです
また、日産系列から独立した経験を活かし、多方面の顧客を取り込む営業戦略を展開することで、安定収益を確保しながら新規事業にも挑戦しやすい環境が整いつつあります
今後はさらなる研究開発投資や新興国での生産拠点強化などが見込まれ、自動車の未来像が変わるなかでどのように成長していくのかが注目されるでしょう
競争の激しい業界のなかで、ヨロズの持つ技術力と効率化ノウハウが大きな武器となり、新しい時代のモビリティを支える存在として期待が高まっています

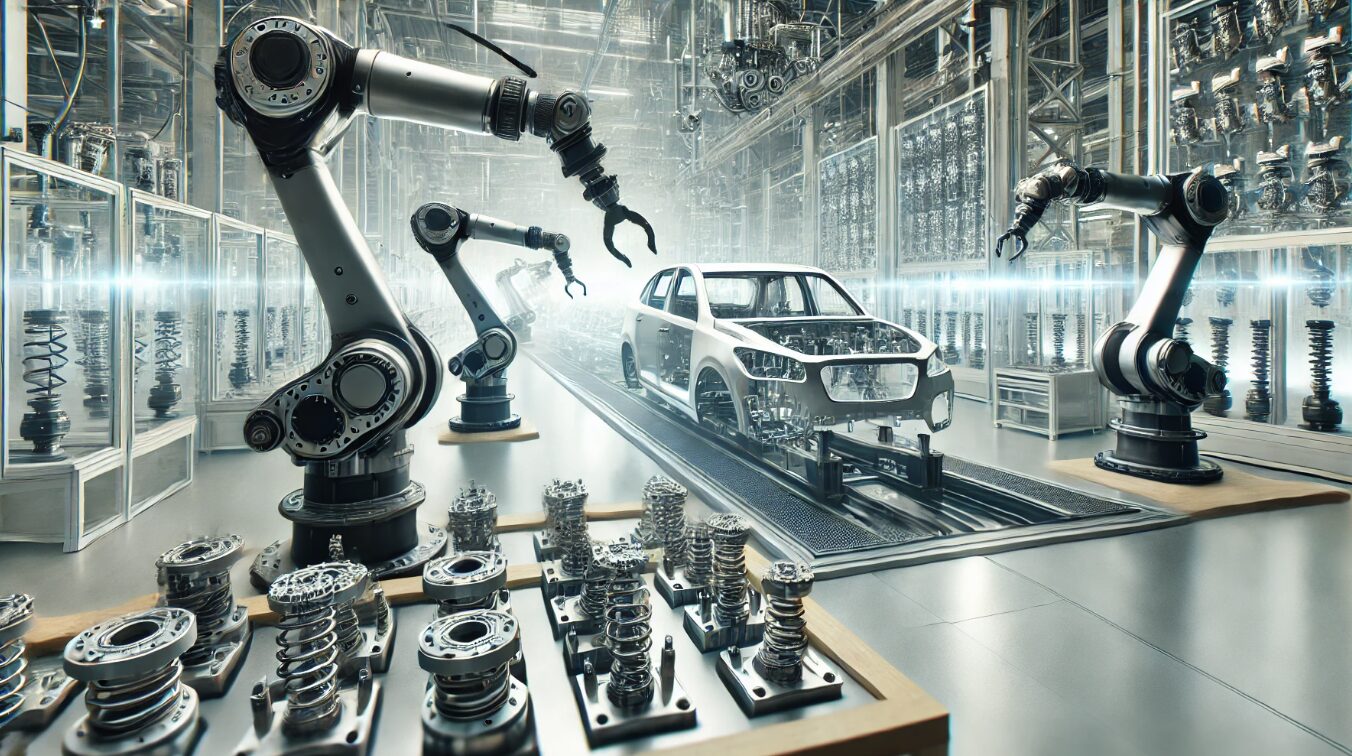


コメント