企業概要と最近の業績
株式会社ライトアップ
当社は、「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンを掲げ、中小企業の経営支援を手掛ける企業です。
主力事業として、国や地方自治体が提供する補助金や助成金の申請をサポートするコンサルティングサービスを展開しています。
また、ITツールの導入を支援するDX支援サービスや、事業承継の支援なども行っています。
会計事務所や金融機関といった専門家と提携し、その先にいる全国の中小企業へサービスを届けるという独自のビジネスモデルが特徴です。
2025年8月8日に発表された2026年3月期第1四半期の決算短信によりますと、売上高は5億2,400万円となり、前年の同じ時期に比べて10.9%の減収となりました。
営業利益は1億1,900万円で前年同期比25.6%減、経常利益も1億1,900万円で同26.1%減となり、減収減益という結果でした。
これは、新型コロナウイルス感染症に関連した大規模な補助金制度が終了したことなどが影響し、主力の補助金・助成金コンサルティングの売上が減少したことが主な要因です。
【参考文献】https://www.writeup.jp/
価値提案
株式会社ライトアップは、中小企業が抱える資金繰りや人材不足といった課題を、AIやITツールを活用して黒字化へ導くことを最大の価値提案としています。
例えばAIを使った経営診断や補助金情報の自動提案など、企業の成長を後押しするソリューションを提供している点が大きな強みです。
【理由】
国内の中小企業が抱える構造的な課題を解決し、経済を底上げする必要性の高まりが挙げられます。
AI研修やコンサルティングを通じて経営者が短期間で成果を実感できる仕組みを整えたことで、多くの企業から信頼を獲得し、継続的なパートナーシップを築いているのです。
主要活動
同社の主要活動には、AI研修とコンサルティングが含まれます。
研修では経営者や従業員がAIの基礎を理解し、自社の業務効率化や新たなビジネスチャンスを見出せるよう支援しています。
またITツールの共同開発・仕入れを行い、導入しやすい価格帯と機能を実現することで、多忙な中小企業の経営者にも安心して利用してもらえるサービスを提供しています。
【理由】
こうした活動の中心にAI研修やコンサルが置かれているのは、自前でAI技術を開発するのが難しい中小企業のニーズを的確に捉えたからです。
時間に余裕のない経営者でも短期間で成果を出せるようなプログラムを整えることで、高い顧客満足度とリピート受注につながっています。
リソース
同社には約150名の従業員と13万社に及ぶ顧客データベース、さらに独自開発のAIソリューションという強力なリソースがあります。
社内にはITやコンサル分野に精通した人材が多く在籍しており、顧客ごとに最適な研修プログラムやコンサルサービスをカスタマイズできる点が評価されています。
【理由】
こうしたリソースが充実した背景には、長年にわたる中小企業支援の実績があり、蓄積されたノウハウをもとに顧客データベースを拡充してきたことが大きいです。
AIソリューションの開発や更新を続けることで、常に最新かつ多角的なサポートを提供し、顧客企業の信頼獲得につなげています。
パートナー
全国の金融機関や自治体、IT企業との幅広い提携が同社の強みです。
金融機関との連携によって企業の資金繰りサポートや補助金の活用支援がスムーズに行えるだけでなく、自治体との協力で地域経済の活性化にも寄与しています。
【理由】
多くの中小企業は経営改善のために公的支援や金融サービスが欠かせないからです。
またIT企業との連携では最新技術をいち早く取り入れ、研修やコンサルティングの内容を常にアップデートすることで付加価値を高めています。
これによりサービス内容が充実し、より多くの中小企業にアプローチできる体制が整っているのです。
チャンネル
オンラインセミナーやウェブサイト、各パートナー企業を通じた販路を活用して、同社は顧客との接点を拡大しています。
特にオンラインセミナーは、中小企業の経営者や担当者が場所を選ばず参加できるため、需要が高まっています。
金融機関の窓口で同社のサービスを案内してもらうケースもあり、資金調達が必要な企業と直接つながる機会が生まれている点は大きなアドバンテージです。
【理由】
多彩なチャンネルを持つに至った背景としては、中小企業の業種や立地条件によってニーズや課題が異なることから、一つのチャネルだけでは対応しきれないという現実があります。
顧客との関係
AI研修やコンサルは単発で終わるのではなく、継続的なフォローアップを実施することによって、顧客との長期的な関係性を築いています。
AIを導入してからが本番とも言え、実際に運用する中で新たな疑問や課題が出てくるため、同社が定期的に情報提供や追加コンサルを行っているのが特徴です。
【理由】
なぜこのような形をとるかと言えば、中小企業が成長軌道を維持するために継続的なサポートが必須だからです。
こうした伴走型の支援が企業の満足度を高め、紹介やリピート受注へとつながっています。
顧客セグメント
主な顧客層は全国の中小企業ですが、特に製造業やサービス業など、AIを導入する効果が高い業種にも積極的にアプローチしています。
またデジタル化が遅れている企業ほど導入効果が大きいため、そのような企業に対して手厚いサポートを提供していることも特徴です。
【理由】
こうした幅広いセグメントをターゲットにできる理由は、13万社を超えるデータベースと長年の中小企業支援の経験があるからです。
一社一社の状況に応じたカスタマイズができるため、最適なAI活用案を提示しやすく、多様なニーズを満たせる点が大きな強みになっています。
収益の流れ
同社の収益は、大きく分けてAI研修・コンサルティングとITツールの販売に依拠しています。
研修やコンサルでは契約企業の数や期間、研修回数などに応じて料金を得られるため、継続的に利用してくれる企業が増えるほど収益は安定します。
一方、ITツールの販売では、開発元との共同プロジェクトによりコストを抑えながら、中小企業が導入しやすい価格帯で提供できるよう工夫しています。
【理由】
こうした二本柱の収益構造がなぜ有効かというと、AIツールのアップデートや追加研修など、新たな顧客ニーズに対応する形で追加料金が発生し、持続的な収益拡大が期待できるからです。
コスト構造
コンサルや研修で活躍する人材への人件費、AIやITツール開発・仕入れコスト、さらには研修を運営するための費用が主なコスト構造となっています。
AI分野の技術革新は速いため、常に最新の知識を持った人材を育成・確保する必要があり、人件費が比較的高い割合を占めるのが特徴です。
しかし共同開発や仕入れのスキームを整えていることで、ITツールの単価を抑え、中小企業にも手が届きやすい価格設定を実現しています。
【理由】
こうしたコストバランスを整える仕組みがあるからこそ、研修やコンサルの品質と価格競争力を両立させることが可能になっています。
自己強化ループ
株式会社ライトアップが提供するAI研修やコンサルティングは、導入企業の成功体験を通じて次々と新規案件を呼び込む自己強化ループを生み出しています。
AI導入によって成果を得た企業は、業務効率の向上やコスト削減だけでなく、補助金の申請や新規プロジェクトに挑戦するなど、さらなる成長機会をつかむことができます。
その結果として評判が高まり、パートナー企業や既存顧客からの紹介につながり、新たな受注が発生します。
さらに、現場の声をフィードバックすることで研修プログラムやITツールをアップデートし、サービスの質を高めていく好循環が生まれるのです。
こうした相乗効果によって顧客数が増え、データが蓄積されるほどAIの分析精度や提案の幅も広がり、同社の強みが一層強固になります。
採用情報
同社の初任給は月給21万円となっており、年間休日数や採用倍率の詳細は公表されていません。
未経験の人材であっても研修制度を活用しながらスキルを身につける機会があり、ITやAI分野の知識をこれから伸ばしていきたい方には魅力的な環境といえます。
実際に研修やコンサル業務を通じて、中小企業支援のノウハウを幅広く学べるため、人材育成に力を入れる企業を探している方にとっても大きなチャンスです。
株式情報
株式会社ライトアップの証券コードは6580で、2025年3月期の配当金は1株あたり16.89円が予想されています。
2025年2月17日時点での株価は1株あたり1,692円で推移しており、AI関連サービスやITツールの展開による成長性が投資家から評価されているとみられます。
中小企業支援という安定需要とAIビジネスの拡張性が組み合わさっていることから、今後も注目される銘柄の一つとなりそうです。
未来展望と注目ポイント
今後はAIやITを活用したサービスの需要がますます高まることが予想されるため、株式会社ライトアップにとっては大きなチャンスが続くと考えられます。
特に国内の中小企業では、人手不足やデジタル化の遅れが深刻化しており、AI導入による業務効率化や売上拡大の期待が一段と高まっています。
同社はこれまで培ってきたAI研修やコンサルティングのノウハウをさらに強化し、業種や地域に合わせた専門的なサービスを展開することで、顧客基盤を一層拡大する可能性があります。
また、金融機関や自治体との連携を強めることで、補助金情報や資金繰りサポートを含むトータルソリューションとしての提供体制が整えば、顧客企業の経営負担を減らすと同時に同社の収益源も広がるでしょう。
これらの取り組みにより、同社は業績拡大と社会への貢献を両立させ、成長戦略を着実に推進していくと期待されます。

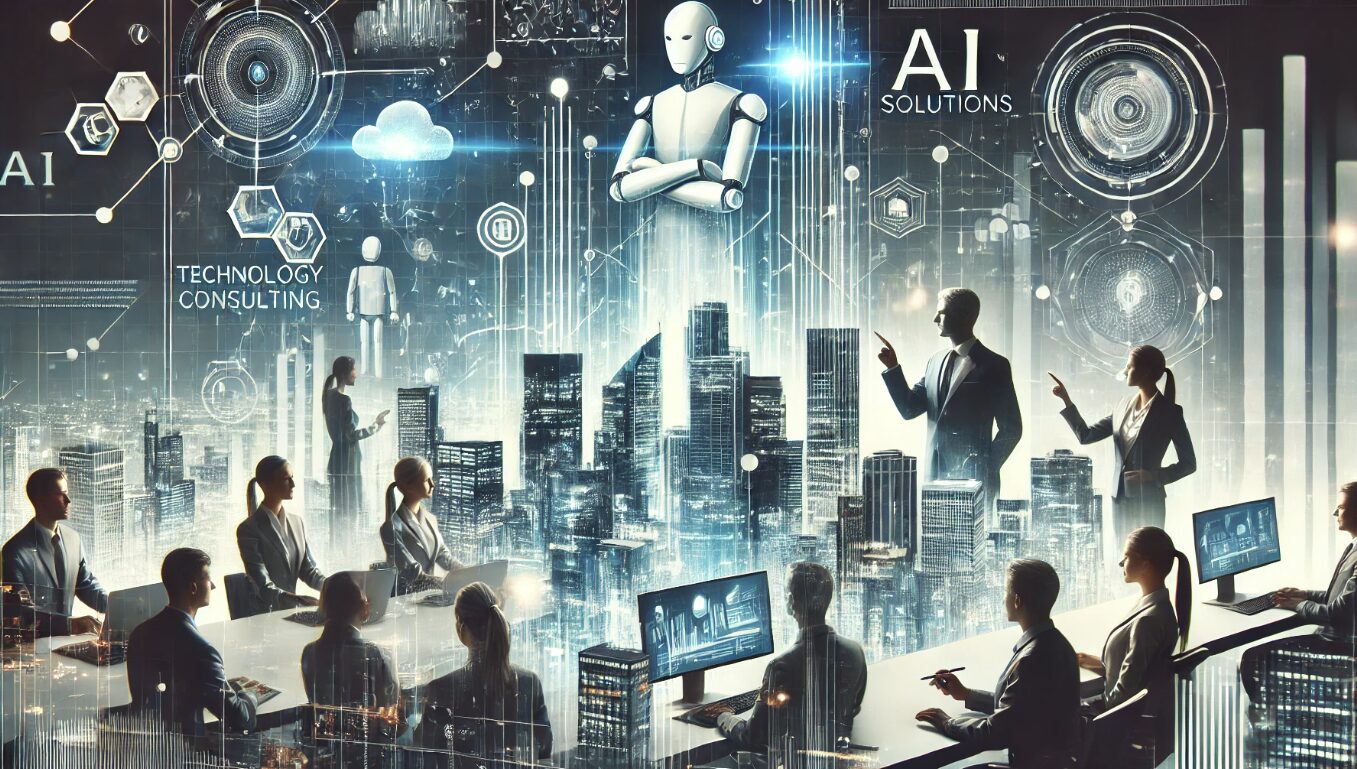


コメント