企業概要と最近の業績
株式会社MDB
企業向けに、事業開発や研究開発、マーケティング活動などに必要なビジネス情報を提供する会社です。
主力サービスは、会員制のビジネス情報検索サービス「MDB Digital Search」です。
このサービスを通じて、国内外の様々な文献や調査レポートから収集・整理した市場動向や技術情報などを、顧客企業に提供しています。
情報の専門家として、企業の意思決定やイノベーション創出を支援しています。
2025年8月7日に発表された2026年3月期第1四半期の決算によりますと、売上高は4億500万円で、前年の同じ時期に比べて4.8%増加しました。
営業利益は1億800万円で、前年の同じ時期から7.2%の増加となりました。
経常利益は1億1,000万円、純利益は7,500万円となり、増収増益を達成しています。
企業のDX推進や新規事業開発に向けた情報収集ニーズの高まりを背景に、主力の会員制サービスの契約社数が順調に増加したことが業績に貢献しました。
価値提案
株式会社エム・デー・ビーは社会インフラを支えるSIサービスと、地図情報やIoTなどを活用したデジタルコンテンツサービスを提供しています。
金融や官公庁といった公共性の高い分野を中心に、大規模かつ高品質なシステムを作り上げることで顧客企業の課題解決を支援している点が大きな特徴です。
さらに地図情報やブランディングデザインを組み合わせることで、リアルとデジタルを結びつけた新しい価値を提案しています。
【理由】
同社のエンジニアが幅広い技術スキルを持ち、かつ社会インフラに精通していることから、多角的なニーズに応えられるビジネスモデルが自然に形成されました。
また官公庁や金融機関といった信頼性が重視される分野での成功体験が、このような価値提案を可能にしたと考えられます。
主要活動
主にシステム開発や運用保守を行うSIサービスのプロジェクトが中心となっています。
銀行や通信、公共事業など重要度の高い業務システムを手がけるため、要件定義から運用・保守まで一貫したサービス提供をしている点が強みです。
さらにデジタルコンテンツ事業では、地図情報の加工やIoTプラットフォームの設計、ブランディングデザインなど多様なクリエイティブ活動も展開しています。
【理由】
社会インフラ系の案件では長期安定的な取引が見込める一方、新しい技術やデザインへの対応が必要とされる時代背景があります。
両軸をうまく組み合わせることで、顧客の要望に幅広く応え、リピート契約や追加プロジェクトを獲得しやすい体制を築いた結果だといえます。
リソース
多様な業界知識と高度な技術スキルを持つ人材が最大のリソースです。
金融や官公庁向けのシステム開発には厳密なセキュリティ要件や品質基準が求められるため、こうした分野の経験を積んだエンジニアやプロジェクトマネージャーが豊富に在籍しています。
さらに地図情報やIoTに精通したクリエイティブ人材もそろえ、技術面とデザイン面の両方をカバーしている点が特長です。
【理由】
SI事業で長年培われたノウハウに加え、新たな市場ニーズに応えるために積極的な採用と教育を行ってきたことが背景にあります。
専門分野に特化したスキルだけでなく、幅広い業種への対応ができる人材育成を進めた結果、リソースの厚みが増したと考えられます。
パートナー
金融機関や官公庁、通信や流通など、社会基盤を担う大手企業との協業や取引関係が主なパートナーです。
要件定義やプロジェクト計画の段階から綿密に連携することで、システム開発の成功率を高め、長期的な信頼関係を築いています。
また他社のIT企業やデジタルコンテンツ制作会社との協業も行い、それぞれの強みを活かしたサービス展開をしています。
【理由】
社会インフラを支える案件には高い信頼性と専門知識が求められるため、一社単独ではカバーしきれない部分が出てきます。
そのため、官公庁や大手企業からの信頼を獲得したうえで、補完的な技術を持つ企業ともパートナーシップを結ぶ必要があり、それが現在の形につながっています。
チャンネル
顧客との接点としては直接営業が中心ですが、ウェブサイトや紹介による案件獲得も増えています。
大手企業を対象とすることが多いので、深耕営業による関係強化が重要視されています。
さらに既存顧客からの口コミや実績紹介が新たなプロジェクト獲得につながるなど、自然発生的なチャンネルも機能しています。
【理由】
SIサービスはカスタマイズ性が高く、導入企業の信頼がとても大切です。
そこで実績のある顧客への継続営業と、その顧客からの評価をベースとした営業スタイルが確立されました。
大手企業同士の口コミは影響力が大きく、ここにウェブ活用を加えたことで、より幅広いチャンネルが築かれたのです。
顧客との関係
カスタマイズ開発の多いSI事業では、顧客と二人三脚で開発を進める場面が多く、自然と長期的な信頼関係が築かれます。
納品後も運用保守を担当し、追加機能やシステム改修などの要望に応じて柔軟に対応することで、リピート契約へつながりやすいのが特徴です。
【理由】
社会インフラ系の案件はシステムの寿命も長く、一度導入したら継続的なメンテナンスが必要になります。
そのため、納品して終わりではなく、継続サポートを重視するスタイルに自然と移行した結果、長期的かつ安定的な顧客関係が形成されました。
顧客セグメント
金融や官公庁、通信、流通など大手企業や公共機関が主な顧客です。
業界特有のセキュリティ要件や大規模なトランザクション処理にも対応できる体制を整えているため、こうした大口顧客からの依頼が多く集まります。
また、新しい取り組みとしてIoTや地図データを活かし、中小企業や自治体向けのソリューション提供にも力を入れ始めています。
【理由】
同社の高度な技術力や厳格な品質管理が評価されることで、最初は比較的大きな案件を受注しやすい環境が整いました。
そこから官公庁や金融機関での実績を積み重ね、信頼を得ることで他の大手企業へと口コミが広がり、現在の顧客層が固まったと推測されます。
収益の流れ
プロジェクトごとに発注を受けるSIサービスの契約収入がメインです。
受託開発ではプロジェクトの規模や期間に応じて売上が変動しますが、大手顧客の案件が多いため一定の安定感があります。
さらにデジタルコンテンツサービスでは、地図関連サービスのライセンス収益や運用サポート、ブランディングデザインの制作費用など複数の収入源を持っています。
【理由】
もともと受託開発を中心としたSIビジネスモデルがベースにありましたが、継続的な収益を増やすために自社のコンテンツやサービスを作る方向へも進みました。
結果として、ライセンス型やサブスクリプション型のビジネスモデルも取り入れ、安定的かつ多角的な収益源を確保することにつながっています。
コスト構造
最大のコストは人件費です。
特に高度なスキルを持つエンジニアやプロジェクトマネージャーを確保するためには、相応の人件費が発生します。
またシステム開発に伴うソフトウェアライセンスやテスト環境の設備投資、案件獲得のための営業費用も大きな割合を占めます。
【理由】
技術力重視のビジネスモデルである以上、優秀な人材の採用と育成が欠かせません。
そのための教育費や働きやすい環境整備への投資が不可欠となり、コスト構造の中で人件費や関連費用が最も大きくなるのは自然な流れです。
自己強化ループ(フィードバックループ)について
株式会社エム・デー・ビーでは、優秀な人材の育成が事業拡大につながり、さらに顧客満足度を高めることでリピート契約や新規顧客の獲得につながるという好循環が生まれています。
具体的には、社員の技術スキル向上や資格取得を支援し、難易度の高いプロジェクトへの挑戦を促すことで、開発力と提案力を強化します。
その結果、高品質な成果物を提供できるようになり、金融や官公庁など信頼性を重視する顧客からの評価が高まります。
こうした実績をもとに新規案件が入り、会社としての売上が上がれば、さらなる人材投資が可能になります。
これが連鎖的に進むことで、社員と企業の成長が相乗的に高まる自己強化ループを形成しているのです。
採用情報と株式情報
同社の初任給や平均休日、採用倍率については現時点で詳しい情報が公開されていません。
ただし、IT人材へのニーズが高い中で幅広い事業領域を持っているため、今後も人材投資を積極的に行うことが予想されます。
応募を検討する際には最新の情報収集が必須でしょう。
株式は東京証券取引所のTOKYO PRO Marketに上場しており、銘柄コードは5594です。
配当金や1株当たりの株価についても詳細は未公開とされています。
同市場は開示が限定的な場合も多く、投資家の方はIR情報を注視する必要があります。
未来展望と注目ポイント
今後は国内外でさらに進むDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れに合わせて、株式会社エム・デー・ビーのビジネス拡大が期待されます。
特に官公庁や金融領域はデジタル化の需要が高く、同社が得意とする大規模システム開発や運用ノウハウは引き続き重宝されるでしょう。
また、地図関連サービスやIoTなどの先端技術を活かした事業がどこまで伸びるのかも注目点となります。
さらに、海外事業への展開や新しいパートナー企業との協業によって、新市場を切り開く可能性も考えられます。
こうした成長戦略を進めていくうえでは、人材の確保や技術力の向上が不可欠です。
安定性と先進性をあわせ持つ同社の取り組みが、これからどのような成果を生み出すのか、長期的な視点で見守りたいところです。

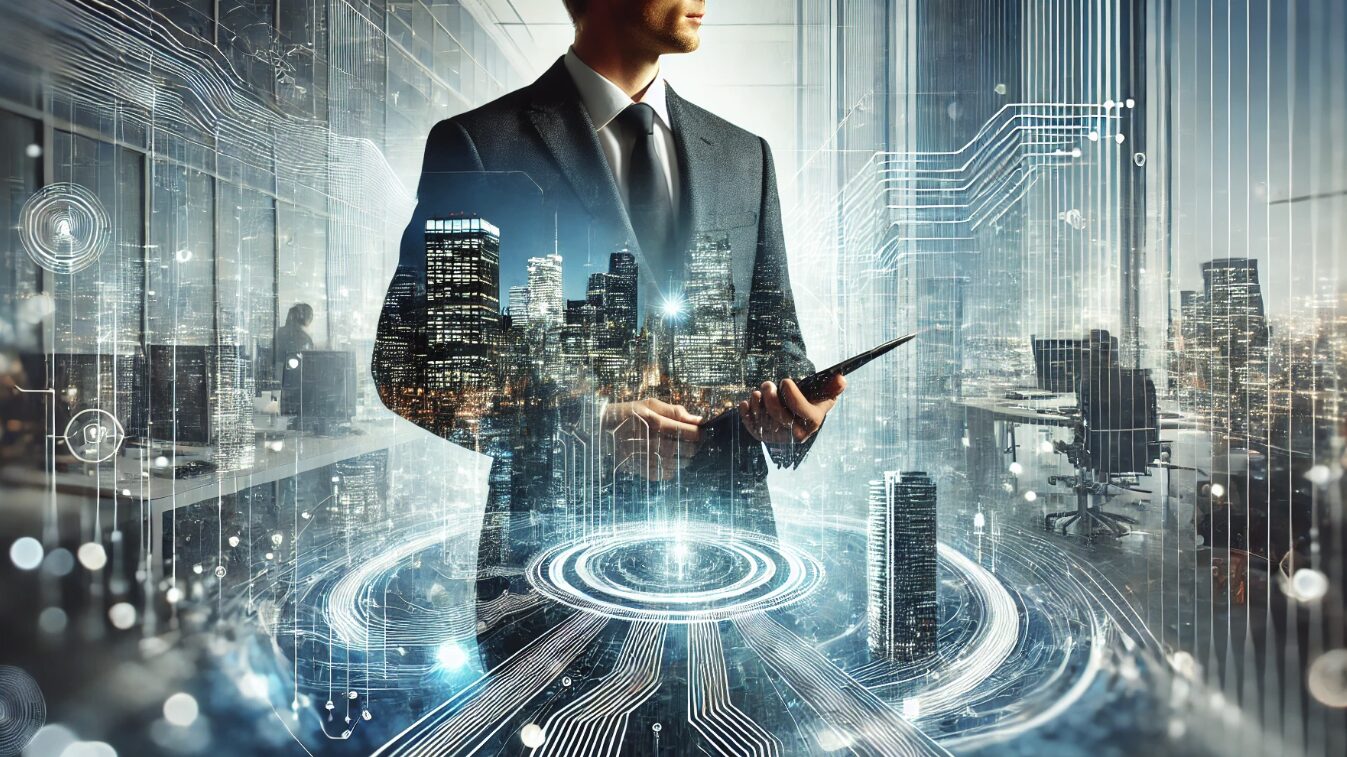


コメント