企業概要と最近の業績
株式会社エルアイイーエイチ
エルアイイーエイチは、複数の事業を手がける企業グループの持株会社です。
主な事業として、輸入肉や国産肉を取り扱う食肉卸事業、本格焼酎「閻魔」などを製造販売する酒類製造事業があります。
また、中学校向けの教材制作や学習塾を運営する教育関連事業も展開しています。
その他にも、就労支援をはじめとする福祉サービス事業、マンションの大規模修繕などを行うリフォーム関連事業、旅行事業、保険代理店事業などをグループ傘下で幅広く行っています。
2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が20億5百万円(前年同期比58.4%減)、営業損失が2億89百万円(前年同期は3億71百万円の損失)、経常損失が2億77百万円(前年同期は3億93百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失が2億96百万円(前年同期は3億93百万円の損失)となりました。
前連結会計年度に食品流通事業から撤退したことなどにより、売上高は大幅に減少しましたが、各損失の赤字幅は縮小しています。
セグメント別に見ると、食肉卸事業は、一部取引先の倒産の影響があったものの、売上高は10億52百万円(前年同期比10.7%増)と増収を確保しました。
酒類製造事業は、海外輸出が好調に推移したことなどから、売上高は4億1百万円(同13.5%増)となりました。
教育関連事業は、生徒数の減少などにより、売上高は3億3百万円(同10.9%減)となりました。
リフォーム関連事業は、大型案件の受注により、売上高は1億45百万円(同112.5%増)と大幅に増加しました。
【参考文献】https://lieh.co.jp/
価値提案
株式会社エルアイイーエイチは、食品や酒類、そして教育関連など、多彩な事業領域で高品質な製品とサービスを提供する点が魅力です。
食品流通では産地直結の新鮮さを、酒類製造では伝統技術を守りながらも新しい商品開発を行い、教育事業では多様な学習ニーズに対応しています。
【理由】
なぜこうした価値提案を行うのかというと、社会が求める幅広いニーズを一社でカバーすることで、相互に補完し合う強固な経営基盤を築きたいという考えがあるからです。
食品の流通ルートや独自ブランドの酒類が教育事業にも相乗効果をもたらすといったように、事業間のシナジーを最大限に活かす狙いがあります。
主要活動
食肉卸売を中心とした食品流通事業、日本酒や焼酎の製造販売を行う酒類製造事業、そして教育コンテンツの制作・配信を担う教育関連事業が大きな柱です。
【理由】
これらの活動がなぜ必要かといえば、日常生活に欠かせない食と飲料、それに学びや情報が加わることで、顧客との接点を多方面に広げやすくなるためです。
例えば食品流通のネットワークがあることで、新鮮な食材を活用した飲食関連イベントが企画できたり、教育サービスが食文化や地域産業と結びついた学習プログラムを提供できたりするなど、各事業が有機的につながるメリットを生み出しています。
リソース
地域の生産者との強固な連携や、長年受け継がれてきた酒造技術、そして教育コンテンツの制作ノウハウが重要な経営資源です。
【理由】
なぜこれらがリソースとして重視されるのかというと、同社が地域密着型のビジネスを展開しながら伝統と革新を融合していくためには、外部との連携と専門技術の継承が欠かせないからです。
また、教育事業では多角的な専門知識を持つ制作チームが不可欠であり、これら人材やノウハウをうまく組み合わせることで、新しいサービスや製品を次々と生み出すことができます。
パートナー
地域の自治体や生産者、教育機関などと協力関係を築いている点も大きな特長です。
【理由】
なぜパートナーを重視するのかというと、協業によって地元産業を活性化したり、伝統的な製造技術を守ったりできるためです。
さらに教育機関との連携は、教材や研修プログラムを開発する際に実践的な知見を取り込む機会にもなります。
こうしたパートナーシップを広げることで、同社のビジネスモデルそのものを地域社会や学術分野とも結びつけ、より大きな社会価値を生み出しているといえます。
チャンネル
店舗での直販やオンラインストア、さらに教育関連ではデジタルプラットフォームを活用しています。
【理由】
これらのチャンネルをなぜ拡充しているのかというと、地域密着だけでなく全国、さらには海外へ展開することも視野に入れているからです。
オンラインでの販売は生鮮食品や酒類などにも対応し、遠方からでも購入できる環境を整備しています。
また教育コンテンツはオンラインでの受講が増えており、デジタル化を推進することで受講者層の拡大を図っています。
顧客との関係
食品・酒類の分野では対面での販売やイベントを通じて顧客とのコミュニケーションを大切にし、教育分野ではオンラインサポートやフォローアップを強化しています。
【理由】
なぜこうした顧客関係が必要かといえば、実際に商品を口にする場面や学習を進める場面で、直接的なフィードバックが得られるからです。
顧客の声を活かして新商品や新コースを開発し、継続的な利用やリピート購入につなげることで、長期的な信頼関係を育んでいます。
顧客セグメント
食にこだわる一般消費者、伝統的な酒造りに魅力を感じる方、そして幅広い学習機会を求める学生や社会人など、多岐にわたります。
【理由】
なぜこうしたセグメントを対象にするのかというと、生活の基本となる食事や飲料に加え、スキルアップや学び直しを求めるニーズは常に存在するからです。
多くの人に共通する分野と個別のニーズが混在しているため、柔軟な事業展開で様々な層を取り込める仕組みを作っています。
収益の流れ
食品・酒類の製品販売による収益と、教育サービスの受講料が主な収益源です。
【理由】
なぜそのような流れになるのかというと、リアルな商品販売による確実な売上と、オンラインやセミナーなどによる教育分野での安定した収益を組み合わせることで、経営リスクを分散したい狙いがあるからです。
さらにイベントやプロモーションを組み合わせることで、収益機会を多層化しています。
コスト構造
主に原材料費や製造コスト、教育コンテンツの制作費、人件費などが中心です。
【理由】
これらがなぜ重要かというと、食品や酒類の品質維持、教育事業の質を高めるためにはコストを惜しまない姿勢が必要な一方、無計画なコスト増大は利益を圧迫するからです。
教育関連事業の制作費や原材料費の高騰が直近の営業利益や経常利益に影響を与えたように、コスト管理の巧拙が同社の業績を大きく左右しています。
自己強化ループの仕組み
株式会社エルアイイーエイチが展開する食品流通事業、酒類製造事業、教育関連事業は、それぞれが独立しているようでいて相乗効果を生み出しやすい構造になっています。
たとえば食品流通事業では地元の生産者と連携して、鮮度の高い食材を安定的に確保できますが、その過程で地域に根ざしたネットワークが形成されます。
このネットワークは地産地消をテーマにした教育プログラムにも活用でき、教育事業のコンテンツ制作に新しいアイデアや実例を提供します。
一方、酒類製造事業では伝統的な酒造りを守りながら新商品の開発を重ねており、そのストーリーは観光や地域イベントでも取り上げられやすいため、さらなる販路拡大やブランド認知度向上につながります。
こうした循環が企業全体の成長エンジンとなり、収益のアップだけでなく新規顧客の獲得にも寄与しているのが特徴です。
採用情報と株式情報
採用に関しては公式サイトなどで随時募集されますが、現時点で初任給や平均休日、採用倍率などの具体的な情報は確認できませんでした。
興味がある方は今後のIR資料や企業ウェブサイトの採用ページをチェックすると良いでしょう。
株式情報については銘柄コードが5856で、2025年3月期の配当金は未定となっています。
また2025年2月19日時点の株価は1株あたり40円ほどで推移しています。
経営戦略や業績次第では配当や株価が変動する可能性があるので、投資検討の際は最新情報に注意が必要です。
未来展望と注目ポイント
株式会社エルアイイーエイチは、食品流通と酒類製造、それに教育関連という異なる3つの事業領域を持ち、それらが相互に補完し合う強みを持っています。
今後の成長戦略としては、地域連携のさらなる拡大やオンラインを活用したサービス強化が挙げられます。
食品流通では新たな販路開拓や海外展開、酒類製造では伝統技術を守りつつも若い世代に訴求する商品づくりが期待されます。
教育事業ではコンテンツ制作のスピードアップとニーズ対応が課題になる一方、学習のデジタル化や社会人学習の需要が高まることで新たなチャンスが生まれそうです。
また、最新のIR資料などを通じて経営方針を随時チェックしていくと、同社の取り組みがどのように業績を底上げしていくのかが見えてくるでしょう。
多角的な事業展開はリスクもありますが、事業間のシナジーを最大限活かすことで、さらに大きな成長が期待できる企業といえます。

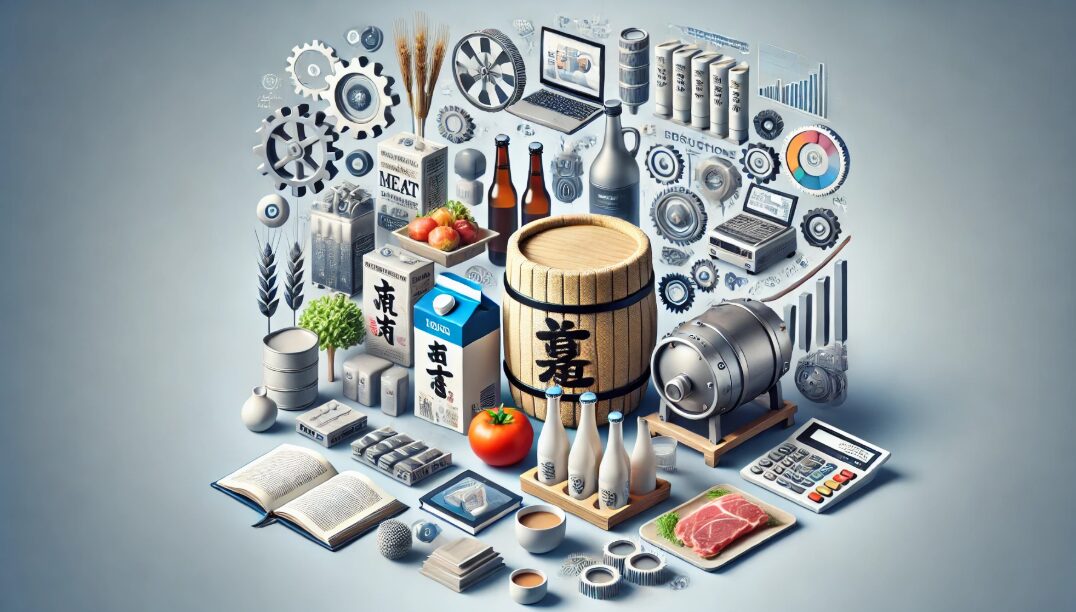


コメント