企業概要と最新業績
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングスは、建設コンサルタント事業を主軸に、国内外の社会インフラ整備を幅広く手がける持株会社です。
道路、橋梁、鉄道、河川といった物理的なインフラに加え、都市開発や環境保全、防災・減災など、多様な分野で調査・計画から設計・管理までを提供しています。
グループ内には高度な専門性を持つ企業を擁し、DXを活用した次世代型のインフラ管理や地方創生などの新たな領域にも積極的に取り組んでいます。
世界各国の国家的プロジェクトに携わるグローバルなコンサルタント・ビジネスを展開し、持続可能な社会の実現に貢献しています。
2025年9月期の通期連結業績は、前年同期と比較して大幅な増収増益となりました。
売上高は前年同期比10.5%増の953億6,500万円、営業利益は同20.6%増の56億2,200万円を達成しています。
経常利益は前年同期比43.6%増の57億7,700万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同47.0%増の38億1,900万円を記録しました。
海外市場における超大型案件の業務進捗が好調に推移したほか、国内でのインフラ整備・保全に関連する需要を確実に取り込んだことが要因です。
全セグメントにおいて事業が堅調に進展し、各段階利益において過去最高を更新するなど、非常に高い成長性と収益性を示しています。
【参考文献】https://www.oriconhd.jp/
価値提案
オリエンタルコンサルタンツホールディングスの価値提案は、橋梁や道路、トンネルといった土木インフラから、都市計画、観光活性化、エネルギー分野まで、総合的な知的サービスを提供する点にあります。
単に調査や測量を行うだけでなく、課題の分析・診断から事業計画の立案、運用や評価に至るまでの一貫した支援が可能なことが大きな強みです。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、公共事業を中心としたインフラ整備コンサルだけでは限界があるという市場環境の変化があります。
国内マーケットの縮小が見込まれる中、さまざまな新規事業領域に展開することで、独自のソリューションを提供し続ける必要が高まっているのです。
この総合コンサルティングとしての幅広さが、顧客企業や行政機関にとって利便性が高いだけでなく、長期的なパートナーシップを築く原動力にもなっています。
結果として、社会課題の発見から解決策の提案、事業の継続的な改善までをトータルにサポートできる体制が整い、顧客の期待に応え続けられるビジネスモデルが形成されました。
主要活動
同社の主要活動は、社会基盤整備に関わる調査・測量・設計・管理といった従来の土木コンサルティングだけでなく、都市開発や交通計画、さらには海外プロジェクトへの技術協力など多岐にわたります。
【理由】
なぜそうなったのかを考えると、社会インフラを横断的に扱う専門家集団として、案件ごとの縦割りを超えた一気通貫のサービスが求められるようになったことが背景です。
加えて、景観デザインや環境アセスメント、PPP/PFI事業の運営スキームなど、より複雑化・高度化するニーズに対応する必要がありました。
その結果、事前の企画段階から実施段階、さらにはアフターメンテナンスに至るまでを包括的に手掛けることが企業の差別化要因となっています。
こうした幅広い業務領域を網羅することで、国内だけでなく海外の大型プロジェクトや新興国のインフラ支援にも着実に対応できる強固な基盤が築かれました。
リソース
リソースとして最も重要なのは、専門技術を有する人材と国内外で培われたプロジェクト経験です。
橋梁やトンネルの設計技術者、都市計画のスペシャリスト、環境調査のエキスパートなど、多彩な分野のプロフェッショナルが集結していることが大きな強みとなっています。
【理由】
なぜそうなったのかという理由は、一つの分野に特化するよりも、複数分野をカバーできる人材がそろうことで総合コンサルティングの付加価値を最大化できると判断したためです。
実際に、各分野の専門家が連携してプロジェクトを進めることで、効率的な問題解決や、クライアントが気付いていない潜在的リスクの早期発見にもつながっています。
さらに、長年にわたって官公庁や海外政府機関と築いてきた関係から得られる知見も重要なリソースです。
大規模インフラ投資には複雑な法規制や多様なステークホルダーとの調整が不可欠であり、こうした経験値が同社の競合優位を支えるエンジンとなっています。
パートナー
同社の主要パートナーは、国内外の政府機関や地方自治体、関連する民間企業、そして海外の国際機関などです。
【理由】
インフラ整備や観光活性化のプロジェクトは多数の利害関係者が存在するため、技術面だけではなく資金や運営ノウハウなど多角的な協力体制が必要だからです。
例えば、PPP/PFI事業を成立させるためには、金融機関や運営会社とも協力しながら収益構造を確立する必要があります。
また、海外では現地の政府や国際機関との連携がないとプロジェクトそのものが成立しないケースもあります。
こうした広範なパートナーとの連携によって、同社は単なるコンサルティング会社にとどまらず、プロジェクトの推進役として大きな役割を果たせるようになっています。
さらに、パートナーとの協働が同社の技術者にも刺激を与え、新たなスキル開発や実績の蓄積に繋がり、さらなる事業拡大を可能にしているのです。
チャンネル
チャンネルは、入札プロセスや業界イベント、公式ウェブサイト、そして直接営業が中心となっています。
【理由】
公共インフラ事業の多くが入札制度で決定されるという業界特性が大きく作用しています。
特に政府・自治体案件では、資格審査や入札参加条件などの厳格なルールに基づいて仕事が発注されるため、入札のプロセスを通じて安定的に案件を獲得することが基本となっています。
一方で、新規領域への進出や、民間主導の観光・地域活性化事業などでは、積極的にセミナーやイベントへ参加し、潜在顧客とコミュニケーションを図ることが鍵になります。
公式ウェブサイトやSNSなどのオンラインチャネルも情報発信の場として機能しており、海外プロジェクトでは現地パートナーとの直接交渉や国際会議など、グローバルな場でのネットワークづくりが重要となっています。
これら複数のチャネルを組み合わせることで、幅広い顧客層に効率よくアプローチできる体制を整えているのです。
顧客との関係
顧客との関係は、基本的にはプロジェクト単位での契約形態が中心ですが、長期的なパートナーシップへと発展するケースも多々あります。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、インフラ整備や地域活性化プロジェクトが単年で完結しないことが多いという点があります。
例えば、橋梁や道路建設などは設計・施工・維持管理までを通じて数年から十数年単位の時間を要し、運営や改修を含めるとさらに長期間にわたることもあります。
この長いスパンにおいて、同社は定期的な点検やコンサルティングを行うことで顧客の課題を継続的に支援し、信頼関係を深めてきました。
また、PPP/PFI事業や観光開発などでは、同社が事業運営に主体的に関わる場合もあるため、パートナーシップという形での関係性が重要視されます。
結果として、単発の受注にとどまらず、顧客企業や自治体が抱える中長期的な問題解決まで担当し、新たな案件にもつながる好循環が生まれるのです。
顧客セグメント
顧客セグメントは、国内外の政府機関や地方自治体、民間企業、国際機関など多岐にわたります。
【理由】
インフラ整備や都市開発、観光、環境保全など幅広い事業領域を扱う同社にとっては、特定の分野だけに依存するリスクを回避する必要があるからです。
国内公共事業が縮小傾向にある一方で、海外市場ではインフラ需要が拡大している地域も多く存在します。
また、民間主導で進められる観光開発やエネルギー事業などへも参入することで、収益源を多角化しつつノウハウを蓄積してきました。
このように、多様な顧客層を対象とすることによって経済環境の変動にも柔軟に対応できるようになり、同時に業界内での知名度や技術評価も高まり続ける好循環が作られています。
収益の流れ
同社の収益源としては、コンサルティングサービスやプロジェクト管理費用、PPP/PFI事業からの収益などが挙げられます。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、単なるコンサルティングフィーだけではなく、事業運営に自ら関与することで収益構造を多層化している点があります。
例えば、公共インフラ案件では設計や調査の報酬を得るだけでなく、その後のメンテナンスや運用支援で追加の収益を獲得することができます。
一方、PPP/PFI事業では、民間企業として公共施設の管理運営に参加することで、長期的な安定収益を確保できる可能性があるのです。
また、観光施設や地域活性化の事業においては、独自のノウハウを生かしたコンサル+運営支援をセットで提供することで、収益源を複線化しています。
こうして多角的な収益モデルを持つことが、景気変動のリスク軽減に繋がり、より強固な経営基盤となっているのです。
コスト構造
コスト構造としては、人件費や調査・設計・管理に伴う経費、さらに事業運営費などが主な割合を占めます。
【理由】
なぜそうなったのかを探ると、コンサルティングビジネスは人材の専門知識と経験が最大の資産となるため、技術者やコンサルタントへの報酬が大きなコスト要素となるのは必然といえます。
さらに、プロジェクトごとの専門的な調査や分析、海外事業における渡航費や現地調整費用なども、コストの重要な部分を占めます。
また、PPP/PFI事業などにおいては、運営会社としての立場で設備投資やランニングコストを一部負担するケースもあり、従来のコンサルティング業務とは異なるコスト要素が生まれてきました。
こうしたコストを適正化するために、同社は人材育成やITツールの活用に力を入れることで業務効率を高め、プロジェクトの採算性と品質を両立させています。
このように、人材への投資と効率化のバランスを取ることが、長期的な競争力につながっているのです。
自己強化ループ(フィードバックループ)
オリエンタルコンサルタンツホールディングスにおける自己強化ループは、人材とプロジェクト経験の蓄積が好循環を生み出す点にあります。
幅広い分野の顧客との取引を通じて、多種多様な課題解決スキルを獲得し、次の案件へとスムーズに応用できるのです。
例えば、国内インフラ関連の計画立案で得た知見を海外の新興国に提供するケースでは、日本での厳格な設計基準や安全対策がそのまま強みになります。
また、海外プロジェクトで培った国際的な調整力や語学力が、国内の多文化共生施策や観光事業にも活かされるでしょう。
このように、一度得たノウハウが別の領域でも役立つため、経験値が企業全体に循環し続けるのです。
さらに、PPP/PFI事業や環境エネルギー分野のように新規領域で一度成功を収めると、社内外で評価が高まり、より大きな予算規模や難易度の高い案件が舞い込む可能性も高まります。
こうした連鎖反応が社員のモチベーション向上にも繋がり、企業のブランド力も強化されるため、まさに好循環が持続していると言えます。
採用情報
同社の初任給は総合一般職で博士了が月額29万3,000円(家族手当5万3,000円含む)、修士了が月額29万1,000円(家族手当5万3,000円含む)と、専門性を評価した設定が特徴的です。
学部卒の具体的な金額は公表されていませんが、いずれの学歴であっても知見を活かせる現場が多いことが魅力でしょう。
平均年間休日は120日以上を確保しており、ワークライフバランスにも配慮しているといえます。
採用倍率は高めと予想されますが、詳しい数値は公表されていません。
技術・コンサル両面で高度な人材を求めている分、専門性をアピールできる学生や転職希望者にとって、やりがいが大きいと考えられます。
株式情報
現在、同社は上場していないとされるケースが多く、公式サイトでも株式関連の情報は限定的です。
よって、特定の銘柄コードや上場市場に関する公表データは確認できず、配当金や1株当たり株価の情報も一般には開示されていない状況にあると言えます。
ただし、インフラ系コンサル企業の安定性や社会的需要の高さを踏まえれば、将来的に何らかの形で資本市場にアクセスする可能性も否定できません。
現段階では非上場企業としての経営方針を貫いており、グループ全体のプロジェクト利益や内部留保を活用しながら、自律的な成長を続けていることが特徴となります。
未来展望と注目ポイント
今後は、国内インフラの老朽化対策が加速し、橋梁や道路、トンネルの再整備需要が大きくなると予想されます。
一方、海外市場ではアジアやアフリカ地域を中心に、交通網や水力発電などのインフラ開発が拡大を続けるでしょう。
こうした環境下で、同社は技術的な強みを活かして総合コンサルティング力をさらに高めることで、公共事業のみならず民間主導の観光開発や都市再生、さらには環境・エネルギーセクターでの実績も拡充する可能性があります。
また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、建設業界でも設計や施工管理にITが積極的に取り入れられる流れが続くため、同社が持つ調査・解析ノウハウとのシナジーが生まれやすいでしょう。
こうした先端技術の取り込みとグローバル展開の両軸で事業を進めることで、今後も高い成長戦略を実現していくことが期待されます。
さらに、地域社会や国際社会の課題解決に貢献する企業姿勢が評価されれば、SDGsやESG投資の観点からも注目度が増していく可能性が高く、今後の動向からますます目が離せません。
まとめ
オリエンタルコンサルタンツホールディングスは、幅広いインフラ領域や新規事業を推進する総合コンサルティング企業として、高度な専門性と豊富なプロジェクト実績を積み重ねてきました。
2024年9月期の売上高862億8,200万円という業績から見ても、国内外問わず安定した需要を確保できるビジネスモデルが機能していると考えられます。
特に、PPP/PFI事業や観光・地域活性化、小水力発電といった新たな成長分野に着実に足場を築いている点は、同社の柔軟な適応力と総合的なコンサルティング力の証といえるでしょう。
また、人材育成や多岐にわたるパートナーとの連携により、自己強化ループを生み出している点も見逃せません。
さらに、採用面では技術者やコンサルタント志望者にとってチャレンジの幅が大きく、専門性を発揮できる環境が整いつつあります。
今後も国内インフラの再整備や海外の大型プロジェクト需要が高まるなかで、社会的なニーズを的確に捉えながら、持続的な成長を実現することが見込まれます。
企業活動を通じて豊かな暮らしと安全を追求する姿勢は、同社のビジネスモデルと成長戦略に深く根付いていると言えるでしょう。
今後のさらなる展開が期待される企業として、注目して損はありません。

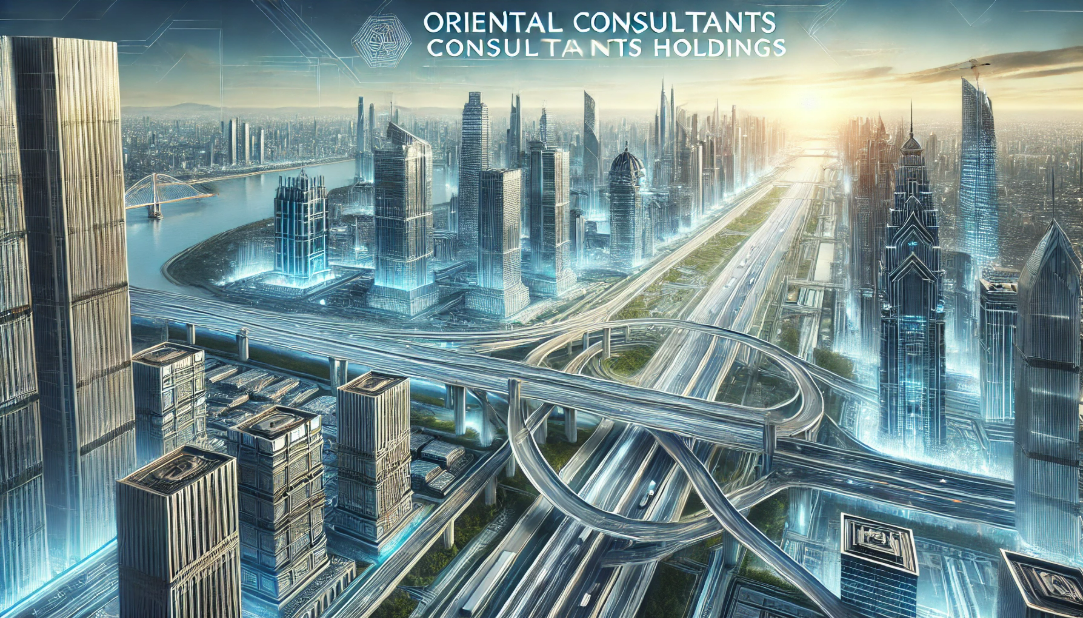


コメント