企業概要と最近の業績
株式会社長野計器
当社は、圧力計や圧力センサーといった、圧力を測るための計測機器を開発・製造しているメーカーです。
主力製品の圧力計は、国内トップクラスのシェアを誇ります。
当社の製品は、自動車や建設機械、半導体製造装置、医療機器など、非常に幅広い産業分野で使われており、様々な機械や設備の安全と品質を支えています。
また、アメリカやヨーロッパ、アジアにも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
2025年8月7日に発表された2026年3月期第1四半期の決算によると、売上高は224億5,000万円で、前年の同じ時期に比べて6.0%増加しました。
営業利益は18億5,200万円で、前年同期比で27.3%の大幅な増加となりました。
経常利益は21億3,600万円(前年同期比4.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億2,500万円(前年同期比5.4%増)と、増収増益を達成しています。
半導体製造装置市場の回復を背景に圧力センサーの販売が好調だったことに加え、海外での建機・農機向け製品の販売も堅調に推移したことが業績を牽引したと報告されています。
価値提案
株式会社長野計器は、高精度と高信頼性を兼ね備えた圧力計測機器を提供することで、顧客の生産工程を支援しています。
高い精度が求められる場面でこそ同社の強みが発揮され、機器トラブルを減らしながら安定稼働を実現する点が大きな価値となっています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、国内外の製造業や医療機器業界で“ミスが許されない”計測ニーズが増えたことが背景にあります。
安心して導入できる製品づくりを続けてきた結果、信頼を得た顧客からのリピート受注や新規分野での採用が拡大し、高い技術力を活かしたソリューション型の提供へと進化しつつあります。
主要活動
同社の主要活動は、製品開発と製造、品質管理、販売、そしてアフターサービスに及びます。
特に自社開発の技術を量産工程に落とし込むプロセスは、幅広い産業で求められる厳格な品質基準に合わせた独自のノウハウが詰まっています。
【理由】
なぜこうした活動に力を入れているかというと、圧力計測は安全管理や効率化に直結するため、確かな品質と継続的なメンテナンス体制が求められるからです。
開発段階から徹底的に試験を行い、製造プロセスでも厳しい品質チェックを重ねることで、不良率を低減して顧客満足度を高める取り組みが同社の主要活動に深く根付いています。
リソース
株式会社長野計器のリソースは、長年培ってきた高度な計測技術をもつエンジニアや専門スタッフ、最新の製造設備、そして研究開発施設が挙げられます。
大手自動車メーカーや医療機器メーカーなど、精度と安全性を重要視する顧客に選ばれるためのコア技術が社内に蓄積されてきました。
【理由】
なぜこうしたリソースが重要なのかというと、圧力計測はミクロ単位の精度が求められる領域であり、熟練の人材や専門設備がなければ安定した品質を保つことが難しいからです。
これらのリソースを活かすことで、新製品開発や既存品の改良に柔軟に対応できる体制が整っています。
パートナー
同社は、部品供給業者や販売代理店、さらに研究機関などと連携しています。
【理由】
なぜパートナーシップが大切かというと、世界的に見ても技術革新が速い計測分野において、外部との協働による新技術開発やコスト削減が競争力の源泉となるからです。
信頼できる部品供給業者と長期的な関係を築くことで、部品調達の安定性を確保し、さらに代理店ネットワークを活用して多様な地域・市場への販売展開を強化しています。
研究機関との協力では、次世代センサやIoT連携技術など先端的なテーマに挑戦しやすくなり、顧客ニーズにマッチするイノベーションを加速させることができます。
チャンネル
同社は、直接営業と代理店ネットワーク、さらにオンラインを含めた複数の販売経路を持っています。
【理由】
なぜ複数のチャンネルを活用するかというと、圧力計測機器を必要とする産業は自動車やエネルギーだけでなく、食品加工や化学プラントなど多岐にわたるからです。
直接営業は大口顧客や特注案件に対応しやすく、代理店ネットワークは地域別にきめ細かな販売活動を展開できます。
オンラインチャネルも拡充することで、幅広い潜在顧客へアプローチし、問い合わせや受注を迅速に獲得できる体制を整えています。
顧客との関係
同社は技術サポートや定期的なメンテナンスサービス、そして問題が起きた際の迅速な対応を重視しています。
【理由】
なぜ顧客との緊密な関係づくりが重要かというと、圧力計測機器の故障や誤差は、製造ライン全体の停止や重大なトラブルにつながりかねないからです。
製品導入後の定期点検やサポート窓口を通じて、トラブルを未然に防ぎ、長期的な信頼を獲得する取り組みが重要視されています。
このようにアフターサービスを手厚くすることで、継続的な顧客ロイヤルティを高め、新たな受注や製品アップグレードへとつなげています。
顧客セグメント
製造業やエネルギー業界はもちろん、医療機器メーカーやインフラ関連の企業など、多様な業界が顧客セグメントとなっています。
【理由】
なぜ幅広いセグメントをカバーするかというと、圧力計測は安全管理や品質保証の要となるため、業界を問わず需要が存在するからです。
近年では医療やヘルスケア分野への応用ニーズも拡大しており、従来の製造業だけでなく、新たな分野にソリューションを提供することで収益源を拡大しています。
また特定の業界不振によるリスク分散効果も大きく、安定した事業基盤を築く要因にもなっています。
収益の流れ
収益の主軸は製品販売で得られる売上です。
加えて、メンテナンスや点検サービスからの収入も重要な収益源となっています。
【理由】
なぜサービス収入が重視されるかというと、製品の稼働年数が長い計測機器では、定期的な調整や修理が必要であり、これに付随するサポート契約が見込めるからです。
製品本体の販売だけではなく、アフターサービスを包括的に提供することで、長期的かつ安定した収益を得る仕組みを整えています。
今後はIoTやデータ連携サービスなど、より付加価値の高い領域へ拡張していく可能性も期待されます。
コスト構造
製造コストと研究開発費、販売・マーケティング費用が主なコスト構造を形成しています。
【理由】
なぜこれらが主軸となるかというと、高い品質を保つために素材や部品の選定、製造ラインの高度化が欠かせないからです。
また、次世代センサやIoT対応技術の開発を続けるには研究開発への投資が不可欠であり、その先行投資が同社の競争力を生む源泉となっています。
販路拡大や海外展開を進めるうえでは、代理店との連携やマーケティングにも一定の費用が必要となり、総合的なコスト管理を行いながら事業を伸ばしているのが特徴です。
自己強化ループ
同社は圧力計測機器の需要増加を受けて、生産効率の向上とコスト改善策を推進し、大幅な売上と利益の拡大を実現しています。
この成果は再投資に回され、研究開発や設備更新に使われることでさらに高精度な製品や新分野への応用技術を生み出すサイクルが回り始めています。
こうした技術力アップが新たな顧客を呼び込み、販売数をさらに増やすことで収益を拡大し、また次の投資につなげられる好循環が形成されているのです。
需要が拡大するほど製品やサービスが成熟し、コスト効率も高まるため、同社のビジネスモデルは持続的な成長を後押ししやすい構造になっています。
競合他社が参入しづらい技術領域を押さえ続けることで、利益率と売上の双方が上昇する自己強化ループを構築し続けることができると考えられます。
採用情報
初任給や平均休日、採用倍率などの詳しい情報は公開されていないようですが、製造業や技術系企業として、技術職を中心に幅広い分野の人材を求めている可能性があります。
最新の情報は会社の公式サイトや各種就職情報サービスで確認するのがおすすめです。
研究開発や品質管理、製品設計など、幅広い専門スキルを活かせるポジションがあると予想されるため、ものづくりに興味がある人には魅力的な環境といえそうです。
株式情報
同社の銘柄は長野計器で、証券コードは7715です。
2023年3月期の配当金は年間32円とされており、中間配当と期末配当がそれぞれ16円ずつとなっています。
1株当たりの株価情報は公開されていませんが、配当利回りや業績の推移を見ながら、投資家がどのように評価しているかを継続的にチェックすることが大切です。
業績が順調に伸びている企業だけに、今後の配当政策や成長投資への使い道にも注目が集まっています。
未来展望と注目ポイント
同社は自動車やエネルギーだけでなく、医療やヘルスケア、さらにはIoTやスマートファクトリー領域への展開など、多方向に成長の余地を持っています。
特に高精度な圧力センサは安全管理や品質制御に欠かせない存在となりつつあり、新興国でのインフラ需要や先進国での省エネ需要などとも結びつきやすいです。
今後は海外展開の強化や新製品の研究開発への投資により、さらなる市場拡大が期待できます。
製造業の景気動向や技術革新のスピードに左右される面はありますが、幅広い顧客セグメントをカバーしていることでリスク分散が可能です。
継続的な研究開発とコスト管理により、さらなる競争力アップを図れるかがポイントとなりそうです。
中長期的に見ても新市場の開拓や高付加価値サービスの提供によって安定した収益を確保し、次なる成長戦略を実現できるかどうかが注目されます。

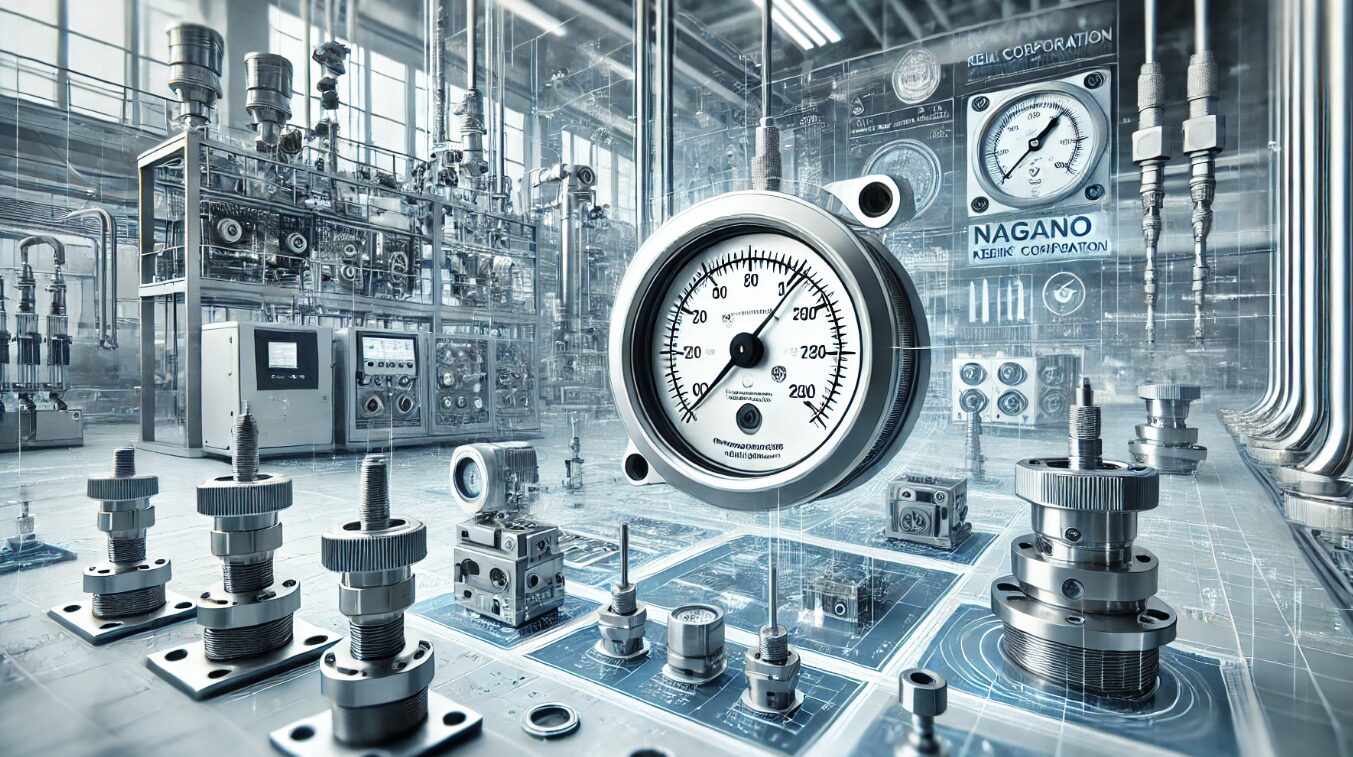


コメント