企業概要と最近の業績
株式会社黒田精工
当社は、超精密なものづくり技術を基盤とする部品・システムメーカーです。
事業の柱は3つあり、1つ目は半導体製造装置や工作機械などに不可欠なボールねじやアクチュエータなどを手掛ける「駆動システム事業」です。
2つ目は、電気自動車(EV)や家電製品のモーターに使われるモーターコアを製造するための金型などを提供する「金型システム事業」です。
3つ目は、精密な平面加工を実現する平面研削盤という工作機械や、創業以来の強みである精密測定技術を活かした「計測システム事業」を展開しています。
これらの事業を通じて、世界の産業の根幹を支える精密技術を提供しています。
2026年3月期の第1四半期決算では、売上高が56億1,900万円となり、前年の同じ時期と比較して2.9%の増収となりました。
これは、駆動システム事業において、半導体製造装置関連の需要が堅調に推移したことによるものです。
一方で利益面では、金型システム事業において中国でのEV向け需要が減速したことや、原材料費などのコスト上昇が影響し、営業利益は1億2,500万円と前年同期比で55.2%の大幅な減益となりました。
経常利益は1億5,300万円(同48.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億2,100万円(同34.6%減)と、増収減益の結果となっています。
価値提案
株式会社黒田精工の価値提案は、高精度かつ高耐久な精密機械部品を提供することで、顧客の生産効率を向上させるところにあります。
特にボールねじなどは工作機械や半導体製造装置など、高度な制御と精密な動作が求められる場面で活用されます。
【理由】
なぜそうなったのかという背景として、同社が長年培ってきた精密加工技術や独自の研究開発体制が挙げられます。
自動車業界や家電業界など、製品の品質に厳しい基準がある企業から選ばれるためには、微細な寸法管理や長期的な耐久性が求められます。
同社はそうしたニーズに対応すべく、高水準の検査と品質保証体制を確立してきました。
その結果、単なる部品供給ではなく「高品質な工程改善のパートナー」として位置づけられ、顧客企業の製造ライン全体の効率アップにつながるソリューションを提供できる点が重要な強みとなっています。
主要活動
主要活動としては、製品開発と製造、品質管理、そして販売とアフターサービスまで一貫して行う体制が整っています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、高精度製品は製造工程でのわずかな誤差や材料選定のミスが品質に大きく響くため、すべてを把握できる自社内管理が不可欠だったからです。
また、アフターサービス面でも、定期点検やメンテナンスを自社でカバーすることによって、顧客が現場で困った時にすぐに対応できる体制を構築しています。
こうした仕組みが評価され、リピーターや長期的な取引につながることが多く、売上の安定化にも寄与しています。
リソース
リソース面では、高度な技術力を持つ人材と先進的な製造設備、さらに研究開発施設が挙げられます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、精密製品を作るには設計から切削加工や研削加工に至るまで、専門知識や技能が必要だからです。
同社は長年の経験と継続的な投資により、最先端の加工機を導入し、技術者を育成してきました。
また、開発拠点では耐久試験や新材料研究などが行われ、顧客からの要求仕様に応えるべく日々改良が進められています。
こうした高度な人材と設備があることで、高品質を維持しながらも新市場に対応できる柔軟さを持続することが可能になっています。
パートナー
パートナーには、部品供給業者や研究機関、技術提携先などが含まれます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、精密機械部品の世界では自社だけではカバーできない特殊加工や先端素材の知見を得るために、外部の優れた技術やリソースを活用することが一般的だからです。
さらに研究機関との連携により、次世代技術の開発スピードを加速し、競合他社との差別化を図っています。
また、共同開発やライセンス契約を行うことで、最新技術を製品へ迅速に取り込み、お互いの強みを高め合うことが狙いです。
チャンネル
チャンネルとしては、直接営業や代理店販売、そして一部オンラインでの情報発信や問い合わせ対応が行われています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、BtoBメーカーの場合、顧客企業の要望が高度で製品仕様を細かく詰める必要があるため、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが非常に重要となるからです。
代理店を活用するのは、地域や業界に詳しいパートナーを通じて販路を拡大するためです。
また、近年はIR資料やウェブサイトなどを通じて企業情報を発信し、新たな取引のきっかけを増やす取り組みも進められています。
顧客との関係
顧客との関係は、カスタマーサポートや定期メンテナンスを通じて深められています。
【理由】
なぜそうなったのかというと、精密部品は故障が発生すると生産ラインの停止につながるため、トラブルを最小限に抑えたい顧客のニーズが強いからです。
同社は定期訪問や技術サポートの体制を整えており、製品寿命を延ばすためのメンテナンス提案なども行います。
こうした手厚いサポートは顧客の信頼を高め、長期的な取引関係に発展しやすい土台になります。
顧客セグメント
顧客セグメントは、半導体や液晶関連装置メーカー、自動車部品メーカー、家電メーカーなどが中心です。
【理由】
なぜそうなったのかというと、これらの業種では高度な精度や耐久性が不可欠であり、量産ラインにも厳しい基準が設けられているため、同社の強みが活きるからです。
特に半導体関連では、微細加工技術と安定した動作が必須なので、同社のボールねじなどが大きな役割を果たしています。
一方で市場変動が激しい分野が多いため、複数の顧客セグメントに分散してリスクを低減する戦略も取られています。
収益の流れ
収益の流れは、製品販売がメインとなり、そのほかにメンテナンスサービス収入やライセンス収入が加わります。
【理由】
なぜそうなったのかというと、精密機械の導入後も定期的なメンテナンスが必要であり、その需要が収益機会として確立されているからです。
さらに同社が開発した独自技術をライセンス供与することで、製品販売以外の形でも安定的な収入源を確保しています。
この複数の収益源があることで、単一の市場変動に依存しすぎない体制を整えています。
コスト構造
コスト構造は、製造コストや研究開発費、人件費、そして販売促進費が主な要素です。
【理由】
なぜそうなったのかというと、精密部品の製造には最新鋭の設備投資が必要であり、さらに技術者の育成や研究開発に多額の費用がかかるためです。
また、高度な品質を維持するために検査体制やテスト工程を充実させる必要があり、その分だけ固定費が大きくなります。
一方で、こうした投資を惜しまないことで、高精度を重視する顧客からの評価が高まり、長期的にはビジネスモデル全体の安定につながっています。
自己強化ループ
同社には自己強化ループが存在します。
高精度かつ高耐久な製品を開発すると、それが顧客の満足度を向上させ、リピーターや口コミによる新規取引先を呼び込みます。
これによって売上が増え、研究開発や設備投資にさらに資金を回せるようになります。
すると新たな技術や製品が生まれ、より幅広い市場での需要を取り込み、また売上が伸びるという好循環です。
特に半導体や自動車、家電といった幅広い分野で高性能部品の需要が生まれると、同社の開発意欲や人材育成をさらに加速させる原動力となります。
顧客からのフィードバックも重要な要素であり、現場で発生した細かな問題を分析して改善に活かすことで、次の製品がさらに強化される仕組みが根付いています。
こうした循環を継続するためにも、市場が停滞気味な時期でも研究開発投資を怠らず、次の需要拡大に備える姿勢を維持している点が注目されます。
採用情報と株式情報
採用情報では、同社の初任給や平均年間休日、採用倍率などは公式には公表されていません。
ただし、精密機械メーカーは高度な技術を必要とするため、研究開発職やエンジニアの採用に力を入れている可能性が高いです。
職場環境としては、高精度な製品づくりに興味を持つ人が多く、技術者同士の情報交換も活発に行われる傾向があります。
株式情報としては、証券コード7726で上場しており、2025年3月期の年間配当予想は1株あたり20円です。
株価は2025年2月24日時点で約1002円となっており、業績回復への期待や設備投資計画の進捗なども含め、投資家からの注目を集めています。
未来展望と注目ポイント
今後の展望としては、半導体や液晶関連装置の需要が回復してくるかどうかが大きなカギとなりそうです。
もし世界的な半導体需要が再び高まり、主要顧客の生産調整が解消されれば、同社の高精度ボールねじや金型システムの受注も回復に向かう可能性が高いです。
また、自動車の電動化や家電の高性能化など、新たな成長市場に対応した開発投資を継続することで、収益源の多角化を進めることが期待されます。
製造ラインの自動化や省エネニーズにも応えられる製品を増やし、環境への配慮と生産効率向上の両立を訴求できれば、新規顧客の開拓にもつながるでしょう。
一方で、研究開発には多額のコストがかかるため、どのタイミングで投資を行うかなど資金繰りのマネジメントが課題になる可能性もあります。
こうした点を乗り越えながら、黒田精工がビジネスモデルを強化し、需要拡大の波を再び捉えられるかが今後の注目ポイントです。
特にIR資料を通じた開示情報や成長戦略の具体策をウォッチすることで、投資家や求職者にとっても同社の未来がより見えやすくなるでしょう。
今後の動向が楽しみです。

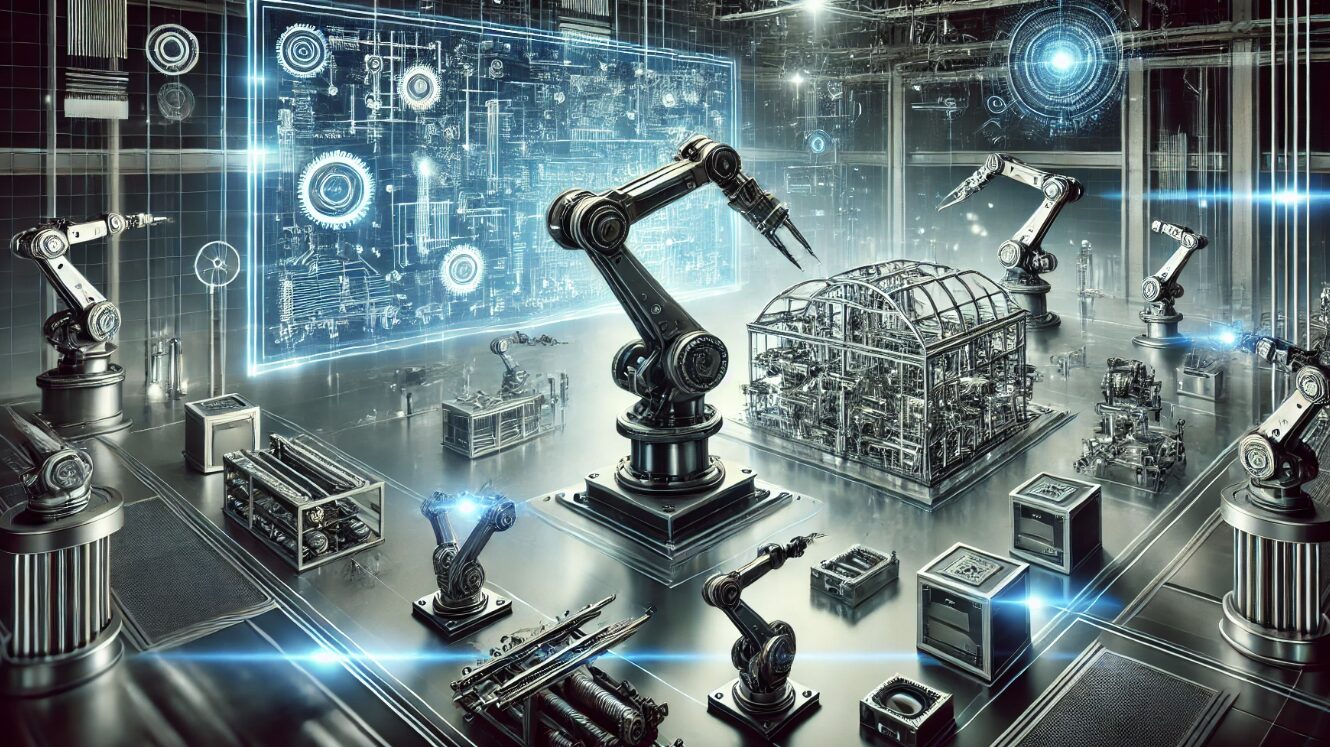


コメント