企業概要と最近の業績
株式会社 安藤・間
安藤建設と間組が合併して誕生した、日本の大手総合建設会社(ゼネコン)です。
事業の柱は、オフィスビルやマンション、医療・福祉施設などを建設する「建築事業」と、ダムやトンネル、橋梁といった社会インフラを造る「土木事業」の2つです。
両社が長年培ってきた高い技術力と豊富な経験を融合させ、安全・安心な社会基盤と生活空間の創造に貢献しています。
「ものづくり」への情熱を原点に、国内外で数多くのプロジェクトを手掛けています。
2026年3月期の第1四半期決算では、売上高が961億60百万円となり、前年の同じ時期と比べて6.8%の減収となりました。
これは、建築事業における完成工事高が減少したことによるものです。
利益面では、採算性の低い工事の計上や、資材価格・労務費の上昇などが影響し、営業損失が37億44百万円(前年同期は8億88百万円の利益)となり、赤字に転じました。
これに伴い、経常損失は27億46百万円、最終的な純損失は20億56百万円となっています。
一方で、新規の受注高は前年同期比で40.5%増の1344億円と好調に推移しました。
価値提案
安藤ハザマの価値提案は、高品質で安全性の高い建築や土木サービスを通じて、社会のインフラを支えることにあります。
橋やトンネルなどの大規模土木工事や、大型ビルから住宅までの多様な建築案件を担うことで、人々の生活を快適にすると同時に街づくりにも貢献します。
さらに最新の施工技術や環境配慮の取り組みを積極的に取り入れ、クライアントに安心と満足を提供しようと努めている点が大きな強みです。
【理由】
なぜそうなったのかという背景としては、長年の経験から培ったノウハウをもとに信頼を勝ち取り、さらに官公庁だけでなく民間からの需要拡大にも対応するため、品質と安全を最優先に据えたサービスが企業の大きな柱になってきたからです。
建設業は単に大きなものを作るだけでなく、完成後の維持管理や周囲の環境との調和など、幅広い視点が求められます。
そのため、経験豊富な技術者と最新技術の組み合わせで、顧客にとって最適な提案を続ける姿勢が、安藤ハザマの強い価値提案へとつながっています。
主要活動
安藤ハザマの主要活動は、施工管理や建築設計、土木技術の研究開発、プロジェクトマネジメントなど多岐にわたります。
実際に工事を行うだけでなく、顧客ニーズをもとにした設計や工程管理、さらに品質のチェックなどを一括して行うため、幅広い専門知識と実務力が求められます。
特に大型案件では、進捗や安全管理を丁寧に行うことが必要とされ、これらを効率よく進めるために高度な技術と豊富な経験を組み合わせている点が特徴です。
【理由】
なぜこのような活動が中心となるかというと、建設プロセスは計画段階から完成後の検証まで、一貫した責任と管理を行うことが信頼構築に直結するためです。
近年はデジタル技術を活用した施工管理システムの導入も進めており、現場の情報をリアルタイムで共有することでミスを減らし、コストやスケジュールを最適化する取り組みが見られます。
こうした工夫がプロジェクトの成功や安全性の向上につながり、企業としての評価を高めているのです。
リソース
安藤ハザマのリソースは、まず熟練した技術者や設計者といった人材が挙げられます。
数多くのプロジェクトを成功させてきたベテランスタッフだけでなく、若手人材の育成にも力を入れており、長期的な視点で人材のすそ野を広げています。
さらに、同社は技術研究所のような研究開発拠点を持ち、先端技術の導入や新工法の開発にも積極的です。
【理由】
なぜこうしたリソースが重要になるかというと、建設業界では一度の施工に失敗が許されないため、確かな知識と技術を持つ人材と、それを支える装置や施設が不可欠だからです。
また、最新の施工機械や情報技術システムなども重要なリソースとなっています。
これらは工事の効率化や品質向上に直結し、競合他社との差別化を図る鍵にもなります。
安藤ハザマは企業規模を生かし、研究開発を継続的に行う体制を整えているため、新技術をいち早く取り入れることで顧客ニーズに的確に応えられるのです。
パートナー
安藤ハザマのパートナーには資材供給業者や設計事務所、現場を支える協力会社などが含まれます。
大型工事や専門性の高い案件では、自社だけで完結せずに外部の専門家や企業とタッグを組むケースが多々あります。
【理由】
なぜそうなったかというと、工事規模が大きくなるほど必要な資材や技術分野が増え、社内リソースだけでは対応しきれない領域が出てくるからです。
そこで、それぞれの分野で強みを持つパートナー企業と連携することで、質の高い成果物を提供できます。
さらに安藤ハザマは、長年の実績から築かれた信頼関係を活かして複数の業者と協力関係を持ち、資材の安定確保や工期短縮に取り組んでいます。
こうしたパートナー戦略はコスト削減だけでなく、最新の建設技術や資材情報を得る上でも役立ち、結果的に顧客満足度を高めることにつながっています。
チャンネル
安藤ハザマのチャンネルは、直接の営業活動や入札参加、公式ウェブサイトなどが中心になります。
公共事業の場合は入札が主な受注経路ですが、民間事業や海外案件では企業間のネットワークや紹介、IR資料を通じたアピールなども利用されています。
【理由】
なぜチャンネルが多様化しているのかというと、公共工事だけに依存してしまうと景気の影響を大きく受けるため、民間デベロッパーや海外政府機関などへも積極的にアプローチしているからです。
また、オンラインでの情報発信に注力することで、企業イメージの向上や採用活動にもつなげています。
最近ではSNSや動画配信などの新しい手段も取り入れ、若い世代にも企業の取り組みをわかりやすく伝えようとしている点も特徴です。
顧客との関係
安藤ハザマはプロジェクト単位で契約を結ぶケースが多いですが、その後もメンテナンスやアフターサービスを通じて長期的に顧客をサポートする関係を築いています。
【理由】
なぜこうした関係が求められるのかというと、大型建設物は完成後の安全管理やメンテナンスが重要であり、一度工事が完了しても終わりではないからです。
長年の実績に裏打ちされた安心感に加え、新しい工法や設備の提案なども行うことで顧客の継続的なニーズに応えています。
また、一度信頼関係が築かれると次の案件でも声がかかりやすくなるため、企業にとってはリピート顧客を育てることが大きな成長につながります。
こうした姿勢が安藤ハザマの安定的な受注の一因になっていると考えられます。
顧客セグメント
安藤ハザマの顧客セグメントは、官公庁や地方自治体、民間企業、海外クライアントなど幅広い範囲にわたります。
道路や橋梁といったインフラ開発は公共セクターが主体となる一方、オフィスビルや商業施設は民間企業が発注元となることが多いです。
【理由】
なぜ多様なセグメントを狙うかというと、公共投資の増減による景気変動のリスクを分散できるからです。
さらに海外事業も成長の余地が大きく、新興国のインフラ需要を取り込むことで収益拡大を目指しています。
こうした多角化戦略を続けることで、経済情勢の変化にも柔軟に対応し、安定したビジネス基盤を築くことができるのです。
収益の流れ
安藤ハザマの収益は主に工事請負収入が柱となります。
土木や建築の大規模案件を受注し、施工から竣工までのプロセスで利益を生み出します。
さらに、設計やコンサルティングサービスなどでも収益を得ており、技術的なアドバイスやプロジェクト企画などを提供している点が特徴です。
【理由】
なぜ工事請負以外の収益源を持つのかというと、建設の計画段階から関わることでプロジェクトをトータルにサポートでき、付加価値を高められるからです。
また、メンテナンスやリニューアル工事などで継続的に利益を上げることも重要で、顧客との関係性を長く維持することで安定した売上を確保しています。
近年は環境に配慮したグリーン建築や防災関連技術のニーズが高まっているため、これらの分野でのコンサル料や新サービスも収益源として期待されています。
コスト構造
安藤ハザマのコスト構造は、人件費や資材費、外注費が大きな割合を占めます。
大型プロジェクトでは特に資材の調達コストや専門技術者の確保が重要です。
【理由】
なぜこのコスト構造が問題となるかというと、資材価格の高騰や人手不足が続くと採算が悪化しやすいため、いかに効率よくリソースを活用するかが企業の生命線になるからです。
また、研究開発に投資することも欠かせないため、これらのコストをバランスよく管理する必要があります。
安藤ハザマは長年の取引実績を活かし、サプライチェーンを安定化させながらコストを削減する工夫を重ねており、大規模案件でも利益を確保できるよう努めています。
デジタル技術の導入や新工法の開発などによって工期短縮を図り、コストを抑えつつも品質を向上させる取り組みが今後の成長にとって大切だといえます。
自己強化ループ
安藤ハザマの自己強化ループは、まず技術力を高める投資を行うことで高品質な施工を実現し、それによって評価が高まり新規案件を獲得しやすくなるという循環が基本です。
新しいプロジェクトを受注すると、そこで得た利益をさらに研究開発や人材育成に回し、技術力と現場対応力を向上させることができます。
こうした好循環は、採用面でも優秀な人材を呼び込みやすくなるというメリットを生み、現場力の強化につながります。
さらに、施工実績が増えるほどノウハウの蓄積も進み、次のプロジェクトでのリスク管理やコスト削減に活かせるという相乗効果が得られます。
大事なのは成功体験だけでなく、大型工事の採算悪化などの失敗事例からも学びを得て、再び技術や管理方法を改善する点です。
その結果、より高い水準の品質や安全性、コスト管理が可能になり、顧客や社会からの信頼をさらに高めることができます。
これを繰り返すことで安藤ハザマは総合的な競争力を維持し、長期的に企業価値を高める好循環を保っているのです。
採用情報
安藤ハザマは人材育成に力を入れており、初任給は修士了で29万5000円、大学卒で27万5000円、高等専門学校卒で25万4000円と発表されています。
休日休暇は完全週休2日制で土日がお休みになり、祝日や年末年始、夏季休暇もきちんと整備されています。
採用倍率は公表されていませんが、人気企業の一つとして堅調な応募があるようです。
平均年間給与は約963万円とされていますが、これは経験年数や役職によって上下します。
社員のキャリア形成をサポートする研修や資格支援制度なども充実しており、若手社員がスキルを伸ばしやすい環境づくりが進められています。
大きな建物を作るやりがいだけでなく、福利厚生が充実している点も就職を考える方にとっての魅力といえます。
株式情報
安藤ハザマの銘柄コードは1719で、2023年3月期の配当金は年間40円です。
株価は日々変動するため正確な情報は金融情報サイトなどでチェックする必要があります。
建設セクターは国内景気や公共投資の動向によって株価が影響を受けやすいですが、民間工事や海外事業の拡大によって安定的な収益を目指す動きも見られます。
配当利回りやPERなどの指標から投資判断するのも良いでしょう。
未来展望と注目ポイント
今後の安藤ハザマは、資材価格の高止まりや人手不足などの課題に直面しながらも、デジタル技術の導入や海外事業の拡大など多角的な成長戦略を模索しています。
例えば、AIを活用した工程管理システムや自動化施工などは生産性を高めるカギとなり、さらなるコスト削減や品質向上が期待されます。
海外に目を向けると、新興国のインフラ需要は依然として高く、技術力のある日本企業としての信頼を強みに受注を増やす可能性があります。
また、カーボンニュートラルやSDGsをはじめとする環境への配慮が世界的なテーマとなっているため、建設現場でも省エネや再生可能エネルギーへの対応が急務です。
これらの動きにいち早く対応し、付加価値の高い提案ができれば、国内外を問わず一層の成長が見込めるでしょう。
大きな課題もありますが、そうしたハードルを越えるために技術開発と人材育成を進め、新しい領域にチャレンジする姿勢が今後のキーポイントになりそうです。
企業としての柔軟性と持続的な投資意欲が今後の競争優位を生むと考えられます。
多方面の需要に応える総合力が安藤ハザマの大きな武器であり、今後もさらなる発展が期待されます。

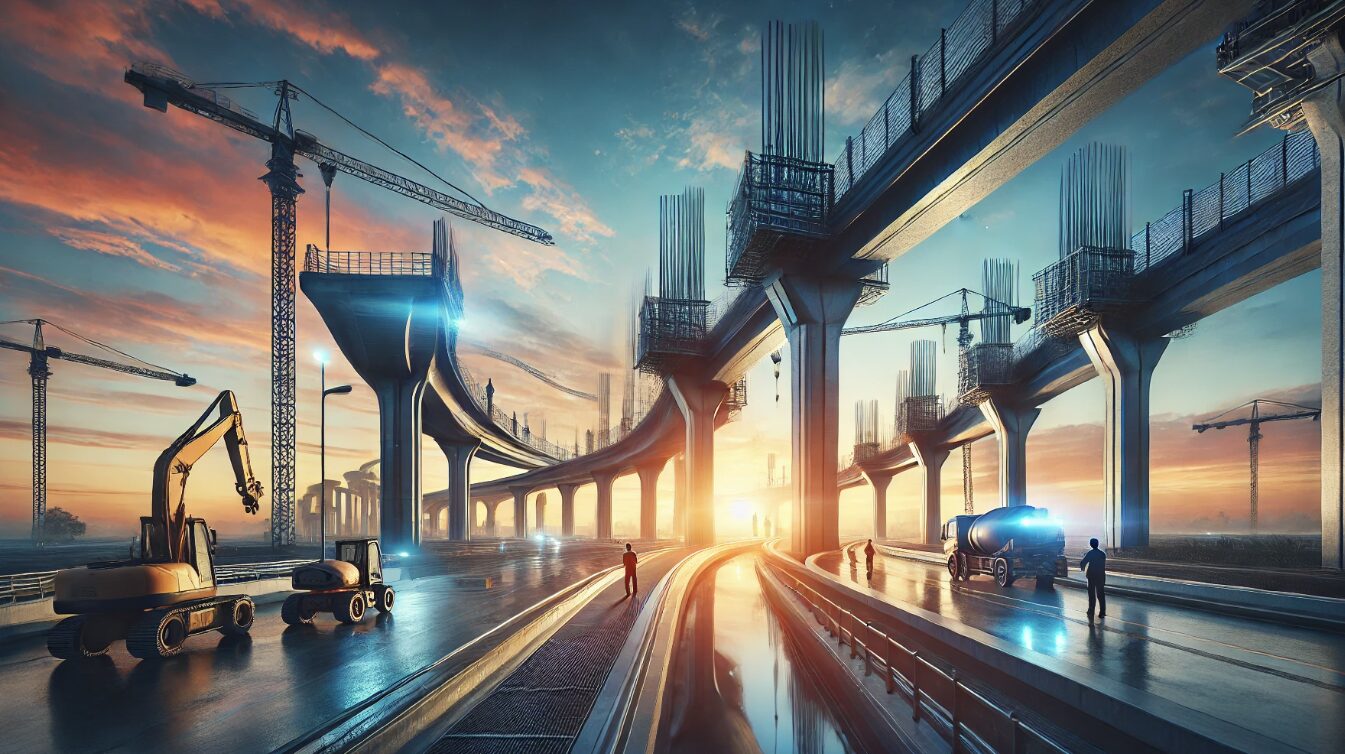


コメント