企業概要と最近の業績
株式会社オービーシステム
当社は、特定のメーカーや親会社に属さない独立系のITソリューション企業です。
金融機関向けのシステム開発、官公庁や製造・物流業向けのシステム開発、そして企業のIT基盤となるサーバーやネットワークの構築を三つの柱として事業を展開しています。
顧客の課題解決に向けて、企画提案からシステム設計、開発、保守・運用まで一貫したサービスを提供しています。
2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が27億46百万円(前年同期比9.0%増)、営業利益が2億43百万円(同25.3%増)、経常利益が2億43百万円(同25.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億69百万円(同26.0%増)となりました。
企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)投資や既存システムの刷新需要が引き続き活発でした。
金融機関向け、官公庁向け、そして事業会社向けの各分野において受注が堅調に推移し、全てのセグメントで増収を達成しました。
生産性の向上も寄与し、売上高、各利益ともに前年同期を大幅に上回る結果となっています。
【参考文献】https://www.obs.co.jp/
価値提案
株式会社オービーシステムは、金融機関から公共機関まで、多様な業種に対応したシステム開発と運用保守を行っています。
単なるソフトウェア開発だけでなく、業務効率化やDX推進といった付加価値を提供することが強みです。
これにより、顧客はITの専門知識がなくても、高度なシステムを安心して導入できるメリットを享受できます。
【理由】
同社は長年の開発経験をもとに蓄積してきたノウハウを生かし、顧客のビジネス課題を的確に捉えるコンサルティングを行ってきた経緯があります。
そうした実績が信頼を呼び、銀行や保険会社など、IT投資に慎重になりがちな分野でも安心して任せられるパートナーとして選ばれる土台となっているのです。
さらに、最近ではクラウド技術の普及に合わせて、新たなサービス形態も提案しています。
これらの取り組みが同社の強力な価値提案につながり、多くの顧客から高い評価を得ていると考えられます。
主要活動
株式会社オービーシステムが中心としている活動は、システムのコンサルティング、設計、開発、そして運用保守です。
たとえば、金融機関向けシステム開発では勘定系システムの改修やオンラインサービスの構築、産業流通分野では自動車関連の管理システム、社会公共分野では電力ICTや公共サービス関連のプラットフォーム構築など、多岐にわたっています。
【理由】
同社は創業以来、幅広い業界のITニーズに応える姿勢を持ち続けてきました。
その結果、開発だけにとどまらず、導入後の運用や保守までを一気通貫で担う体制が自然と整えられたのです。
こうした包括的なサービスの提供が可能な点が、クライアント企業にとって大きな安心材料となっています。
リソース
株式会社オービーシステムのリソースとして最も注目すべきは、高度な技術を持つエンジニア集団と50年以上にわたる業界経験です。
同社は独立系の立場を活かし、多様なシステム開発プロジェクトに参画してきました。
【理由】
銀行の勘定系システムのように高い信頼性が求められる案件から、クラウドを使った新技術の検証案件まで、柔軟に対応してきたことで、現場で培われた技術力が積み上がってきたからです。
加えて、人材の育成に力を入れ、若手エンジニアがベテランからノウハウを継承する仕組みを整えています。
このようにして経験豊富なエンジニアが数多く在籍しているため、大規模案件にも迅速かつ的確に対応できる点が強みになっています。
パートナー
同社は日立製作所グループや三菱電機ソフトウェアなど、大手SIerとのパートナーシップを築いています。
これによって大規模案件や公共事業などの開発機会が得られ、プロジェクト遂行時には多様な連携が可能になります。
【理由】
独立系として培ってきた技術力と信頼性が評価され、大手SIerの協力会社としても活躍できる環境を整備してきたからです。
大手パートナー企業と長期的な取引関係を続けることで、安定的な収益につなげるだけでなく、新しいプロジェクトの情報も早期に得られるメリットがあります。
こうした連携は、同社の成長戦略を支える大きな要素の一つです。
チャネル
株式会社オービーシステムは、直接営業だけでなく、パートナー企業を通じた間接営業も行っています。
これにより、特定の業界や技術領域に限らず、幅広い顧客への提案を可能にしているのです。
【理由】
同社の技術とサービスを必要としている企業は多岐にわたるため、すべてを自社の直接営業だけではカバーしきれません。
そこで、大手SIerなどとの協業を進めることで、接点を持ちにくい市場にもリーチできるようになりました。
このようなチャネル戦略は、受注拡大を後押しする重要な役割を果たし、売上高や利益の安定にもつながっています。
顧客との関係
同社は一度システムを導入した顧客との長期的なパートナーシップを築く傾向にあります。
ソフトウェア開発は導入後の運用や保守が不可欠なため、顧客から継続的に開発や改善の依頼を受けるケースが多いのです。
【理由】
銀行や保険会社など、重要な情報を扱う企業にとっては、信頼できるパートナーの存在が業務の安定を左右するからです。
こうした企業文化や事業特性に合わせて、同社は継続的なサポート体制を整え、問題が生じた際には迅速に対応できるよう準備しています。
その結果、顧客企業からの信頼度が高まり、長期契約が自然に成立する流れが生まれています。
顧客セグメント
株式会社オービーシステムの顧客セグメントは、金融機関(地銀・都銀、保険、クレジットなど)、産業・流通分野(自動車や製薬など)、公共機関、医療機関まで幅広いです。
【理由】
独立系であることから特定のベンダーや業界に縛られることなく、多様な技術と業務知識を積極的に吸収してきたからです。
その結果、銀行のオンラインシステムから電力ICT関連、クラウド系の新興分野まで、さまざまな業界ニーズに対応可能な総合力を獲得しました。
この幅広い顧客セグメントは、景気の変動があっても安定した売上を確保できる要因ともなっています。
収益の流れ
同社の収益は大きく分けると、システム開発の受託と、運用保守サービス、それに加えてパッケージソフトウェアの販売から成り立っています。
システム開発の受託は、大型プロジェクトにおける売上の柱となり、運用保守サービスは長期的に安定した収益源となっています。
【理由】
長年の実績に基づく高い技術力と顧客との長期的な信頼関係があるためです。
銀行や公共機関などは、一度導入したシステムを長期間使い続けることが多く、日常の運用や定期的な保守点検、新機能の追加要望などで継続的な契約が発生します。
そのため、同社のビジネスは短期的な開発利益だけでなく、保守・運用における継続的な収益にも支えられているのです。
コスト構造
コストの大部分は人件費や外注費、研究開発費などです。
高い技術力を持つエンジニアを確保するためには、競合企業と比較しても相応の投資が必要となります。
【理由】
IT業界全体でエンジニアの需要が高まっているため、優秀な人材を採用し続けるには給与や研修環境などの投資が欠かせないからです。
また、新しい技術を取り入れる研究開発費も必要になりますが、これを怠ると顧客の期待に応えられなくなる可能性があるため、同社は積極的な投資を行っています。
こうしたコストは短期的には負担になり得ますが、将来的にはさらなる成長をもたらす重要な要素と言えます。
自己強化ループ(フィードバックループ)
株式会社オービーシステムでは、「人材確保」と「受注拡大」が相互に影響し合う好循環が生まれています。
エンジニアの数と質を向上させることで、新規案件を獲得しやすくなり、結果として売上や利益が増えます。
その利益をもとに、さらに優秀な人材を採用したり、技術研修や研究開発に投資したりすることで、サービスの質が向上します。
そして、質の高いサービスや製品を提供できると、顧客の信頼を得て追加受注を獲得しやすくなり、また利益が増えるというサイクルです。
この循環を意識的に回すことで、同社は高い技術力を保ちつつ事業を安定的に拡大しています。
さらに、大手SIerとのパートナーシップによる継続案件も、このサイクルを支える要素になっています。
一度信頼を得ると、次のプロジェクトや新たな分野でも声がかかりやすくなるため、同社の成長が持続的に加速していく仕組みになっているのです。
採用情報
初任給や平均休日、採用倍率などの具体的な数字は公表されていないようですが、IT業界の中でも幅広い分野のシステム開発や運用を担当できるのが大きな特徴です。
金融から公共事業まで多様な案件があるので、若手エンジニアにとっては学べる領域が広い環境と言えます。
また、長期的に顧客企業と付き合っていくスタイルのため、しっかりと技術を身につけながらキャリアアップできる可能性が高いです。
エンジニアとして成長したい人にとっては、有望な職場選択の一つになるでしょう。
株式情報
同社は証券コード5576で上場しており、2024年3月期の配当金は1株あたり70円、2025年3月期は75円を予定しています。
2024年6月3日時点での株価は1株あたり2240円とされており、今後の成長次第では配当面でも魅力が高まる可能性があります。
増配傾向が続いていることは、長期投資を検討する上での安心材料になるでしょう。
IR資料などでも戦略を公表しており、事業拡大や新技術への投資を積極的に進めている姿勢がうかがえます。
未来展望と注目ポイント
今後の注目点は、同社が持つ豊富な業界知識をどのように新技術と組み合わせ、さらなる顧客価値を生み出していくかにあります。
特に金融業界向けのデジタル化ニーズはますます高まり、地銀や都銀のシステム統廃合やクラウド化が急務となっています。
こうした需要に対応できる企業は限られているため、同社のように長年の開発実績と高い技術力を持つ存在は市場で貴重なポジションを確保できます。
また、産業や公共インフラの分野では、IoTやAIなどの先端技術を取り入れる動きも加速しています。
同社がこれらの分野でさらなるソリューションを展開し、大手SIerとの連携を深めることで、新規受注がますます拡大する可能性があります。
こうした成長戦略を実行するために、引き続き人材確保と育成に力を入れ、安定した財務基盤を活かして研究開発を続けることが重要です。
今後、IT市場の需要拡大とともに、同社がどのようにビジネスモデルをアップデートし、新たな価値を生み出していくのかは大いに注目されます。
今後も業績だけでなく、技術面の取り組みやパートナーシップの展開にも目が離せない企業と言えるでしょう。

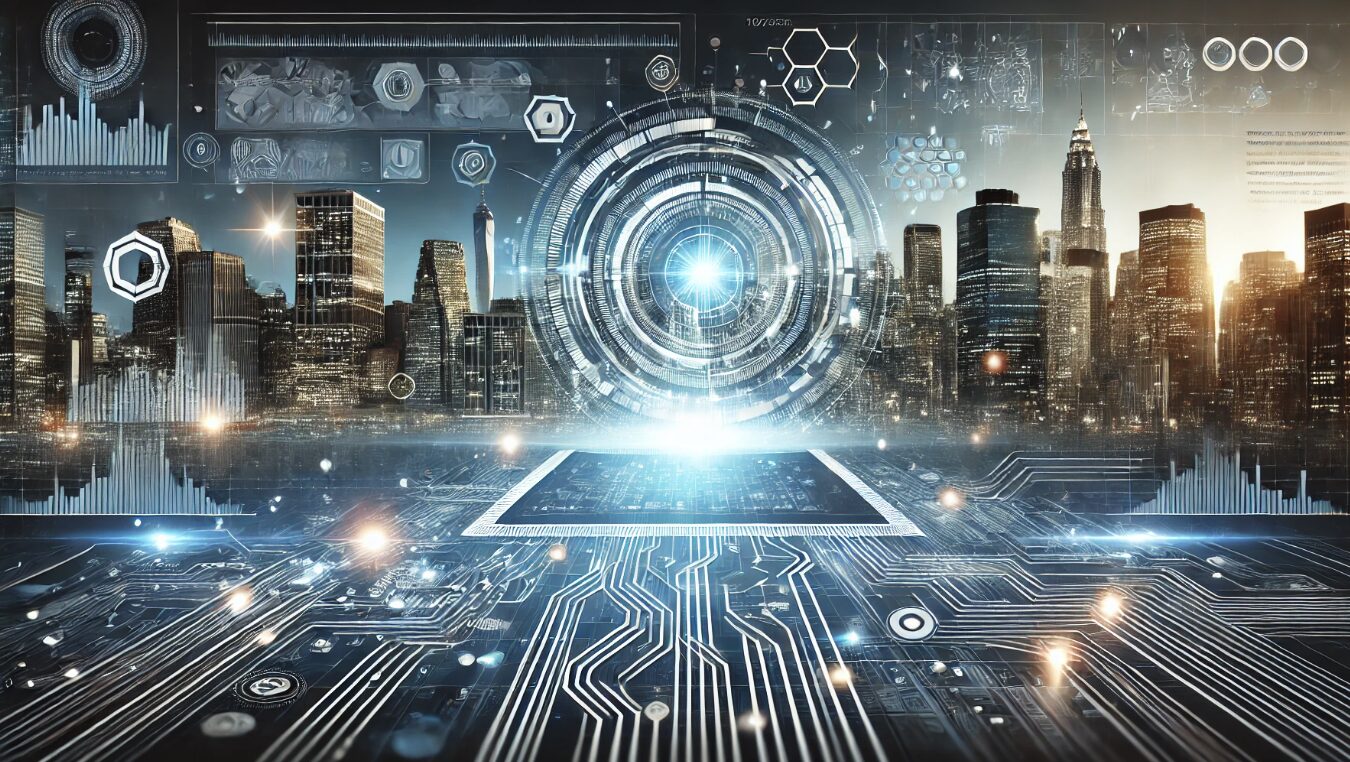


コメント