企業概要と最近の業績
TONE株式会社
総合工具メーカーです。
「TONE」ブランドで工具を製造販売しています。
主な事業は、作業工具、トルク管理機器、ボルト締結機器の製造・販売です。
「ボルティング・ソリューション・カンパニー」として、国内外で事業を展開し社会の発展に貢献することを企業理念に掲げています。
2025年5月期の通期連結業績は、売上高が75億9,100万円(前の期に比べて0.2%減)、営業利益は10億200万円(同10.9%減)、経常利益は10億9,100万円(同13.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は7億8,700万円(同16.5%減)となりました。
国内セグメントの売上高は60億6,400万円(同0.5%減)でした。
海外セグメントの売上高は15億2,600万円(同3.1%増)でした。
次期は増収増益を見込んでおり、新製品開発や原価軽減などを通じて競争力強化を図る方針です。
価値提案
株式会社TONEの価値提案は、高品質かつ多様な工具を提供することでプロの現場の生産性を上げるところにあります。
長年にわたって培われてきた技術力と信頼性の高い製品群が魅力で、特にボルト締結機器や高トルクレンチなどは国内外の工場や建設現場、自動車整備などで広く活躍しています。
【理由】
創業当初から「現場で求められる頑丈さと使いやすさを両立する」方針を貫き、大量生産だけでなく顧客の細かな要望に応じた製品開発を続けてきたことが大きいです。
さらに最近は海外市場でのニーズに合わせ、耐久性だけでなく軽量化や使い勝手を重視した製品展開を行うことでブランド力を高め、結果的に幅広い顧客層に対して「安心して使える工具」という価値を提供し続けています。
主要活動
同社の主要活動は、製品開発から製造、販売までを一貫して手掛けることにあります。
自社工場や協力工場でこだわりの工具を生産し、徹底した品質管理を実施することで耐久性と安定供給を実現しているのが特徴です。
【理由】
創業からの歴史の中で「自社で設計・開発した工具を自らの手で送り出す」という職人気質と企業理念が根付いており、その結果、生産体制を一元管理してノウハウを社内に蓄積してきた背景があります。
さらに近年は、マーケティング活動にも力を入れ、国内外の展示会やオンラインでの情報発信、ユーザーからのフィードバックを元に改良を繰り返すなど、現場目線のニーズを短期間で商品企画に反映できる仕組みをつくり上げています。
リソース
株式会社TONEのリソースは、まず長年の工具開発によって培われた技術力とノウハウです。
加えて4,000点以上という豊富な製品ラインナップは多種多様な要求に対応できる強みになっています。
【理由】
国内外のユーザーからの要望や独自の研究開発によりコツコツと商品数を積み上げてきたことと、工具の基本構造をしっかり学び上げたエンジニアたちが数多く在籍しているからです。
また、近年は海外展開にも注力しており、日本国内だけでなく海外で蓄積した市場データや製造ネットワークも貴重なリソースになっています。
こうした人的資源と製品の多様性が組み合わさることで、既存の工具市場の隙間を埋める製品から、最先端の締結技術を要する大型案件まで幅広く対応できる体制が整っています。
パートナー
同社には国内外の販売代理店や協力工場をはじめ、70社以上の海外代理店ネットワークが存在します。
これらのパートナーと連携することで、新しい市場へ効率的に製品を届ける体制が構築されています。
【理由】
ブランドをグローバルに育てるために、信頼できる地元企業との取引関係を長い年月をかけて築いてきたからです。
特に海外市場の拡大には、言語や文化の壁があるため、優れた技術を持つだけでは不十分です。
現地の代理店と協業し、その国や地域に合った営業やアフターサポートを実施することによって、ユーザーに安心感を与える仕組みを作り上げることができました。
結果として、海外の大規模プロジェクトや高度な安全基準を要する工場などにもスムーズに参入できる基盤が整っています。
チャンネル
チャネルとしては、直販によるオンラインショップや国内外の代理店ルート、さらには業界向け展示会など、多彩な方法を使っています。
【理由】
工具の購入形態は企業や個人によって大きく異なり、現場ですぐに使いたいお客様から専門商社経由で大量に仕入れたい企業まで幅広いニーズがあるからです。
オンラインでは公式サイトやECモールを通じて小ロット販売や情報発信を行い、展示会では新製品を直接手に取ってもらいながら製品性能をアピールしています。
また、代理店経由では国内外の工場や建設現場への安定した物流を確保しつつ、専門知識を持ったスタッフが導入サポートを行うことで信頼を得ています。
顧客との関係
株式会社TONEの顧客との関係は、売りきりではなくアフターサービスやカスタマイズ対応を重要視する姿勢によって築かれています。
【理由】
工具を使う現場では、「壊れにくい」「修理が早い」「定期的な点検が受けられる」といった安心感が求められるからです。
同社では長期使用が前提の製品が多いため、修理対応や部品交換などのサービスを手厚く行うことで、一度導入されたらリピートや追加購入につながりやすい仕組みを作っています。
さらに、特定の現場で使う特殊な工具の要望に応じて、形状や材質をカスタマイズするケースも増えており、そうした細やかな要望に応じることで顧客との信頼関係を長期的に築いている点が大きな特徴です。
顧客セグメント
同社の顧客セグメントは製造業や建設業、自動車産業など、業務で工具を使用する法人がメインですが、プロ仕様の道具を好む個人ユーザーの存在も見逃せません。
【理由】
プロ向け製品を手掛けることで高い品質水準を確保してきた背景があり、その信頼がホビーやDIY領域にも拡張しているからです。
さらに大型工場や建設現場のような過酷な環境に耐えられる製品を作り続けてきた実績から、「とにかく壊れにくく効率的」という印象が定着し、個人ユーザーからも支持を得ています。
こうした幅広い顧客層をターゲットにすることで、景気変動のリスクを分散しながら売上を伸ばす戦略が可能となっています。
収益の流れ
収益の流れは、主に製品販売とカスタマイズ品の受注から得ています。
法人顧客が大量に発注するケースや、特定の産業向けの特注品が収益面を支える大きな柱になっています。
【理由】
一般ユーザー向けの小売だけでなく、大規模案件や工場のライン導入に合わせた独自製品を開発し、付加価値を高めるというスタイルを長く続けてきたからです。
単なる単価競争に巻き込まれないように、高度な機能や信頼性の高さをアピールすることで、ある程度高めの価格帯でも採用してもらえる仕組みを築いています。
そこに安定的なアフターサービスを組み合わせることで、長期的にリピート発注やメンテナンス需要を獲得できる点が強みです。
コスト構造
コスト構造としては、製造にかかる原材料費や人件費に加えて、研究開発費、販売管理費などが大きなウエイトを占めています。
【理由】
高い品質を保つために工具の材質や加工技術にこだわり、研究開発段階から丁寧にテストを重ねているからです。
さらに海外展開を進めるためには、広告宣伝費や輸送費といったコストも増大しやすく、営業利益率がやや圧迫される一因にもなっています。
しかし、付加価値の高い製品開発に注力することで価格競争への巻き込まれを避け、ある程度の利益を確保しながら成長を目指す方針がとられています。
今後は量産効果の拡大や生産効率の改善を図ることで、コスト構造の最適化を進めようとしています。
自己強化ループ
株式会社TONEでは、新製品の開発が進むほど売上が増加し、その増収分を研究開発へ再投資するという自己強化ループが回っています。
これは、まず顧客の現場で生まれた課題を解決するために新製品のアイデアを取り入れ、試作品を作って販売するところから始まります。
そこから得られた売上を元に、さらに高性能で信頼度の高い工具へブラッシュアップするための開発費や実証実験に投資し、完成度を一段と高めていくのです。
そうすることで製品ラインナップが広がり、より多くの顧客層や市場にアプローチできるようになります。
それと同時に、ブランドイメージが向上して再度売上が増えるという好循環が生まれています。
このように売上と開発が相互に助け合うことで、より優れた製品が安定的に生み出される仕組みを築くことが、同社の成長戦略を支える大きなポイントになっています。
採用情報と株式情報
同社の採用情報については、初任給や年間休日、採用倍率などの具体的な数値は公表されていないため、応募や就職を検討されている方は最新の公式サイトや説明会での確認がおすすめです。
技術開発や営業だけでなく、海外事業にも積極的なので、グローバル志向をお持ちの方には魅力的な環境といえそうです。
株式情報としては、銘柄は株式会社TONE(証券コード5967)で、配当利回りは1.97%となっています。
1株当たり株価は2025年2月17日時点で1,037円です。
配当と株価の両面から、長期的な視点で安定性を期待する投資家にとっては検討材料の一つになるかもしれません。
未来展望と注目ポイント
今後の株式会社TONEは、国内だけでなく海外市場での展開を一層加速させることが予想されます。
特に新興国の建設需要や先進国の自動化工場など、プロが使う工具の需要は引き続き底堅いと考えられます。
さらに新製品開発においては、IoTを活用したモニタリング機能やデータ連携ツールなど、従来の手工具の枠を超えた技術革新が期待されます。
こうしたハイテク化によって作業効率や安全性が向上すれば、より高価格帯でも導入したいという企業が増え、結果的に収益の柱が強化される可能性があります。
また、今後は為替や原材料価格の変動リスクにも注目が必要ですが、効率的なコスト管理とブランド力の向上を両立することで、安定的に業績を伸ばすことが目指せるのではないでしょうか。
今後のIR資料にも注目しながら、同社がどのように新市場を切り拓いていくかを見守っていくと、投資家や就職希望者にとっても大きなヒントが得られそうです。

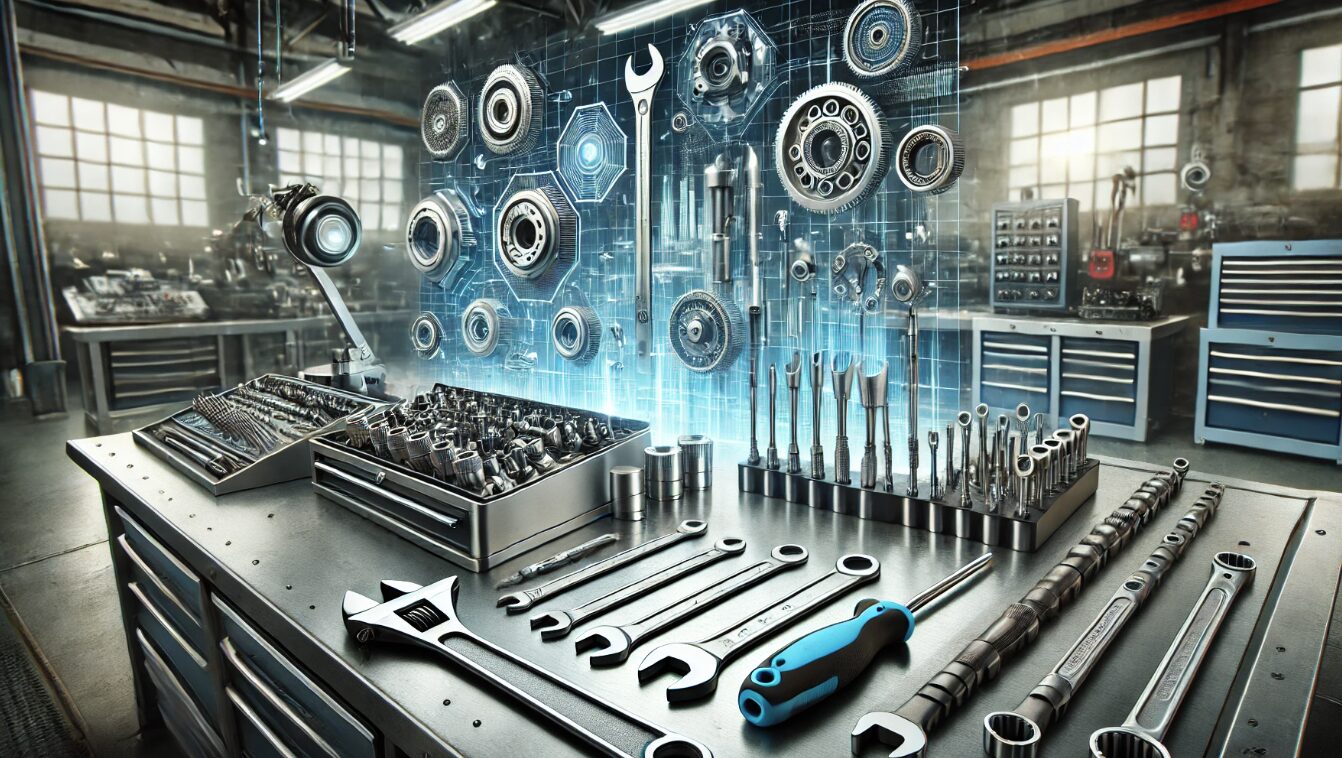


コメント