企業概要と最近の業績
NISSHA株式会社
NISSHAは、印刷技術を応用・発展させた独自の技術を核に、多様な市場で事業を展開する企業です。
事業は主に3つのセグメントで構成されています。
スマートフォンやタブレット、ゲーム機などに使われるタッチセンサーや精密部品などを手掛ける「産業資材事業」。
医療機器や使い捨て医療用部材などを製造・販売する「メディカルテクノロジー事業」。
そして、化粧品や医薬品などのサンプルの企画・製造を行う「情報コミュニケーション事業」です。
2025年12月期第2四半期の連結業績は、売上高が878億54百万円となり、前年同期比で0.6%の減収となりました。
営業利益は26億80百万円で前年同期比31.7%減、経常利益は28億2百万円で同38.8%減、親会社株主に帰属する四半期純利益は18億60百万円で同43.0%減となり、減収減益でした。
産業資材事業では、一部の顧客における生産調整の影響を受け、タッチセンサーなどの販売が伸び悩みました。
メディカルテクノロジー事業は、欧米市場を中心に医療機器の販売が堅調に推移し、増収増益を確保しました。
情報コミュニケーション事業は、原材料価格の高騰などが利益を圧迫しました。
【参考文献】https://www.nissha.com/
価値提案
NISSHA株式会社が提供する価値は、高品質な加飾フィルムやタッチセンサーなどの高度なものづくりと、医療機器の開発製造受託サービスという幅広い分野での技術力です。
たとえば自動車の内装に使われる加飾フィルムは、デザイン性や耐久性の高さが自動車メーカーに評価されています。
またタブレットや業務用端末に必要なタッチセンサーの開発においても、使いやすさと高精度を両立させたノウハウを提供しています。
さらにメディカルテクノロジー事業では、医療機器の開発から製造まで一貫して受託することで製薬企業や医療機器メーカーの負担を軽減し、品質と効率を同時に高められる点が強みです。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、複数の産業で培ってきたものづくりの経験と、医療分野へ参入するために積極的なM&Aや技術開発を進めてきた経緯があります。
こうした多角的なアプローチが、NISSHA株式会社の価値提案を豊かにしているのです。
主要活動
NISSHA株式会社の主要活動は製品開発と製造、それらを支える販売活動や顧客サポートに集約されます。
たとえば産業資材事業では最新の加飾技術を使った試作品の開発から量産までのプロセスを担い、デバイス事業ではタブレットや業務用端末に組み込まれるセンサーの開発と供給を行っています。
メディカルテクノロジー事業では医療機器の設計と実際の製造、さらには規制対応のサポートまでを包括的に手掛けることで、顧客企業の負担を減らし、医療現場に迅速かつ安全な製品を届ける体制を整えています。
【理由】
なぜそうなったのかについては、早い段階から多様な顧客ニーズに応えるための技術研究と製造設備投資を重ねてきたことが大きく影響しています。
幅広い事業分野を一貫して自社内で完結できることが、顧客からの信頼とリピートオーダーにつながっているのです。
リソース
同社のリソースは高度な研究開発力と充実した製造設備、そして製品分野ごとに専門性を持つ人材です。
たとえば加飾フィルムではデザイン担当と素材研究の専門チームが連携し、ユーザーが求める色・質感・強度を再現できる技術を確立しています。
デバイス事業ではタッチパネルの高精度化を支えるエンジニアが在籍しており、医療向けのプロジェクトにおいては厳しい品質管理体制の構築が求められるため、薬事法などの規制に精通したスタッフも育成しています。
【理由】
なぜそうなったのかという背景には、市場ごとに異なる要件に対応し続ける中で、専門知識が蓄積されていったという流れがあります。
一度確立した技術やノウハウを新しい事業領域に適応することで、効率的に経営資源を活用しているのです。
パートナー
NISSHA株式会社のパートナーは医療機器メーカーや自動車メーカー、電子機器メーカーなど多岐にわたります。
自動車メーカーとの提携では、加飾フィルムのデザインや素材の改良を共同で行うことで独自性の高い内装を実現しています。
医療機器メーカーとは製品開発受託の段階で技術要件や品質規格をすり合わせ、医療現場のニーズに合った製品を生み出しています。
【理由】
なぜそうなったのかは、同社が長年にわたり複数の業界と取引を重ねてきた実績と、複合的な技術力を獲得してきたからです。
幅広い企業との提携や共同開発を続けることで、NISSHA株式会社は自社だけでは得られない市場情報や技術を手にしており、それがさらなる製品イノベーションにつながっています。
チャンネル
NISSHA株式会社は直接の営業活動だけでなく、代理店やオンラインプラットフォームを活用し、世界各地の企業へのアプローチを実現しています。
たとえば産業資材分野では自動車部品メーカーとのタイアップを通じて最終的な自動車メーカーに製品を供給する形をとっており、デバイス分野では大手電子機器メーカーからの直接受注や、代理店を介した販売の両方を行っています。
【理由】
なぜそうなったのかという理由には、顧客の所在地や規模が多岐にわたることが挙げられます。
世界のニーズに対し柔軟に対応するため、複数のチャンネルを組み合わせる必要があるのです。
この複線的な販売戦略が、景気や需要の変動に左右されにくい安定した収益基盤を生み出しています。
顧客との関係
NISSHA株式会社は製品を納入して終わりではなく、長期的なパートナーシップを重視しています。
加飾フィルムの場合ならデザインや品質改良の要望を継続的にヒアリングし、新製品や改良版を素早く提案できる体制があります。
メディカルテクノロジー事業では開発や製造の段階から顧客と密に連絡をとり、医療現場の声を細かく反映することで性能面や安全性を高めています。
【理由】
なぜそうなったのかについては、高度な技術を必要とする分野ではアフターサポートや連続的な改良が不可欠であり、それが会社の信頼度と顧客満足度を向上させることにつながっているからです。
こうした長期的な関係づくりがリピートオーダーを呼び込み、売上の安定にも貢献しているといえます。
顧客セグメント
同社が主に対象とする顧客セグメントは、自動車産業、電子機器産業、そして医療産業です。
自動車産業では内装の意匠性や耐久性などが重視され、電子機器産業ではユーザーの操作感に直結するタッチセンサーの精度が重要視されます。
医療産業の場合は安全性や衛生面の徹底が必須であり、信頼性の高い製品を提供し続けることが大切です。
【理由】
なぜそうなったのかというと、NISSHA株式会社はもともと加飾技術を強みに家電やモビリティ分野で実績を積み上げ、それを応用してタッチセンサーや医療機器の分野にも参入を拡大してきました。
成長性の高い市場と自社の得意分野を巧みに組み合わせることで、複数のセグメントで収益を確保する戦略が機能しているのです。
収益の流れ
NISSHA株式会社の収益源は製品販売による売上と、医療機器などの受託製造サービスによる収益の大きく2種類に分かれています。
産業資材事業ではフィルムやタッチセンサーなどの素材や部品を一定数量納品し、その数量と単価に応じて収益が計上されます。
メディカルテクノロジー事業では顧客企業との受託製造契約に基づき、開発費や製造費用などが積算される形で収益を獲得します。
【理由】
なぜそうなったのかは、製品販売だけでなく医療機器開発製造という付加価値の高いサービスを提供することで、景気の波に左右されにくい安定したキャッシュフローを得ようとしたからです。
多様な収益モデルを組み合わせることで、一方の市場が低迷しても他方が補う形となり、経営基盤が安定していることが特徴です。
コスト構造
同社のコスト構造は研究開発費と製造コスト、販売管理費が中心になります。
研究開発費は新しい加飾技術やタッチセンサー技術、さらには医療機器の開発にも必要であり、長期的な競争力の源泉を生むために欠かせません。
製造コストは品質を落とさずに量産効率を高めるための設備投資や、専門知識を持つ人材の確保に投入されます。
【理由】
なぜそうなったのかというと、高品質と最新技術への投資がNISSHA株式会社の強みを維持するカギであり、国際競争力を保つためにもコスト管理と品質向上の両立を常に模索しているからです。
販売管理費もグローバルに展開するための営業活動や顧客サポートに必要であり、顧客満足度の維持に直結する重要な要素といえます。
自己強化ループ
NISSHA株式会社の成長を支える大きなポイントは、メディカルテクノロジー事業などの成長分野で得られた利益を、再び技術開発や事業拡大に再投資し、その結果として新たな収益を獲得するという好循環ができあがっていることです。
たとえば医療機器の開発製造受託で蓄積したノウハウは、規制の厳しい他国への参入や、新たに生まれる医療ニーズに素早く対応するために役立ちます。
また産業資材事業で得た技術がデバイス事業や医療機器分野に応用されることもあり、一度習得した技術や知見が別の領域での製品開発を後押しするケースも多いのです。
こうして複数の事業セグメントが互いを補完し合い、利益を生み出しては次の投資に回すという自己強化ループが形成されています。
さらに企業買収を通じて外部から得た技術や販売ネットワークを生かし、新規事業や既存事業の強化を同時に進めることで、より大きな事業シナジーが生まれているのです。
このような仕組みがNISSHA株式会社の持続的な成長を後押しし、競合他社との差別化にもつながっていると考えられます。
採用情報
NISSHA株式会社の初任給は明確に公表されていませんが、業界水準を踏まえた設定が想定されます。
年間休日は120日以上で、しっかりと休みをとりながら働ける環境を整えています。
採用倍率についても公表されていませんが、総合職や技術職など多彩な職種が存在し、自分の得意分野や興味に合わせたキャリアを築くことができるといわれています。
株式情報
NISSHA株式会社の銘柄コードは7915です。
2024年12月期の配当金については未公表ですが、業績の回復傾向が続けば配当の増額や安定も期待されます。
株価は市場や経済状況によって変動するため、投資家の方は証券会社や金融情報サイトで最新の株価を確認すると安心です。
未来展望と注目ポイント
今後の展開としては、メディカルテクノロジー事業の成長がさらに加速する可能性があります。
世界的に医療ニーズが多様化し、特に高齢化社会を迎える国々では医療機器への需要が拡大していくと考えられるため、開発製造を一貫して任せられるNISSHA株式会社の強みが生かされるでしょう。
さらに産業資材事業ではサステナブルな素材開発に力を入れており、環境対応を求める顧客が増えるほど需要が高まると予想されます。
デバイス事業も物流や小売などで導入されるタブレット端末の拡大に伴い、市場の伸びが見込まれています。
これらが相乗効果を起こして同社の収益基盤をさらに強化し、投資によって得た新たな技術を再び各分野へ還元するサイクルが強固になるのではないかと期待されます。
中期的な成長戦略としては、国内外の医療機器メーカーや自動車メーカーとの連携を深めつつ、新しいマーケットの開拓にも積極的にチャレンジすることで、更なる飛躍が目指せるでしょう。
ビジネスモデルを複数の軸で展開している同社の強みは、景気や業界の変化に柔軟に対応しながら安定的に業績を伸ばしていく点にあります。
こうした強みを背景に、今後ますます目が離せない企業といえます。

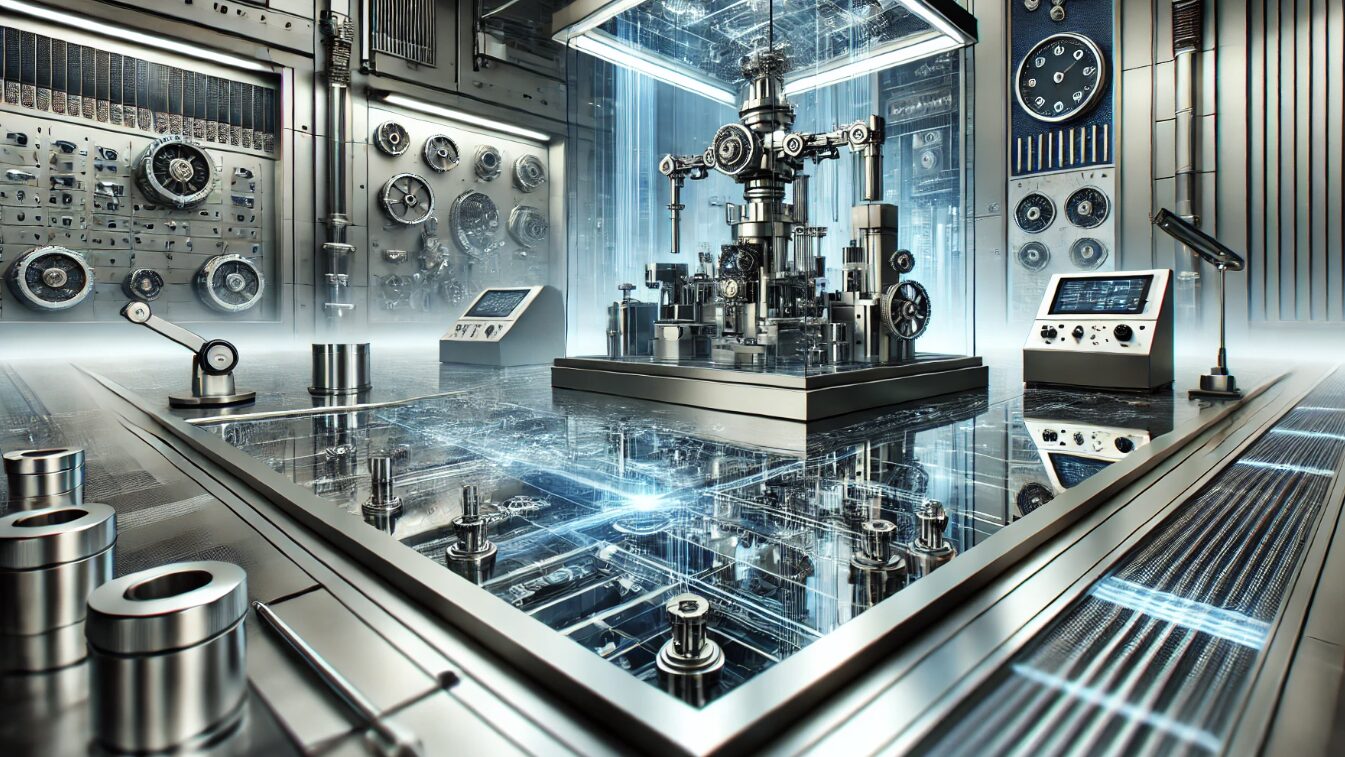


コメント